ドル円3つの市場の節目
また、日足のMACDとモメンタムはドル円の地合いの弱さを示唆している(下の日足チャートを参照)。この状況で今週の米国イベントが米金利の低下となれば日米利回り格差の縮小が進行し円高が進行しよう。
■ここ数年の円安ドル高トレンドをけん引してきたのは、日米金融政策の両股開きを背景とした、金利差の拡大が大きかったように思われます。とはいえ、過去にも日米金利差が大きく開いた時期は幾度もありましたが、ドル円がいつも素直に金利差に反応してきた訳ではありません。
為替介入が協調介入の場合であれば、海外市場で大きく円安が進んだ際に、日本は海外当局に要請して委託介入を実施できる。しかし今回のような単独介入では、それができない。日本側の材料によって、東京市場の取引時間で円安が大幅に進む局面でしか政府が為替介入をできないのであれば、介入実施の機会はかなり限られてしまうだろう。ドル円レートの大きな変動は、日本よりも海外要因で引き起こされるケースが多いからだ。
■しかし、こうした「安い円を更に売る」理由は、足元では急速に解消しつつあります。例えば、ここ数年、ドル円と高い相関を保ってきた日米の実質長期金利差(10年国債利回り)は、ここもとの円金利の上昇でにわかに縮小しつつあります(図表5)。また、中国景気の悪化やサプライチェーンの混乱が落ち着いたことから原油価格は大きく調整しており、日本の貿易赤字は大きく縮小するとともに、経常収支は大幅な黒字基調に回帰しています。
■こうしてみると、一つの大まかな目安として、日米の短期金利差が5%を下回り、更にドル円の1カ月のヒストリカル・ボラティリティが8%を超えてくると、「行き過ぎた円安」が大きく巻き戻すきっかけとなる可能性が出てきそうです。ちなみに、足元の日米の同3カ月物金利の差は5.31%(6月5日現在)ですので、政策金利に概ね連動して動く短期金利の差は、日米の政策金利が0.31%以上反対方向に動くと、5%の閾値を下回ってくる可能性が高まります。
■1995年12月末以降、約28年間のデータを見ると、日米の短期金利差(3カ月物の銀行間取引金利)が5%超の時期、ドル円の3カ月(60営業日)の騰落率は平均約1.48%のドル高となっています。また、より細かいレンジで見ると、金利差が拡大するほどドル高の傾向が強まります。しかし、同金利差が5%を下回り、4.5%以上5%未満のレンジに切り下がると、ドル円の騰落率は同約0.53%のドル安となっています(図表6)。
外国為替市場で円相場が対ドルで節目の140円超に向かう中でトレーダーは海外金利差を超える円売りの理由を探っている。
そして、FRBの利上げ幅が0.25%に縮小するとの期待が強まる時点で、米国の長期金利の上昇は一巡し、ドル高円安の流れが一巡することが期待される。今年12月のFOMCまではFRBは大幅な利上げを続ける可能性は高く、その場合、FF金利は4%台半ばから後半の水準に達する。
そのため、円安の流れが一巡するためには、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペースが明確に落ちるなど、その政策姿勢の変化が確認されることが必要となる。この観点から注目されるのは、先般のG7財務相・中央銀行総裁会議で、ドル高進行とそれを引き起こす米国の急速な利上げに対する不満が各国の間で一気に強まったとみられることだ(コラム「国際協調の揺らぎを示唆したG7共同声明:各国はドル独歩高に強い不満」、2022年10月13日)。
米国商品先物取引委員会(CFTC)が集計したデータ(毎週火曜日の取引終了後に集計したデータが金曜日の取引終了後に発表される建玉明細の報告)によれば、2月11日時点で非商業部門の円買い越し(ネットロング)は5.4万枚超と、昨年10月以来の高い水準にある。昨秋は6.6万枚でネットロングが積み上がった後に円ポジションが売り越し(ネットショート)へ転じた。この時のドル円は上昇トレンドにあり、調整売りが散見された程度の影響にとどまった。
しかし現在は、短期レジスタンスラインが形成され、かつ200日線を下回る状況にある(下の日足チャートを参照)。投機筋の円ネットロングが5万枚を超えてきた状況で、上述した米国イベントが米金利の低下要因となれば、円ロングの調整要因になり得る。このケースでのドル円は、下でまとめたサポートラインの攻防に注目したい。
先週のドル円は米経済指標で上下に大きく振れた。上昇の局面でレジスタンスラインとなったのが21日線だった(下の日足チャートを参照)。二日連続でこの移動平均線がドル円の上昇を止めた結果、短期レジスタンスラインが形成され200日線を再び下方ブレイクする状況にある。
■ちなみに、日米の3カ月物の短期金利差が5%の場合、金利差から得られるリターン(取引コスト等控除前)は1.25%になります(5%×90日÷360日)。一方、日米金利差が4.5%以上5%未満の時期における3カ月間の為替騰落率は、ボラティリティが8%を超えると平均1.35%のドル安となります。このため、低金利の円で資金を調達して高金利のドルで運用する、いわゆる「キャリートレード」の損益はマイナスに転じる可能性が高まります。
10月20日の東京市場で、ドル円レートは1ドル150円台に乗せ、32年来の安値水準を更新した。今年3月以降、ドル高円安傾向が続いており、3月22日には120円台、4月28日には130円台、9月1日には140円台にそれぞれ乗せていた。
理由1:投機筋の円買い越し(ネットロング) 今週のドル円(USD/JPY)も上下に大きく振れる不安定な展開を想定したい。警戒すべきは下値トライである。そう考える理由が3つある。まずは投機筋のポジション動向である。

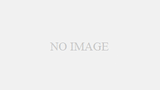

コメント