
午前の為替予想は… 下値リスク拡大 積み上がった円買いポジションの巻き戻しには注意
作成日時 :2025年3月11日7時30分
執筆・監修:株式会社外為どっとコム総合研究所 調査部 中村勉
ドル円予想レンジ
146.000-148.000円
前日の振り返りとドル円予想
昨日のドル/円は終値ベースで約0.5%安。トランプ米大統領の関税政策や米政府職員の大量解雇などにより米景気後退懸念が強まった。米株価指数は大幅に下落し、安全資産とされる米国債が買われたことで日米金利差が縮小。ドル/円は一時昨年10月4日以来となる146.63円前後まで下値を拡大した。週末にトランプ米大統領が米国の景気減速リスクを否定しなかったこともドルの上値を抑える一因となっている。本日は米1月JOLTS求人件数が発表される。米労働市場の悪化を示唆する結果となれば、一段のドル売り圧力がかかることになりそうだ。ドル/円は一時的とはいえ昨年9月から今年1月の上げ幅の61.8%押し水準(146.94円前後)を下抜けたことで、145.00円前後まで下値余地が拡大したと考えられる。一方で、投機筋の円買いポジションが歴史的な水準まで積み上がっているため、米経済指標の好結果などドル買い要因が出た場合には、短期間で大きく上昇する可能性があることは留意しておきたい。
今朝 最新のドル/円チャート

レポートの本編は「外為どっとコムレポート」でチェック

外為どっとコム総合研究所 調査部 研究員
中村 勉(なかむら・つとむ)
米国の大学で学び、帰国後に上田ハーロー(株)へ入社。 8年間カバーディーラーに従事し、顧客サービス開発にも携わる。 2021年10月から(株)外為どっとコム総合研究所へ入社。 優れた英語力とカバーディーラー時代の経験を活かし、レポート、X(Twitter)を通してFX個人投資家向けの情報発信を担当している。
経済番組専門放送局ストックボイスTV『東京マーケットワイド』、ニッポン放送『飯田浩司のOK! Cozy up!』などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
ドル円午前の為替予想 下値リスク拡大 積み上がった円買いポジションの巻き戻しには注意
金融政策、変動相場、通貨管理は、それぞれを独立に決めることができない。ドルとの為替を固定化しようとすれば、政策金利をドルと合わせなければならない。通貨管理されない状態で固定相場で金利差があると、高金利の通貨で運用し、一定期間後に固定相場で低金利通貨に戻せば、確実に利益が得られるため、高金利通貨が買われ、固定相場が維持できなくなる。つまり自由な政策金利は、通貨管理するか、変動相場とするかしか実現できない。国内のインフレをコントロールするには、金利政策が有効で、このため、通貨管理するか、変動相場とするかの選択となる。
企業や金融機関は、業務上、1年間の決まった時期に為替取引を行うと言われている。企業活動は、年単位、年度単位、4半期単位で区切りを設けるので、為替決済をそのタイミングで行いやすい。具体的には、日本企業では、年度末の3月、半期末の9月、4半期末の6月、12月である。欧米企業は、年末の12月、半期末の6月、4半期末の3月、9月である。このタイミングで海外で挙げた利益を自国通貨に交換する。よって、ドル円でいえば、3月に円高となり、6月に円安、9月に円高、12月に円安となる。4半期末の影響はどちらともいえない。しかし、実際の過去のデータで検証してみると、必ずしもあてはまらない。
企業は業務上一定周期で外貨の交換を行う傾向がある。例えば会計年度が近付くと外貨を自国通貨に交換するなどである。通貨の需要にも1年を通じた季節性がある。一般に、年末が近づくとクリスマス商戦などでドルの需要が増す。このため、ドルが高くなる。また、日本では、年度末が近づくと決済手段として通貨の需要が高まるため、円が高くなるといわれている。
ドル安となれば商品は高くなる。国際商品市場では、商品はドル建てが多い。ドルの価値が下がっても商品自体の価値が変わらなければ、ドル建ての商品価格は上昇する。ドルの指標としては、ユーロドルが代表的である。過去データを見ても、対ユーロでのドル安が原油高、金価格上昇に繋がっている。
チャートの山と谷の位置など短期的な動きでみると、ユーロとスイスフランは、相関性が高い。これはスイス中央銀行がユーロとスイスフランの比を一定に保つべく為替介入していることが影響しています。ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドルは、連動した動きをします。これは、ドルが他の先進国通貨に対して上昇や下降をしていると見ることもできます。一方、先進国通貨の中で唯一円は、別の動きをする。
為替市場の投資主体である実需筋は輸出入企業である。企業活動は1年間を一つの単位として決まった時期に為替取引をしていることが考えられる。例えばよく言われることだが、日本企業は9月と3月が決算期で9月末、3月末が近づくと、決算処理のため海外で稼いだドルを円に交換するため円高となるとか、クリスマスと年末が来る12月は、世界的にドル需要が増しドル高となるとかである。ドル円の変動率を月別に集計して見てみよう。1年間を見渡すと特徴的なのは、年前半より年後半に円高となる傾向にあることである。特に秋は円高になりやすい。年前半については、記念では奇数月が円高、偶数月が円安となっているが長期で見ると定まった傾向にはない。よく言われる点である3月、9月12月を検証する。3月末が近づくにつれ円高とはなっていないが、9月末が近づくにつれ顕著に円高となっている。12月にドル高となるとはいえない。各月の変化率をつなげて1本のグラフにしてみると、年前半にドル高となり、年後半にドル安となっている。
為替市場は、自国内で閉じた市場ではない。世界中で取引される。ドル円も主に東京市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場で24時間取引される。世界で行われる為替取引量は膨大で、為替介入は、1国だけで行っても効果が薄い。そこで世界の主要国で為替介入により通貨をコントロールする必要性について共通認識ができると、各国の中央銀行が各地の為替市場で同じ目的の為替介入を行うことがある。日本、米国、欧州で協調して行われる場合は、介入効果は大きくなる。また、直接市場介入を行わなくても、核国の中央銀行が協力して金融政策を行えば、為替市場へ間接的に影響力を行使することができる。過去、先進国蔵相・中央銀行総裁会議を通じての協調により為替が大きく動いた。
為替は、2国間の通貨の交換比率である。日本では対円での交換比率が注目されるが、国際的には、基軸通貨である対ドルでの交換比率が代表的な指標となる。為替は、2つの通貨間の交換比率なので、ある通貨の価値を見るには、どの通貨との交換比率を見るかによって異なってくる。世界経済においては、基軸通貨であるドルとの交換比率でみるのが一般的である。日本では、円建てで外貨(円以外の通貨)の価値を見る場合が多い。通貨の交換比率である為替レートは、為替市場における2国通貨の需要と供給の変化で、常に変動している。世界経済において取引量の多い先進国通貨の過去30年の動きを見てみよう。
過去30年で円とスイスフランが上昇した。円とスイスフランの動きには連動性が見てとれる。それ以外の先進国通貨は、ボックス圏での動きとなっている。先進国通貨共通の動きとしては、1980年から1985年にかけて下落し、1985年に底を付け、1985年から1995年まで上昇し1995年から2002年まで下落し、2002年に底をつけ、その後上昇し、2008年のリーマンショックで円とスイスフラン以外は急落したが、現在は回復している。先進国通貨に共通的動きが見られることは、ドルの価値の変動であると解釈できる。つまり、ドルの価値が1985年と2002年にピークを付けたのである。ドイツの通貨が欧州通貨と連動しながらも高く推移していた。長期的には円、スイスフラン、ドイツマルクが上昇していた。通貨価値がその国の経済成長と連動していたことが推測できる。
為替レートには「理論価格」というものがあり、市場で日々動く為替レートは、やがて理論価格に収れんしていくとの考え方があります。理論価格の一つに、購買力平価仮説があります。モノの価値は世界どの地域でも同じで、すなわち価格が世界共通であるとする説です。ある商品の価格が日本で100円であり、まったく同一の商品が米国で1ドルで売られていたとすると、商品の価値は日米で同じと考え、その結果100円=1ドルが妥当な為替レートとなるわけです。理論としては単純ですが留意点があります。同一の商品といっても、生産地が一つで販売先が世界各地である場合は、輸送費や関税などが異なり、同じ商品なら同じ価値(価格)とは厳密には言えません。もうひとつは、そもそも同じ商品は世界どこでも同じ価値かという疑問です。市場価格は需要と供給で決まります。需要も供給も時間とともに時々刻々と変化し、その結果価格も変化します。それならば、場所によって商品の需給関係が変化していても不自然ではありません。地域によって消費者の収入水準、原材料価格、輸送費などが異なるため、価値(価格)が異なることもありえます。この場合、価値が同じとの前提で、円建て価格とドル建て価格をイコールとして考えることはできません。しかし、絶対的な為替レートを計算できないとしても、為替レートの変化を理論的に計算することはできます。ある商品の円建て価格が5%上昇し、ドル建て価格が不変であるとしたら、円がドルに対して5%下落したと解釈するのです。個々の商品の価格の動きでは、商品固有の需給関係の事情で動くこともありますから、様々な商品の全体的動きを表す消費者物価指数の動きから為替の理論的な動きを計算します。例えば日本の消費者物価指数が1年で1%上昇したとき、米国では同じ期間に3%上昇した場合、ドルの価値が円に対して2%(3%-1%)下落したと考えます。理論的には1年で2%円高となるわけです。過去20年の日米の消費者物価指数の変化を見ると、米国の消費者物価指数は、一貫して毎年2~4%上昇しているのに対して、日本の消費者物価指数は、-1~1%であり、相対的に円の価値が一貫して上昇していることになります。円の理論値がドルに対してずっと上昇しているため、実際の為替レートでも、長期のトレンドとしては円高になると説明されます。
長期間でみれば、ほぼ一貫して上昇している。特にここ数年はその傾向が顕著である。他の先進国の通貨がユーロと似た動きをするのに対して、円の動きだけが独特である。短期的な連動性は低いが、長期的にはスイスフランと同様な動きである。円の特徴は安全通貨とみられていることだ。従来は「有事のドル」といわれ、国際経済が不透明になるとドルが買われた。これは基軸通貨であるドルが現金で、他の通貨はドルに対するリスク資産とみられ、有事の際の現金化を意味している。しかし近年、経済が不透明になる、または有事が起きると、ドルに対して円が買われ円高となる。この傾向はスイスフランにも当てはまるが、円とスイスフランとの関係では、円の方がより買われる。データの分析では、日本と米国の長期金利差の動きと為替レートの連動性が見て取れる。日本の長期金利は低く変動が小さいので、便宜上、米国の長期金利の動きだけを見ても、為替との連動性は高い。
中央銀行は為替相場の調整のために、為替介入を行います。介入が自国通貨売り、外国通貨買いの場合は、外貨準備が積み上がります。この外貨を現金のまま長期に保有することは少なく、外国債券を購入し運用する場合が多いです。このとき、持っている外貨を別の国の債権を購入しようとする場合に外貨の売買が発生します。中央銀行は、取り扱う量が大きいので、その行動が為替の変動につながります。
円ドルは、他通貨に比べ上下の変動幅は小さい。全般的なトレンドでは、上下動を繰り返しながらも上昇傾向にある。一方、円以外の通貨対ドルでは、全般的な傾向としては、上下動を繰り返しながらも上昇傾向にある。
スイスフランは、円と並んで安全通貨といわれる。昔は基軸通貨のドルも安全通貨であったが、今はスイスフランと円の2つである。投資家のリスク回避的志向が強まると買われて上昇する。スイスフラン円を見ればこの2つのうちどちらがより安全通貨とみられているかが分かる。スイスフランは円と並んで低金利通貨の代表各であるが、近年は基軸通貨のドルも低金利化しており、スイスフランと円の特徴とはいえなくなった。スイスは中立国でユーロ加盟国ではないが、スイス中央銀行の為替介入により、ユーロとの比率が一定に保たれてきた。投資家もこれを知った上でスイスフランを売買するので、中央銀行の為替介入がなくても、ユーロと連動することになる。
消費者物価指数の日米差が為替レートの変化をもたらすという理論は、長期の統計においては、ある程度の説明力がありそうです。しかし、短期的な動きを説明するものではありません。長期の為替レートの動きを説明する理論であるならば、ドル円だけでなく、他の通貨の為替レートにおいても説明力が求められます。ユーロドルの場合、欧州と米国では、消費者物価指数の差は日米ほどはありません。しかしユーロドルの為替レートは大きく変動しています。ユーロ円の場合、欧州では消費者物価指数は上昇、日本では横ばい又は下落です。この理論によると、ユーロ円はずっと下落することになります。最近のユーロ危機でユーロ円は下がっていますが、リーマンショック前まではユーロ円は上昇していました。新興国通貨とドル、又は新興国通貨と円の場合はどうでしょう。一般に、新興国の方が日米などの先進国よりインフレ率が高く、理論によれば新興国通貨が先進国通貨より下落することになります。実際の為替レートでは、リーマンショック時とユーロ危機時に新興国通貨は下落していますが、それ以外の期間では、新興国通貨がずっと上昇しています。一般に、経済が大きく成長している国は、インフレ率も高い傾向にあります。中央銀行はインフレを抑えるために金利を高く維持しています。高金利通貨は投資家にとって魅力であり、為替市場で買われやすくなります。経済がさらに発展しさらにインフレの可能性が高まると、経済の発展によるその国の通貨の需要増と、さらなる高金利の期待から、為替市場で買われ通貨高となります。金利が高くてもその分インフレであれば実質金利は低くなります。自国民にとっては実質金利が重要ですが、外国人にとっては、その国で生活することはないので名目金利だけが重要となります。高インフレ率の通貨は名目金利が高く、外国人に買われやすくなります。このため、相対的にインフレ率の低い通貨の為替レートが上昇するという理論は、当てはまらない場合が多いと言えます。


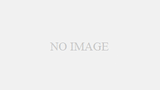
コメント