
19日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、23時過ぎに米長期金利の上昇や米国株相場が反発したことを受けて一時150.15円まで上昇したものの、米連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表後は米長期金利の低下で148.61円と日通し安値を更新した。ユーロドルは、米長期金利の上昇で1.0861ドルまで下落後、FOMC後の米長期金利の低下で1.0913ドル付近まで下げ幅を縮めた。
本日のアジア外国為替市場のドル円は、東京市場が休場で閑散取引が予想される中、植田日銀総裁のややタカ派的な見解と米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で「成長見通し引き下げ、インフレ見通し引き上げ」というスタグフレーションへの警戒感が示されたことで、軟調推移が予想される。
日銀金融政策決定会合では、予想通りに政策金利の無担保コール翌日物金利を0.5%程度で据え置くことを全員一致で決定した。
声明文では、「各国の通商政策」がリスク要因に加えられたことは、ハト派材料だが、植田日銀総裁が記者会見で「4月初めには通商政策の内容がある程度でてくる。次回の決定会合ないし展望リポートの中である程度消化できる」と述べて、「4月」や「次回会合」という時期を示したことがタカ派的と受け止められて、円高材料視された。
タカ派的な見解としては以下の通り。
・現在の金融市場の混乱は利上げの障害ではない
・現在の実質金利は極めて低い水準にある
・今後も日銀の経済・物価見通しが実現していけば政策金利を引き上げて金融緩和度合いを調整していく
・強めの春闘の集計結果を含めて賃金・物価はオントラック(想定通り)
・食料品などの価格上昇が基調的な物価上昇率に波及する可能性
オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)市場での追加利上げの時期は、7月の参議院選挙前の6月16-17日の日銀金融政策決定会合と予想されている。
FOMCでは、予想通りにFF金利誘導目標4.25-50%の据え置きが決定された。
しかし、成長減速とインフレ率上昇、というスタグフレーションへの警戒感が示され、4月からバランスシート縮小ペースの減速を開始する方針が示されたことは、間接的な利下げと受け止められた。
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」が示している今年の利下げ回数は2回、6月FOMCで▲0.25%、9月FOMCで▲0.25%、年末のFF金利誘導目標は3.75-4.00%となっている。
一方で、米WSJのFEDウォッチャー、ニック・ティミラオス記者は、昨日、「恐らく今後6カ月間は、FRBは様子見であまり何もしないと予想される」と配信している。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
市場概況 東京為替見通しドル円 今後の日米金融政策への思惑から軟調推移か
原油市場は、価格が下落すると油田開発が抑制され、供給が減ると価格が上昇に転じ、価格が上昇すると比較的高コストな油田の開発活動が促進され、再び価格が下落するというサイクルを繰り返すと指摘されている。このことは、掘削リグ稼働数の動向にも表れている。98年に価格が低迷したことから、99年の世界全体の掘削リグ稼働数が大幅に減少したが、2000年に入ってからは、稼働数は増加に転じている。
99年のユーロ誕生以降、取引コストの削減など顧客の利便性向上の観点から、汎欧州市場の創設の実現が望まれていたが、各取引市場間の主導権争いなどから、先行きは不透明なものとなっている。
このようなユーロ安の背景には、(1)欧米間の景況格差の他、(2)ユーロ圏の為替政策に関して金融・為替当局の信認が確立されていないと市場がみていること、(3)ユーロ圏の構造改革の遅れ等から海外への資本流出が続いていること、等が指摘されている。また、イギリス・ポンドの対ユーロでの増価基調も長期化しており、域内外の企業には生産拠点をイギリスから東欧などに移すべく戦略を見直す例も見られる。ブレア首相はユーロ参加に向け条件整備を急ぐ姿勢を表明しているが、2001年中にも予想される総選挙後に国民投票によって決定されるユーロへの参加の賛否が注目される(第1-5-2図)。
今次上昇局面は、産油国は、原油価格の低迷した時期に減少した外貨準備高の積み上げや巨額に膨れ上がった負債の返済を優先しているものと考えられるが、一部に先進国の資産市場へと向う動きが活発化する兆候もみられ始めている。例えば、2000年に入ってからは、OPEC加盟主要国を含む石油輸出国のアメリカ証券市場への株式投資や国債投資が大幅な買い越しとなっており、OPEC加盟国の通関ベースの輸入増加率(ドルベース)についても、99年半ばからはマイナス幅が縮小している(第1-5-27表)。
国際原油価格が主要先進国の物価へ及ぼす影響は、傾向的に小さくなっている。アメリカ、フランス、日本における、国際原油価格の上昇1%当たりの(1)国内の石油製品価格、(2)国内消費者物価への影響について、それぞれ推計した(第1-5-24図(1)、(2))。まず、国際原油価格の上昇が国内石油価格へ与える影響は、各種規制緩和の進展や市場(売買・輸送・先物)機能の発達などが波及経路(タイムラグ)の縮小をもたらしたため、70年代、80年代には反応が急速に速まった。しかし、90年代以降は反応が総じてほぼ一定の水準に保たれている。次に、国内石油価格の変動が国内消費者物価上昇率へ与える影響は、70年代の石油危機後に経済の石油依存度が低下するにつれ次第に低減し、2000年は70年代を大きく下回っている。つまり、2000年には、70年代と同程度の石油価格の上昇を受けたとしても、急激な物価上昇をもたらす可能性は低くなっているといえる。
日銀金融政策決定会合のあとは、28-29日のFOMC(米連邦公開市場委員会)が注目となる。市場では政策金利の据え置きが見込まれており、焦点は今後の金融政策に対する考え方となりそう。トランプ大統領が(原油価格の下落を条件に)FRBに値下げを求める考えを表明しており、FOMC後の31日にはFRBがインフレ指標として重視する12月のPCE(個人消費支出)価格指数の発表を控えているが、米インフレの落ち着きが確認できれば米利下げ前倒し観測が高まる可能性もある。
対円での動きをみると、99年7月以降、日本の99年1~3月期の経済成長率が大幅なプラスであったことや、日本の株価が大きく上昇した一方で米株価は長期金利上昇に伴って相対的に伸び悩んだこと等からドル安基調が続いていたが、99年末ごろからは、米株価(特にナスダック総合指数)の上昇、2000年1月初の通貨当局の円売り介入の実施、米実質GDP成長率が高い伸びを示したこと及びそれに伴う金利差拡大懸念等から増価基調で推移した。5月に入ってもアメリカの景気の過熱感が収まらず、同月16日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されたことや日本のゼロ金利政策早期解除の思惑等から減価する場面もみられたが、その後も日本の大手百貨店の民事再生法申請等に伴う日本の景気に対する不透明感や米格付け会社ムーディーズによる日本の国債格下げ等から増価基調が続いている。
18日の東京外国為替市場は、為替をめぐる日米の要人の発言などを背景にドルを売って円を買う動きが広がり、円相場は一時、およそ1か月ぶりの水準となる1ドル=155円台半ばまで値上がりしました。
このような中、市場は、当面の需給動向だけでなく、OPEC諸国の動向、とりわけOPEC総会での増減産に関する決議を注視するようになっている。これは、OPECの生産シェアや埋蔵量シェアなどが1990年代に入り再び高まっていることに加え、2000年に入り非公式ながらプライスバンド制(4)の導入を示唆するなど、OPECの市況に応じた生産調整を模索する動きが活発化していることによる。ただし、プライスバンド制については、機動的な増減産に対応できるだけの充分な余剰生産能力を擁する国は加盟国の一部にすぎないことや、増減産協定に参加していないイラクの情勢が不透明であることから、定着に至るかどうかは不確実なところが多い。
企業収益の悪化は、企業の設備投資意欲の減退を引き起こし、所得の減少や株価の下落を通じて、消費の抑制へと波及する。株価は企業収益の期待収益率を反映しているため、企業収益見通しの下方修正が発表された場合には、実際の企業収益が悪化する前に、期待成長率の低下を通じて株価は下落し、設備投資や消費が抑制される。例えば、2000年9月には、原油価格の高騰に加え、ユーロ安の影響もあいまって、アルミ、化学の大手企業や航空会社など、燃料価格高騰の影響を受け易い企業の株価を中心に、アメリカの株式市場は軟調な展開となった。今のところ、実体経済への影響はさほど大きくないものの、今後も企業収益見通しの下方修正が相次いだ場合には、株価下落を通じて実体経済へ悪影響を及ぼすことが懸念される。
一方、トランプ大統領によるFRBへの直接的な利下げ要求はFRBの独立性を揺るがすことにもつながりかねない。トランプ大統領とFRBの関係性に溝が生じるようなことでもあれば波乱含みとなるため、今後の協議は注視しておきたく、これを含めトランプ大統領の発言に振らされる動きはしばらく続くとみられる。
投資家のリスク回避の動きは幅広い市場に広がった。
アメリカの長期金利は、景気の過熱や労働市場のひっ迫感から生ずる将来のインフレ懸念を反映して99年に入ってからは上昇傾向で推移していた。しかしながら、2000年の1月に、アメリカ財務省が300億ドル規模の国債買戻し計画を発表すると、国債の供給量が減少するという期待が働き、相場は上昇傾向に転じた(利回りは低下:第1-5-6図)。また、2月には2000年度の国債入札計画が明らかにされ、その中で30年債の発行量が今後半減することが明らかなり、更に相場が上昇したことから30年債の指標性が薄れることになった。30年債の利回りは急速に低下し、10年債との利回りスプレッドは逆転した。社債との利回り差も拡大している(第1-5-7図)。また、9月末現在の金利の期間構造をみると、国債利回りでみた利回り曲線は右下がりになっているが、スワップ金利や政府保証債の利回りでみると、よりフラットな形状となっており、アメリカでは市場における先行きのインフレ懸念が2000年初よりも抑制されつつあることを表している。(第1-5-8図)。
このような中、世界最大の原油輸入国であるアメリカでは、原油・石油製品の輸入増加を主因に、99年以降は貿易収支赤字が急拡大している。それにもかかわらず、米ドルの実効レートが上昇しているのは、米国市場を経由するマネーフローのためと考えられ、産油国のこうした行動がそれを支える要因の一つとなっている可能性がある。
日銀が足元の景気や先行きについてどう見ているのか、金融政策をどう動かしていくのかを知る絶好の機会として、市場参加者の関心が非常に高いイベントとなっています。会合の結果そのものはもちろん、会合後に開かれる日銀総裁の記者会見や、会合の前後によく目にする、日銀がどう動くのかを先読み、深読みする解説記事も注目されます。それらを手掛かりに投資家らが動くことで株式市場や債券市場、為替市場に大きく影響を与えるイベントなのです。


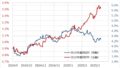
コメント