ドル円 日米の金融政策会合受け荒い動き
今週初めのドル円は、日米の金融政策決定イベントを控えて動意が鈍る中、148円台後半でスタートしました。
17日(月)は米2月小売売上高などの米指標が予想を下回ったことで一時148円台前半まで下落しましたが、その後米長期金利の上昇とともに買い戻しが進みました。
18日(火)には日経平均株価の上昇などを背景に一時149.94円前後まで上昇しましたが、米長期金利の低下とともに19日(水)未明にかけて149円台前半へと失速しました。
19日には日銀が金融政策決定会合で市場予想通り現行の金融政策を維持することを決定し、次回の利上げ時期に関する見方が定まらない中で売り買いが交錯して、ドル円は乱高下しました。
20日(木)未明には米FOMCで市場予想通り政策金利の据え置きが決定されたことが伝わり、パウエルFRB議長の会見を受けて米景気減速への懸念からドルを売る動きが強まって、ドル円は148円台前半へと下落しました。
その後米新規失業保険申請件数や米2月中古住宅販売件数が発表されると好調な結果を受けてドル買いが強まり、21日(金)には日経平均株価の上昇も支えとなって、149円台へと上昇しました。
今週のドル円は日銀会合と米FOMCを経て一時大きく下落した後上昇し、荒い動きとなりました。日米ともに金融政策決定イベントの結果は市場予想通り政策金利の据え置きとなりましたが、米FRBが示した経済見通しやパウエルFRB議長の発言から米景気減速への懸念が強まり、一時ドル売りが活発化しました。
来週は米2月個人消費支出(PCE)などの重要イベントが予定されています。日銀の追加利上げ観測と米FRBの追加利下げ観測からドル円の軟調な推移が予想される中、来週の米PCEで米景気減速を示唆する結果が示されるかどうかが注目されることとなりそうです。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
ドル円相場3 17週振り返り 日米の金融政策会合受け荒い動き
2月の米ドル/円は前月反落した流れが一段と広がり、150円の大台を割れ、一時は148円台と2024年12月初め以来の水準まで米ドル安・円高となりました(図表1参照)。2024年12月は148円台で米ドル/円下落が止まると、その後は米ドル/円の上昇再燃に向かいましたが、今回はどうなるのでしょうか。
そうであれば、米ドル/円も米ドル高・円安への戻りは限られ、一段の米ドル安・円高に向かう可能性があるのではないでしょうか。3月は、日米欧の金融政策を決める会合も予定されています。それらが、日米金利、そして金利差にどのように影響するかも注目されるところでしょう。
それを後押しした「予想以上に強い米景気」が変化するなら、米株高の「行き過ぎ」の反動が起こる可能性はあるでしょう。米国株の下落が拡大した場合、それが米金利の一段の低下、日米金利差のさらなる縮小をもたらす可能性も要注意ではないでしょうか。以上を踏まえ、3月の米ドル/円の予想レンジは、144~152円で想定したいと思います。
以上、日米の金利について見てきましたが、2月に見られた米金利低下、日本の金利上昇、それに伴う日米金利差縮小の流れが3月に大きく変わる可能性は低く、むしろさらに広がる可能性もあると考えます。
私は、1月の一部の経済指標悪化の一因は、トランプ政権スタート前の「駆け込み需要」の反動の影響も注目しています。移民の強制送還や輸入関税引き上げの前の「駆け込み需要」があったなら、政権の正式スタート後はその反動が入りやすいでしょう。そうした見立てを前提にすると、今週の米ドル/円は「米金利上昇=米ドル高」より、その逆のリスクが大きいとの考え方から、146~152円で予想します。
2月に米ドル/円の下落が拡大したのは、日米金利差(米ドル優位・円劣位)が急縮小した影響が大きかったようです。1月には日米10年債利回り差は3.6%まで拡大しましたが、2月には3%を大きく下回るまでに縮小しました。同金利差の3%割れは2024年10月初め以来で、当時の米ドル/円は基本的に145円前後で推移していました(図表2参照)。その意味では、2月の米ドル/円はより大きく下落が広がってもおかしくなかったほどの金利差急縮小だったと言ってもよいでしょう。
実は、このような現象は2017年からのトランプ政権1期目でも見られたものでした。2016年11月の大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて米金利は急騰しましたが、2017年1月から正式に政権がスタートするとむしろ9月頃まで低下傾向となったのでした。これは、選挙勝利を受けた急騰で、すでに米金利は「上がり過ぎ」となり、その反動が入ったためだったのではないでしょう。
ところが、2月に入ってから一時米金利の低下傾向を尻目に日本の金利は大きく上昇しました(図表3参照)。より金利水準の高い米金利が低下する一方、より金利水準の低い日本の金利が大きく上昇したことから、日米金利差縮小は急加速しました。では、この金利差縮小が3月はどのようになるのか、それが3月の米ドル/円の行方を考える上で最初の手掛かりになるでしょう。
もう1つ、2月末にかけて日米などの株価急落が見られました。この中でも特に米国株について、2022年にNYダウが2割以上、ナスダック総合指数は3割以上と急落したものの、2023年以降は大きな下落もないまま上昇トレンドが続いてきましたが、それが変化するのでしょうか。
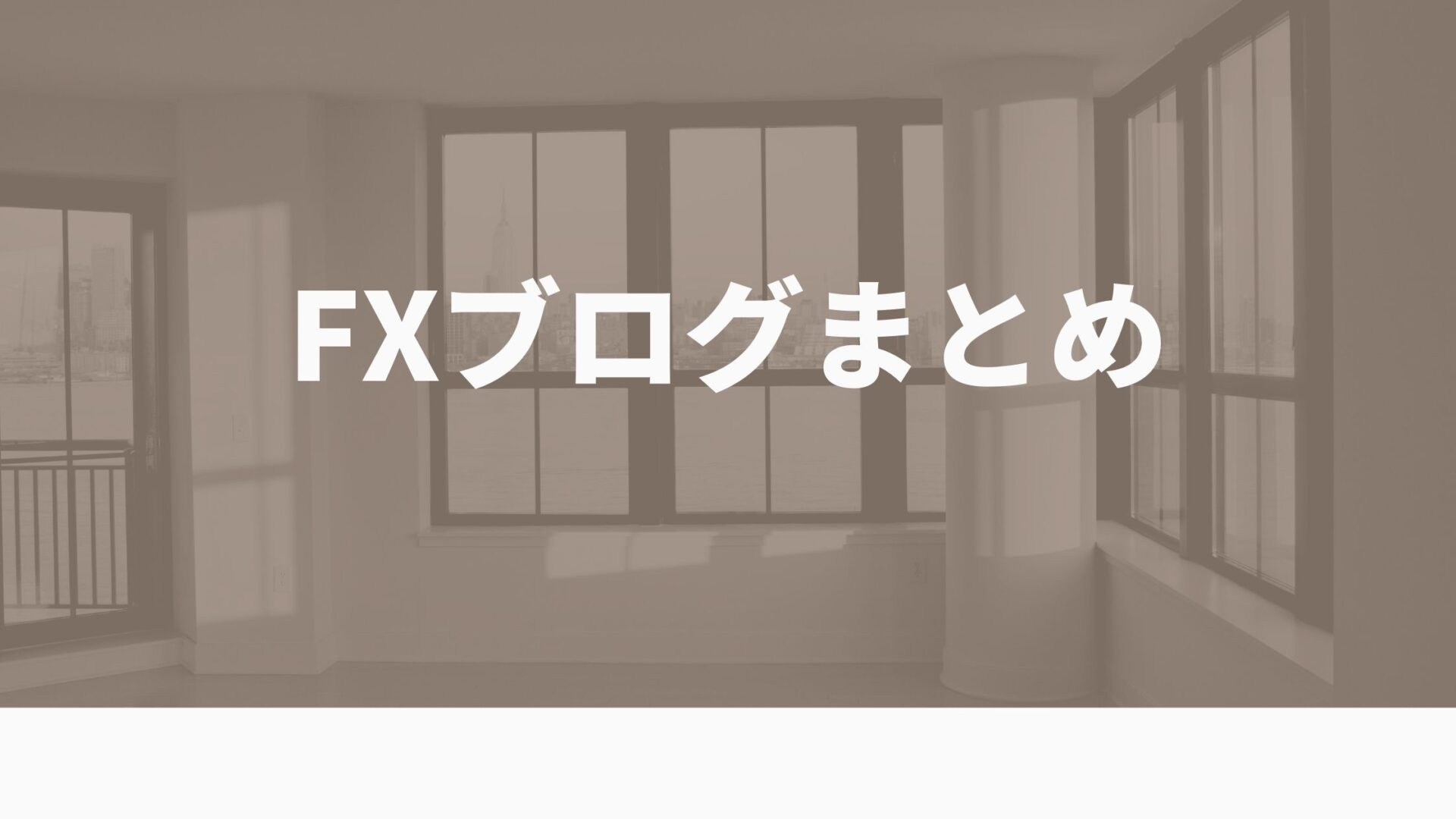
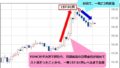
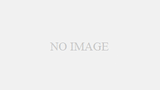
コメント