収穫迫ったワカメ 山林火災で悲劇
岩手県では公立高校の入学試験が5日から始まり、山林火災が続く大船渡市にある大船渡高校でも試験が行われました。5日朝は雨が降る中、受験生たちが保護者に車で送ってもらうなどして高校の敷地内に入っていきました。試験会場の教室では、参考書やノートの内容を確認したり深呼吸したりするなど、緊張した面持ちで試験の開始を待っていました。県内の公立高校の入学試験は6日まで行われます。
三陸町綾里の三陸B&G海洋センターの南西方向にある住宅が建ち並ぶエリアでは、多くの建物に被害が出ていました。このエリアは山林に隣接していて、建物が焼けて崩れ落ちていたり、屋根がなくなって壁だけになっていたりしていました。この付近から北に500メートルほどの場所には綾里小学校があり、校庭には多くの消防車両が集結していました。
大船渡市三陸町綾里では山林火災の影響で全域に避難指示が出されているため、最盛期を迎えている特産のワカメの収穫ができなくなっています。水産会社を経営する佐々木晶生さんは、山林火災が発生する前に収穫し、避難指示の区域外で保管していたワカメを販売しようと箱詰めの作業にあたっています。5日朝は従業員などがおよそ400キロのワカメを袋に小分けして箱に詰めていきました。箱詰めしたのは通常よりも早い時期に収穫した「早採りわかめ」で、東京・銀座にある岩手県のアンテナショップで販売し、売り上げの一部を市に寄付するということです。佐々木さんは「毎日、山林火災を見ていてストレスや不安がたまり、このままではいけないと思い始めました。復興につなげていきたいです」と話していました。
避難生活を送るワカメ漁師の熊谷建汰さんは5日、自宅があり避難指示が出ている甫嶺地区に漁船で近づき、集落の様子を確認しました。自宅は無事だとみられることが確認できたものの、3日と比べて自宅のすぐ近くまで煙が迫っていたということです。熊谷さんは、ワカメ漁を今月1日から始める予定でしたが自衛隊などの消火活動が続いているため、今シーズンの収穫を断念することも視野に入れているということです。熊谷さんは「自分の目で見てみないと自宅の被害の有無はわからないので確認した。早い鎮火を願っている」と話していました。
4日午後4時ごろ、岩手県大船渡市の現場上空からNHKのヘリコプターが撮影した映像です。このときも現場の山林からはいくつもの白い煙が上がっていました。
岩手県大船渡市で山林火災が発生してから5日で1週間となります。焼失した面積は市の面積の9%にのぼっています。市内では火災の発生以降、初めてまとまった雨が降っていて、大船渡市は地上の消防隊からの情報としてさらなる延焼は確認されていないことを明らかにし「きょうの雨が延焼を食い止める効果が少なからずあった」という見方を示しました。
大船渡市赤崎町でカキの養殖を営む鳥澤富蔵さん(64)は、自宅や養殖場のある地区に避難指示が出されているため水揚げができない状況が続いています。鳥澤さんは、赤崎町でカキの養殖をおよそ20年にわたって行っています。しかし、今回の山林火災で自宅や養殖場のある地区に避難指示が出されたため、カキの水揚げができなくなってしまったということです。鳥澤さんによりますとカキを水揚げして出荷できるのが今月末までだということで、もし、火災が続いて今月中に出荷できなければおよそ200万円の損失が出る恐れがあるということです。鳥澤さんは避難指示が出されてから毎日のように赤崎町の対岸にある漁港などを訪れて、養殖場やカキの殻むきなどを行う作業場に火が回っていないか見ています。鳥澤さんは「先が見通せず心配で早い鎮火を願っています。見えている範囲では養殖場などに被害はないようです。東日本大震災のときのようになんとか生活できるようにとにかくみんなで協力していきたい」と話していました。
三陸町綾里の綾里漁港の西側にある山林に囲われたように住宅が建つエリアでは、複数の建物が崩れていました。山林沿いの建物に被害が集中していました。
「ただ煙をみるしかない。もうワカメの収穫が迫っているのにもどかしい」。綾里地区の漁師の古川祐介さんは、対岸にあがる煙をみながらそうつぶやいた。綾里沖で昨年11月ごろから育ててきた養殖ワカメの収穫まで、もう間もなくだった。最近は海水温も低く、ワカメの状況も良かったという。
山林火災が続いている岩手県大船渡市でまとまった雨が予想されていることについて専門家は、予想どおりの量になれば地中に雨がしみこみ鎮圧に向けて大きく進む一方、再び晴れの日が続くと落ち葉が乾燥して火災のリスクが上がるため今後も火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。被害が拡大している要因について森林総合研究所の玉井幸治研究ディレクターは空気の乾燥や強風といった火災のリスクの高い状態が続き、落ち葉など地表が燃えただけでなく木の枝葉全体が燃える樹冠火も発生し延焼のスピードが上がったためと分析しています。大船渡市では5日になって雪や雨が降っていて正午までに6ミリの雨を観測したほか、6日の昼までの24時間におよそ40ミリのまとまった雨が降ると予想されています。この雨の効果について玉井さんは「数ミリ程度の雨だと枝葉にさえぎられたり落ち葉を湿らしたりして終わるが、数十ミリ降れば地中に水がしみこんで火種を消すことにもつながる。鎮圧に大きな進展がある」と話しています。そのうえで「この時期はまだ落葉樹が芽吹いていないので林床に届く光の量が多い。晴れた日が2、3日続くと落ち葉が乾燥して再び火災のリスクが上がるため、火の取り扱いには今後も注意が必要だ」と呼びかけています。
市が5日午後5時に開いた会見での発表によりますと三陸町の綾里と越喜来のほか▽赤崎町の北部にも燃え広がったということです。大船渡地区消防組合によりますと三陸町では火が▽綾里の砂子浜地区や小石浜地区の沿岸部のほか▽越喜来の甫嶺地区の山林に広がったのが確認されています。赤崎町では▽永浜地区と▽蛸ノ浦地区の山林に延焼したということです。6日以降も、消防や自衛隊が消火活動にあたるとともに、降り続く雨によって鎮火に向かっているのか火災の状況について詳しく調べることにしています。
綾里地区では、1月中旬ごろから湯通しすると鮮やかな緑色になる「早採りワカメ」の収穫が始まる。3月には2メートル近くに育った本格的なワカメの収穫時期を迎え、4月まで繁忙期となる。だが山林火災は特産ワカメの刈り取り時期を直撃した。
大船渡市によりますと山林火災は先月26日に市の南東部にある赤崎町の合足地区で発生し、その東隣にある三陸町綾里など広い範囲に拡大しました。
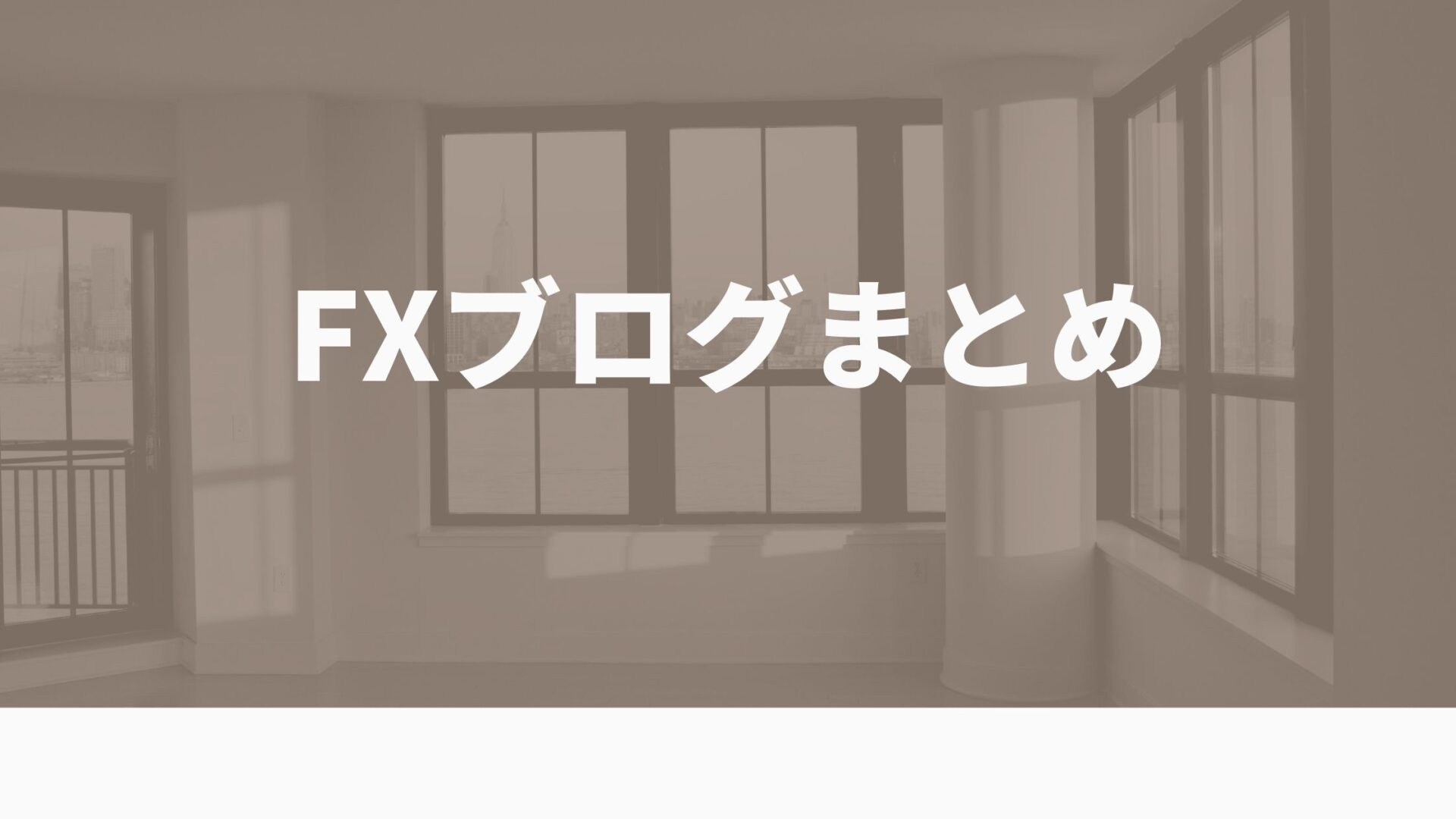


コメント