実質手取り増 第3の賃上げ とは
第3の賃上げ、つまり「従業員の手取り額が実質的にアップする福利厚生」の認知度は約半数。活用している企業は、約2割に過ぎません。一方で、すでに導入している企業では、高い満足度を得ており、エンゲージメントの向上や、採用力強化への効果を実感されています。当プロジェクトでは、「第3の賃上げ」がかしこい選択のひとつとして多くの企業に広がることを目指します。
次に、「第3の賃上げ」の導入企業にその満足度を聞くと、8割近く(75.2%)が、「非常に満足/やや満足」と回答。特に中小企業は、約9割(89.5%)に達しており、高い評価を得ていた。
一方で、長引く物価高は、生活を直撃。未だ実質賃金はマイナスを記録しており、伸び悩んでいるのが現状だ。こうした状況の中、賃上げが従業員の暮らしにどのような影響を与えているのだろうか。
続いて、「従業員の手取り額が実質的にアップする福利厚生(第3の賃上げ)」について調査。「第3の賃上げ」の認知度は、約4割(42.6%)という結果となり、昨年49.7%から微減となった。
「第3の賃上げ」とは、3社が提唱する、従来の賃上げとは異なる福利厚生を活用した新しい賃上げの手法のこと。
・第1:勤続年数、年齢、従業員の成績など企業が定めた基準で行われる定期昇給。・第2:基本給が引き上げられるベースアップ。・第3:“実質手取りを増やす”ことができる、福利厚生サービスを活用した“賃上げ”のこと。
第三の賃上げを行えば福利厚生が充実するため、離職率の低下につながり、企業内での人材の流出防止効果が期待できます。昨今の賃上げムーブメントが起こっているなかで、賃上げに対してなにもアクションがなければ、従業員の不満が高まり人材流出による人手不足が懸念されます。そのため、第三の賃上げによって実質手取りをアップさせ、従業員の満足度を上げる必要があるといえるでしょう。
定期昇給や基本給のベースアップ等の通常の賃上げは、目に見えて実感できるため、モチベーションアップや全員が自由に使える公平性の高さが支持されているようだ。第3の賃上げに関しては、福利厚生を活用するため人件費の総額が維持できることや賃金アップが難しい時の対応として支持されていた。また賃上げと福利厚生の両方が効果的だと回答した声としては、給与も福利厚生も両方大切なのでそれぞれのメリットを上手く活かしたいという意見が多く見られたという。この結果を受けて、フリー株式会社 HR事業部 社宅事業責任者 相澤茂氏は「どの賃上げが良い悪いではなくて、各会社の現状や経営課題によって最適な賃上げ方法を選んでほしい。そのためには第3の賃上げという新たな選択肢を知ってほしい」と締めた。
給与が増加する「賃上げ」は、増加分だけ税金や社会保険料の負担額も増加する。一方、食事補助・社宅などの福利厚生費は、一定条件を満たすことで非課税として処理でき、制度によっては社会保険料に影響しないため、従業員は給与で還元するよりも実質的に手取りを増やせる。企業においても全額を経費扱いにでき、税負担の軽減につながるというメリットがある。
まもなく新年度。 お給料アップを期待している方も多いかもしれませんが、「第3の賃上げ」ってしってますか?
賃上げが話題になっている昨今、実は「給料アップ」だけでは、家計の負担が軽くならないという現実があります。物価の上昇や生活費の増加で、せっかくの賃上げでも実感できないという声も多いのです。そんな中、企業が「福利厚生」を活用して、実質的な手取りを増やす「第3の賃上げ」が注目を集めています。
一方で、「第3の賃上げ」未導入の人に手取り額が実質的にアップする「第3の賃上げ」に興味があるか聞いたところ、経営層・人事担当者の7割近く(66.9%)が「非常に興味がある/やや興味がある」と回答し、一般社員の9割近く(85.3%)が「非常に導入してほしい/やや導入してほしい」と回答。「第3の賃上げ」の潜在的ニーズは非常に高いことが伺える。
また、働く方も「賃上げはうれしいけど、あまり実感がない」「手取りはそんなに増えてない」と感じる方が多いのではないでしょうか?事実、物価高に賃金の上昇が追い付かず、実質賃金は20か月連続でマイナス。税金・社会保険料などの国民負担も増加傾向にあり、同じ給与額でも実質手取りは減少しています。
昨年3位であった「従業員の生活支援(44.1%)」という回答が大きく増え、今年は1位となった。税金や社会保険料の負担増加に加え、実質賃金の停滞が続く中、企業にとっても従業員の生活を支援する重要性がこれまで以上に高まっていると考えられる。
給与が増加する「賃上げ」は、増加分だけ税金や社会保険料の負担額も増加します。一方、食事補助、社宅などの福利厚生費は、一定の要件を満たせば、非課税で処理でき、また制度によっては社会保険料にも影響しないため、給与で還元するよりも従業員は実質手取りを増やすことができます。加えて企業は、全額経費扱いにできるため、税負担の軽減につながります。

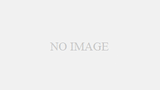

コメント