混入の公表当初控える すき家謝罪
続けて「店内カメラの映像については、具材をお椀に入れる準備工程のほか、みそ汁を鍋で作成してから保温機器(ジャー)にセットし当該お客様に提供するまでの一連の映像を確認しました。その結果、当該異物が鍋に混入する様子は確認されませんでした。混入が認められたお椀は1つです」とした。
こうした中、すき家は公式サイトでお知らせを公開し、クチコミ内容が事実であったことを認めた。
「なお、同店において同様の異物混入の恐れがある商品は当該お客様以外の方に対しては提供されておりません」という。
トラブルの発生後、当該店舗は「すぐに一時閉店し、衛生検査の実施と、異物混入に繋がる可能性のある建物のクラックなどへの対策を講じるとともに、商品提供前の目視確認など、衛生管理に関して改めて従業員に対する厳格な教育を行いました」。発生当日に所管の保健所にも相談を行い、2日後、保健所からの現地確認を受けた上で営業を再開した。
全国の店舗に向けても「異物混入を未然に防ぐために提供前の商品状態の目視確認」の徹底を周知したという。
こうした対応は、得てして「問題の本質を見誤っている」、もしくは「見ようとしていない」と認識され、誠実な対応ではないと判断されがちだ。そこで今回は、一連の経緯を振り返りつつ、ネットメディア編集者の視点から、すき家による対応の問題点を考えてみよう。
問題となっていたのは、鳥取県の店舗のGoogleマップのクチコミへの投稿だ。投稿したユーザーは、灰色のネズミがみそ汁に浸かった状態で写った写真を添え、「たまかけ朝食を注文したところ味噌汁の中にねずみの死骸が混入していました。考えられません」と訴えていた。日時は「2028年1月21日」と書かれていたが、西暦はタイプミスとみられていた。
外食チェーン「すき家」の店舗で、みそ汁にネズミが混入している事案が明らかになった。Googleマップの口コミ投稿から注目を集め、運営会社もそれを認めたのだが、SNS上では対応が適切だったのかを問う声が少なくない。
最後に「また、当社の専門部署(グループ食品安全基準本部)が、混入した異物が加熱されていたかどうかを調べる検査(カタラーゼ検査)を実施した結果、加熱されていないことを示す反応が出たことから、科学的な視点からも異物が鍋に混入した可能性は著しく低いと考えております」と締めくくった。
混入原因については、「調査を行った結果、『みそ汁』の具材をお椀に入れて複数個準備をする段階において、そのうちの1つのお椀の中に異物が混入していたと考えられています。当該従業員が提供前に商品状態の目視確認を怠ったため、異物に気付かずに提供が行われました」と説明。
異物の混入による「炎上」は、いまや珍しくない。これまでも各社で話題となり、その度に企業は、謝罪や再発防止策の公表を行ってきた。しかし今回は、「発生から2カ月後の公表」だったことから、迅速に対応していないのではないかとの反応が出ている。
ゼンショーグループの牛丼チェーン店「すき家」が22日、鳥取南吉方店で提供した「みそ汁」に異物(ネズミ...
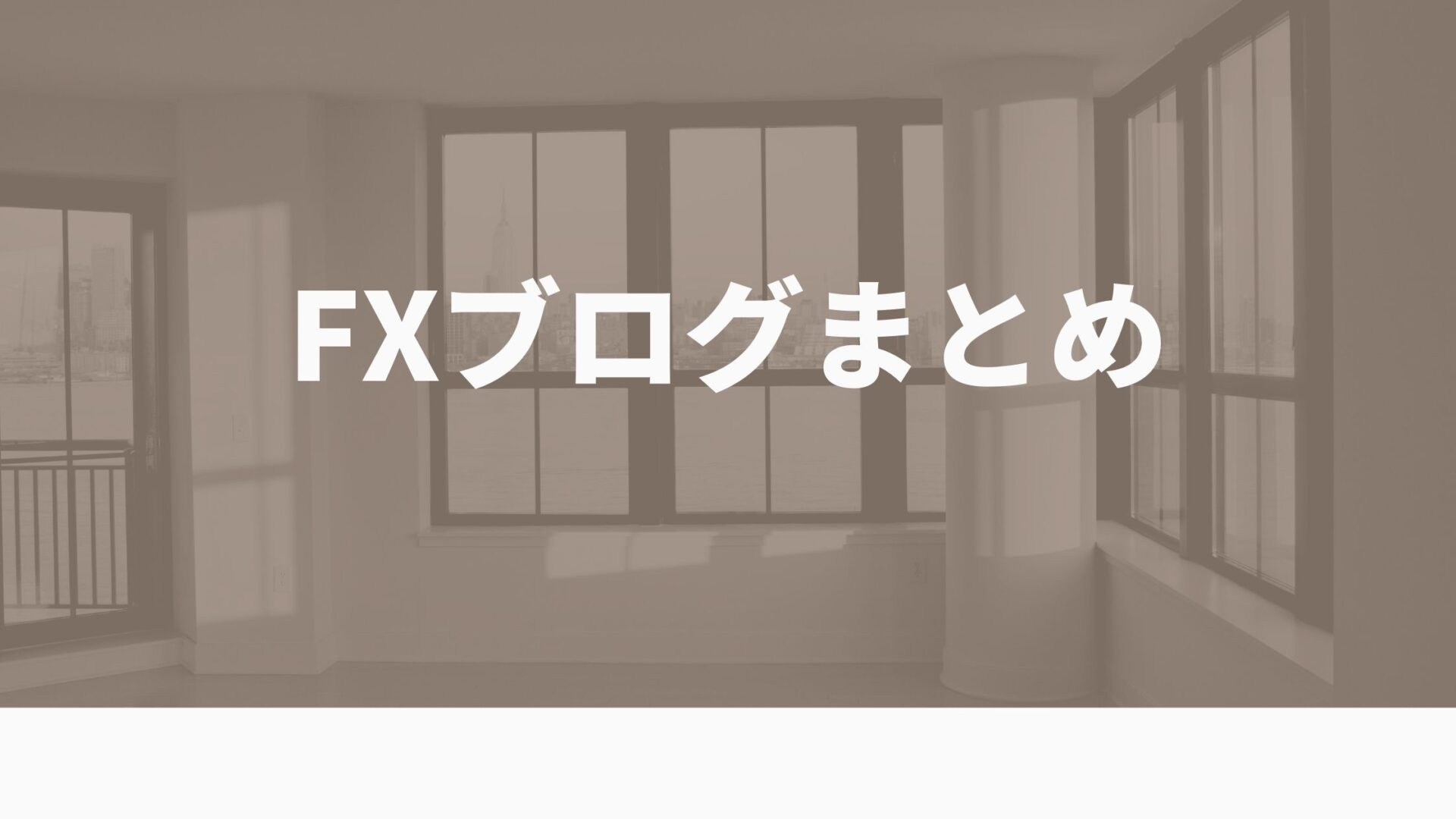


コメント