利益よりも検証すべきこと目線の合致
実証研究では、理論研究で示された各業績指標に対する顧客満足度の影響が検証されている。表1は主な実証研究の結果の一覧である。これらを総合すると、理論研究が示した通り、顧客満足度は売上高を高め(Morgan & Rego, 2006など)、広告費や販売費など顧客獲得コストを低下させることで(Lim, Tuli, & Grewal, 2020など)、純利益(Ittner, Larcker, & Taylor, 2009など)および営業CF(Gruca & Rego, 2005など)を高めることを確認できる。一方、理論研究と異なる結果として、顧客満足度の追求は粗利益率を低下させ、また運転資本や設備投資を増加させることを確認できる(Guenther & Guenther, 2021)。理論研究が最終的指標としたFCFについては検証されていない。
パネルデータの分析13)には二元配置の固定効果推定法を用いた14)。表3はその分析結果で、顧客満足度の影響は次に示す通りである。(1)売上高を高める影響について有意傾向がみられた(β1 = .0097,p = .075)。(2)原価率を低下させるが統計的有意な結果は得られなかった(β1 = −.0018,p = .391)。(3)販売管理費率を低下させる影響を確認できた(β1 = −.0043,p = .032)。(4)営業利益率を高める影響を確認できた(β1 = .0061,p = .001)。(5)運転資本増減額を低下させるが統計的有意な結果は得られなかった(β1 = −.0020,p = .479)15)。(6)営業CFを高める影響について有意傾向がみられた(β1 = .0303,p = .089)。(7)設備投資を増加させる影響について有意傾向がみられた(β1 = .0225,p = .061)。(8)FCFを高めるが統計的有意な結果は得られなかった(β1 = .0049,p = .440)。
顧客満足度がFCFへ与える影響を検証した本稿は、次の点で学術的貢献を果たす。第一に、先行研究をもとに、理論研究で示された総合的な業績指標を加えて、包括的に再検証した点である。そして、顧客満足度は本業の儲けを示す営業利益・営業CFを高めると明らかにしたことは、先行研究を補完すると考える。第二に、顧客満足度とFCFの関係性を検証した点である。理論研究では顧客満足度はFCFを向上させることが示されていたが、実証研究ではFCFまでを検証した研究はなかった。本稿では顧客満足度はFCFを向上させることを確認できなかったが、顧客満足度は本業へ貢献するが同時に設備投資の増加を招くという結果は、両者の影響を含む総合的指標であるFCFまで検証するべきであることを示す。これは、顧客満足度と企業業績に関する研究に新たな議論を導くと考える。
また、企業実務に対しても貢献を果たす。マーケティング担当者は、マーケティング投資が企業の最終利益をどのように向上させるかを立証する必要性に迫られている(Kumar, 2015)。本稿は、損益計算書やキャッシュフロー計算書の流れに沿って、顧客満足度が各業績指標に与える影響を示した点で、マーケティング投資の説明責任を果たす際の一助となるはずである。
そこで本稿は、顧客満足度がFCFへ与える影響を明らかにすることを目的に、理論研究で示された各指標を包括的に検証した二つの先行研究をもとに、利益・営業CF・FCFを加えて再検証を行う。具体的には、顧客満足度が売上高・コスト(売上原価・販売管理費)・利益・運転資本・営業CF・設備投資・FCFの各指標に与える影響を検証する。
また、新システムの導入においてもPoCは効果的です。企業が新しいシステムやプラットフォームを採用する際、PoCを実施することで、そのシステムがビジネスニーズに適しているか、予想される利益や効果が得られるかを確認します。これにより、本格的な導入前に問題を発見し、調整できます。
5フォース分析は、競合企業だけでなく業界全体の価格バランスの状況と収益構造を客観的に分析することで、自社が今後どれだけ利益を上げることができるのかを測る目的があるフレームワークである。フォースとは、自社を取り巻く競争要因のことであり、脅威を分析することによって、自社の業界における優位性を検討することができる。
これら理論研究から、顧客満足度がFCFを高める過程を次の通りに整理できる。顧客満足度は、売上高の向上とコストの低下により利益を高める。さらに、利益の向上と運転資本の低下により営業CFを高める。そして、営業CFの向上と設備投資の低下によりFCFを高める。
同様に、マーケティング効果を企業価値算出や損益計算書の流れに沿って示した理論研究として次の二つがある。Rust, Ambler, Carpenter, Kumar, and Srivastava(2004)が提唱した「マーケティング・プロダクティビティ・チェーン」は、マーケティング戦略はマーケティング資産(ブランド資産や顧客資産)・市場ポジション(売上高)・財務業績(利益やキャッシュフロー)・企業価値(時価総額やトービンのq)に繋がると示した。Rust, Zahorik, and Keiningham(1995)が提唱した「リターン・オン・クオリティ」は、顧客満足度は顧客維持と口コミによる新規顧客の獲得を通して、売上高の向上とコストの低下に結びつき、収益性を高めると示した。また、顧客満足度の過度な追求はコストの増加を招く可能性(トレードオフ)に言及し、顧客満足度の貢献はコストの視点を含む収益性で評価すべきと述べた。
企業経営のレバレッジは、財務的(機械的)なてこ入れによってではなく、「相乗効果」によってもたらされる。個々の経済活動が、当事者のみならず、経済活動が存在する、より大きな生きているシステムに利益をもたらす場合に相乗効果は生まれる。相乗効果が生まれると、全体は部分の寄せ集め以上のものになる。一方、財務的なてこ入れの働きはこれとは異なる。財務的なてこ入れは、エネルギーの継続的かつ累積的な「循環」というよりは、エネルギーの限定的かつ線形の「移動」を意味する。またこれは、リスクももたらす。事業のてこ入れを図るために多額の借り入れを行う企業が返済を負うことになるのは、言うまでもないことである。
LASが実際にどう機能するかを探るために、ラーニング・ラボラトリーから16社をフォーカス・グループとして選び出した。注目すべきは、これらの企業が、航空、自動車、化学、林産、非鉄金属、鉄鋼など、概して従来型の機械論的な経営を行う、成熟し景気循環の影響を受ける業界に多いことである。このような構成を用いるリスクは、フォーカス・グループが成長の緩やかな業界に偏ることで、LASに不利な状況を作り出すことだ。一方でメリットは、これらの厳しい業界の中で、LAS先進企業が従来型企業を抑え、莫大な利益を得ていることにスポットライトを当てることにある。
Guenther and Guenther(2021)は、売上高・粗利益率・マーケティング費および顧客獲得費率・運転資本・設備投資をキャッシュフローの構成要素として、顧客満足度の追求が各指標に与える影響を検証した。検証に用いた顧客満足度データは15年分のACSIである。そして、顧客満足度は売上高を向上させ、マーケティング費および顧客獲得費率を低下させ、顧客満足度が中~高水準の場合にそれら影響力は強まると報告した。一方で、顧客満足度が中~高水準の場合に粗利益率を低下させ、また運転資本と設備投資を増加させると報告し、顧客満足度とそれら指標でトレードオフが発生する可能性を示した。その理由について、顧客満足度が高まるにつれ、顧客ニーズへの対応として、スケールメリットの小さい在庫の確保や多額の設備投資が必要となることを挙げた。しかし、理論研究で示された、総合的な業績指標である利益や営業CFへの影響を検証していないため、顧客満足度の貢献を総合的に評価することは難しい。顧客満足度が粗利益率の低下を招くとしても、営業利益など利益指標への影響が検証されなければ、顧客満足度の貢献を評価できない。同様に運転資本や設備投資の増加を招くとしても、営業CFやFCFへの影響が検証されなければ、顧客満足度の貢献を評価できない。よって、利益や営業CFへの影響も併せて一つの実証研究の中で検証されるべきと考える。
LASの考え方の先駆者たる企業が、最良の社員や顧客、戦略的パートナー、投資家を惹きつけ、しかもその状態を維持しているのは決して偶然ではない。LASの考え方が、私たちを「彼らと手を結ぼう」という気持ちにさせるからだ。深い配慮を講じるのに費用がいくらかかろうとも、それは何倍もの売上げや利益となって戻ってくる。
顧客満足度が企業価値を高める理由として、理論研究ではフリーキャッシュフローを高めることが示されている。また、その過程について企業価値算出の流れに沿って各業績指標へ与える影響が示されている。しかし実証研究では、フリーキャッシュフローへ与える影響は検証されていない。また過程について、理論研究で示された総合的な業績指標を含めた検証はされておらず、顧客満足度の業績への貢献を総合的に判断することはできない。本稿は、理論研究で示された過程に焦点を当てた二つ先行研究をもとに、総合的な業績指標である利益・営業キャッシュフローおよびフリーキャッシュフローを加え、より包括的に再検証を行った。そして、顧客満足度は売上高の向上と販売管理費率の低下により営業利益率および営業キャッシュフローを高めるが、同時に設備投資の増加を招くことを明らかにした。しかし、フリーキャッシュフローを高めることは確認できなかった。
分析対象を規制産業である電力など公益企業に限った研究であるが、Bhattacharya et al.(2021)は、市場ベース資産理論で示された顧客満足度と売上高およびコストの関係性が公益企業にも当てはまるかについて、利益指標を含めて包括的に検証した。検証に用いた顧客満足度データは17年分の米国顧客満足度指数(ACSI)5)である。そして、公益企業では、顧客満足度は純利益を高めるが、それは売上高の向上ではなく物流費・顧客サービス費・販売管理費の低下によると報告した。ただし検証は純利益までに留まり、運転資本以降の指標は検証されていない。


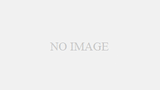
コメント