
31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが4.25%台まで上昇し、ダウ平均が560ドル超高になったことで、欧州市場の安値148.70円から150.27円まで強含んだ。ユーロドルは1.0784ドルまで下落後、「欧州中央銀行(ECB)内では4月の金利据え置きを受け入れる用意のあるメンバーが増えている」との一部報道などで、1.08ドル台前半まで下値を切り上げた。ユーロ円は欧州時間の安値161.05円から162.48円まで上値を伸ばした。
本日の東京外国為替市場のドル円は、明日発動予定のトランプ米政権の相互関税への警戒感が上値を抑える中、3月の日銀短観を見極めることになる。
トランプ米政権の相互関税に関して、先日の日銀金融政策決定会合と米連邦公開市場委員会(FOMC)は「不確実性」として、それぞれ、追加利上げと追加利下げを見送る要因としていた。明日以降、「不確実性」が深まるのか否かは不明だが、ドル円の注目水準は、上値は、50日移動平均線の151.11円や200日移動平均線の151.52円、下値は、一目均衡表・基準線の148.92円を念頭に置き、過去最大規模の円の買い持ちポジションを抱えたシカゴ筋の動向を見極めていくことになるのかもしれない。
8時50分に日銀が公表する3月の企業短期経済観測調査(短観)の大企業製造業の業況判断指数(DI)は、+12と予想されており、昨年12月調査の+14から2ポイント下落が見込まれている。背景には、明日トランプ米政権が発動予定の相互関税への警戒感、中国経済の低迷、そして、コメ価格の高騰に代表される物価上昇への警戒感などが挙げられる。
植田日銀総裁は、先日の日銀金融政策決定会合の後の記者会見で、海外発の不確実性への警戒感を示しながらも、「4月初めには通商政策の内容がある程度でてくる。次回の決定会合(4/30-5/1)ないし展望リポートの中である程度消化できる」と述べていた。
3月日銀短観の悪化、日経平均株価の下落、そして、相互関税の内容などが想定内なのか否か、今後の植田日銀総裁の発言に注目しておきたい。
12時30分に発表される豪準備銀行(RBA)政策金利は、現状の4.10%での据え置きが予想されており、注目ポイントは、声明文でインフレ見通しや金融政策に対する見解に変化が見られるか否かとなる。
2月の豪消費者物価指数はインフレの伸び率鈍化を示していたが、RBAは、単月のデータよりも四半期のデータを重要視しており、4月30日に公表予定の1-3月期CPIを待って、5月19-20日の豪準備銀行(RBA)理事会で追加利下げが決定されるのかもしれない。
オーストラリアでは、5月3日に総選挙が予定されており、政権交代の可能性もあることで、予断を許さない政治・経済状況となっている。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
市場概況 東京為替見通しドル円は3月日銀短観 豪ドルがRBAの金融政策に要注目
12日01:02 イエレン米財務長官 「ドルに対抗できる通貨はおそらく存在しない」 「極端なボラティリティでは市場介入が適切となり得るだろう」 「他国が通貨を操作すると米国は強く反応する」
10日の豪準備銀行(RBA)理事会では、政策金利4.35%の据え置きが決定されたが、労働市場に関しては、賃金上昇率の低下や労働生産性の伸びの弱さが言及されており、雇用情勢が悪化した場合には警戒しておきたい。
また、先日、氷見野日銀副総裁が来年1月14日に神奈川県金融経済懇談会に出席し、その後記者会見を行う、と報じられていた。すなわち、来年1月23-24日の日銀金融政策決定会合の前に、氷見野副総裁が日銀の政策運営に関する考え方を市場に伝えることで、7月31日の政策金利0.25%への引き上げという植田ショックの再現を回避する目論見ではないか、との見方が強まっていた。
豪ドル/円は、前回RBAが見送り予想もあった中で、結果的に利上げを行うとそれをきっかけに一時は97円台後半まで上昇した。ただこの時点で、90日MA(移動平均線)かい離率はプラス7%以上に拡大した(図表2参照)。
11月のRBA理事会では雇用市場の大幅な悪化を警告し、将来のデータによっては金融緩和が必要になる可能性が示唆されていた。
経験的には、同かい離率がプラス10%に近付く中で、短期的な「上がり過ぎ」懸念が強まる。その意味では、7月4日にRBAが利上げを決定し、それを受けて豪ドル/円が上昇に向かった場合でも、6月の豪ドル高値を大きく上回るようなら、短期的な「上がり過ぎ」懸念が強まる可能性はありそうだ。
次に、5年MAかい離率から、中長期的な豪ドル/円の評価について考えてみよう。豪ドル/円の5年MAかい離率は、6月末の段階でプラス17%以上に拡大した(図表3参照)。2000年以降で見ても、同かい離率がプラス20%以上に拡大したのは3回しかなかったことを考えると、足元でも豪ドル/円は中長期的な「上がり過ぎ」懸念が強くなっている可能性がありそうだ。
11日23:52 カナダ銀行(BOC、カナダ中央銀行)声明 「理事会は政策金利を0.50%引き下げ、バランスシート正常化政策を継続」 「世界経済は10月時点の想定通りにほぼ進展している」 「米国では、消費が堅調で労働市場が堅調なため、経済は引き続き幅広い分野で力強い状態にある」 「米国のインフレは安定しているが、物価上昇圧力は依然として残っている」 「ユーロ圏では、最近の指標は成長の鈍化を示している」 「中国では、最近の政策措置と堅調な輸出が成長を支えているが、支出は依然として低迷している」 「世界的な金融状況は緩和し、カナダドルは米ドルの幅広い分野での強さに直面して下落している」 「第3四半期の経済成長率は1%で、10月時点の予測をやや下回り、第4四半期も予測より弱い見通し」 「賃金の伸びは緩和の兆しを見せているが、生産性に比べると依然として高い」 「米新政権がカナダから米国への輸出品に新たな関税を課す可能性が不確実性を高め、経済見通しに影を落としている」 「CPIインフレ率は夏以来約2%で推移しており、今後数年間は平均して2%の目標に近づくと予想」 「理事会は6月以降、政策金利を大幅に引き下げてきた。今後は政策金利のさらなる引き下げの必要性を1つずつ判断していく」 「我々の決定は、今後得られる情報とインフレ見通しへの影響の評価に基づいて下される」 「BOCはインフレ率を2%の目標に近づけることで、国民の物価安定を維持することに尽力する」
翌日物金利スワップ(OIS)市場が織り込む18-19日の日銀金融政策決定会合での0.25%の利上げ確率は、12月初めに66%程度まで上昇していたが、現状は19%台まで低下してきており、1月会合での利上げ確率は50%台に上昇している。
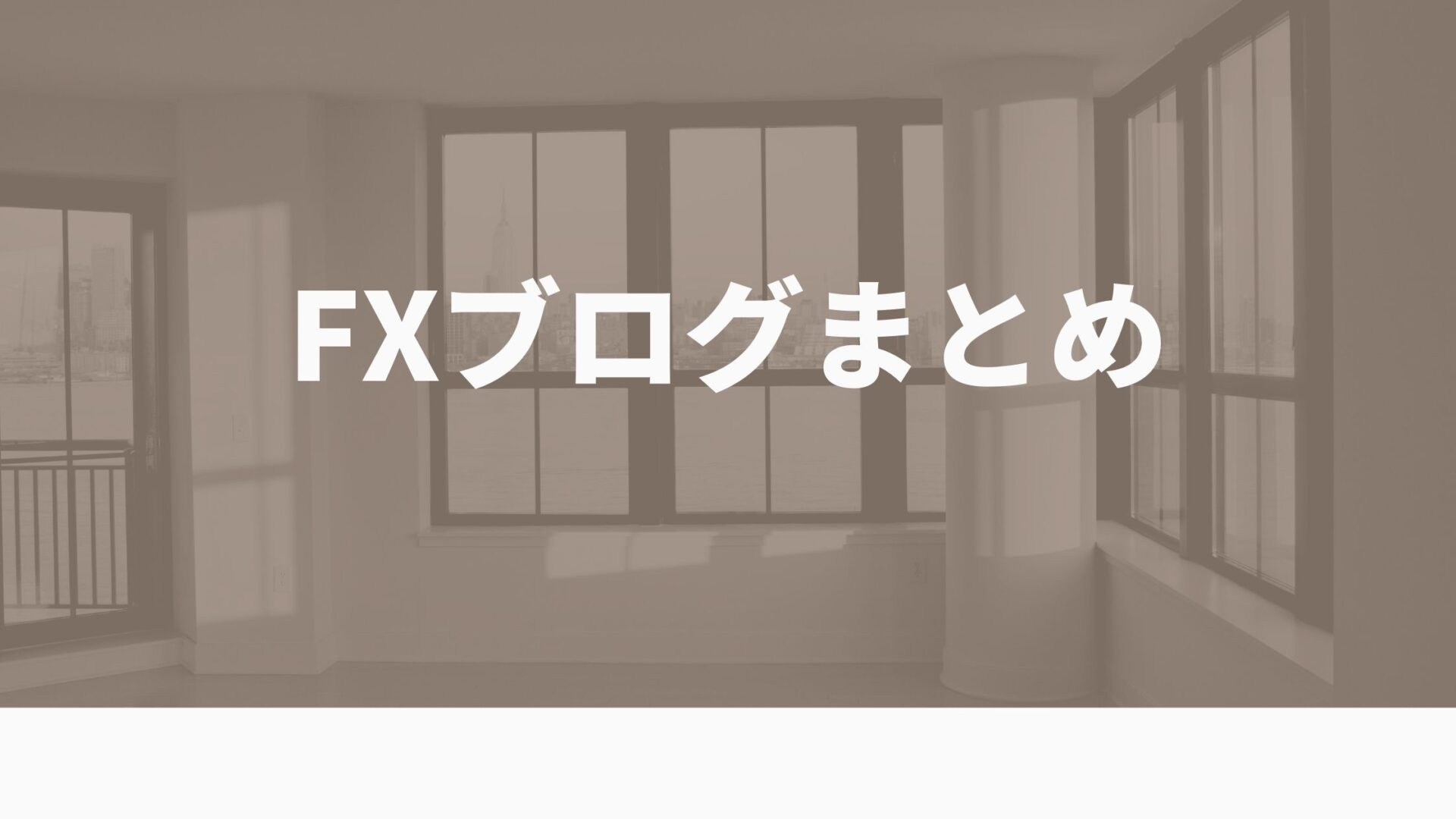


コメント