bZ4Xは2022年にトヨタ初の量産EVとして発売された
定額制サービスの導入は、収益面にも寄与しそうだ。EVでは車載電池が車両コストの3―4割を占め、EVビジネスの採算性悪化の要因となっていると言われる。電池の回収から再利用までの循環システムを確立できれば、定置型蓄電池への再利用など、新たな付加価値も期待できる。またトヨタの前田昌彦副社長はメンテナンスや機能更新なども含め「バリューチェーンを通した期待値も持てる」と話す。市場性だけでなく収益性の見極めが、bZ4Xに課せられたもう一つの試金石となる。
トヨタは、革新的で安全かつ高品質なモノづくりやサービスの提供を通じ「幸せを量産する」ことに取り組んでいます。1937年の創業以来80年あまり、「豊田綱領」のもと、お客様、パートナー、従業員、そして地域社会の皆さまの幸せをサポートすることが、企業の成長にも繋がると考え、安全で、環境に優しく、誰もが参画できる住みやすい社会の実現を目指してきました。現在トヨタは、コネクティッド・自動化・電動化などの新しい技術分野にも一層力を入れ、モビリティカンパニーへと生まれ変わろうとしています。この変革の中において、引き続き創業の精神および国連が定めたSDGsを尊重し、すべての人が自由に移動できるより良いモビリティ社会の実現に向けて努力してまいります。
「トヨタ FCHV-adv」
燃料電池「トヨタFCスタック」とリチウムイオン電池の電力により、4輪のインホイールモーターを駆動。FCシステム効率の高効率化、水素タンクの高圧化により、航続距離500km(10・15モード)を実現。
トヨタ自動車が発売する初の電気自動車(EV)専用車「bZ4X」
トヨタと日野自動車(株)が共同で開発。車体をはじめバス固有の分野を日野自動車(株)が担当し、トヨタは燃料電池システムに関する部分を担当。また、両社がそれぞれ培ってきたハイブリッド技術やノウハウを活用している。
bZ4Xは2022年にトヨタ初の量産EVとして発売された。現在は元町工場(同市)でハイブリッド車などと同じラインで生産しているが、高い製造コストが課題だった。24年に世界で販売したEVは、前年比3割増の約14万台と伸びている。
同クラスのガソリン車に対し日本のモード燃費2倍の目標を掲げて開発されたトヨタハイブリッドシステム(THS)は2モーター(駆動用、発電用)、ニッケル水素電池、動力分割装置を有するシステムである。エンジンは熱効率の高いアトキンサイクルをモーターは永久磁石モーターを採用した。
新工場は、敷地1,825エーカー(約7.4平方キロ)で、HEV用バッテリー生産ライン4本、BEVおよびPHEV用生産ライン10本の計14本の生産ラインが稼働する予定だ。2030年までに全ての生産ラインの立ち上げを計画しており、最終的には年間生産能力30ギガワット時(GWh)以上を見込む。生産されるバッテリーは、2024年にトヨタがBEVの3列シートSUV(スポーツ用多目的車)生産と併せバッテリーパック組立ラインの設置を発表したケンタッキー州とインディアナ州の製造拠点に供給される(2024年2月8日記事、2024年4月26日記事参照)。
充電インフラの拡充にも取り組んでいきます。今後のBEV普及進度を踏まえつつ、2025年を目途に、全国のトヨタ販売店に急速充電器を設置していく計画です。まず本年は、BEV需要が高い地域を中心に順次設置を進めていきます。
2003年のモデルチェンジ時にハイブリッド・シナジー・ドライブ(HSD)のコンセプトであるエコとパワーの高次元での両立を目指し、ハイブリッドシステムを全面的に改良。新世代トヨタハイブリッドシステム(THSⅡ)を搭載し、世界最高レベルの燃費35.5km/Lと低エミッションを実現した。THSⅡは可変電圧システムの採用によりモーター出力を約1.5倍に高め、ハイブリッドならではの応答性の良さ、なめらかさ、力強さを飛躍的に向上させた走りを実現。ハイブリッドシステムの特長を活用した世界初のEVドライブモード、縦列駐車時のステアリング操作を補助するインテリジェントパーキングアシストを採用。
トヨタ自動車は、初の電気自動車(EV)専用車「bZ4X(ビーズィーフォーエックス)」を、5月12日に国内発売する。新車としては初めて、売り切り型ではなくサブスクリプション(定額制)サービスの「KINTO(キント)」のみで販売する。ユーザーの不安払拭(ふっしょく)と利便性向上に加え、車載電池の回収モデルやコネクテッド機能を活用した更新サービスなど、EV時代の新たな販売モデルの確立を目指す。


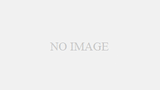
コメント