動画配信期間:公開日から2週間
動画の内容をギュッと要約
日本株の状況
日本株は今年最弱の株式市場となっており、年初から10%以上下落
日経平均、一昨日はトランプ氏の関税発動で約4%(1500円)下落
昨日は他国が戻し相場となったが、日本は0.2%(6円)しか上昇せず
4万円の水準はかなり遠くなってきた印象
日本市場の弱さの要因
日銀の利上げの影響
円安ではなくなったことによる企業収益の低下
アメリカのナスダック(ハイテク株)の調整が日本市場にも波及
石破首相が消費税引き下げを拒否した影響
市場をリードしてきた銀行株の下落
アメリカ市場の状況
関税問題で騒がれているが、日本ほど大きく下落していない
S&P500は約1%の下落にとどまる(ナスダックは約9%下落)
明日(4月3日)のトランプ大統領の関税措置発表が注目される
ベッセント財務長官の発言によると、発表される税率は上限で、交渉次第で下がる可能性も
米国経済指標の弱さ
第1四半期の貿易赤字が拡大
アトランタ連銀の予想ではマイナス3.7%
製造業PMIも悪化
雇用動態調査で求人数が減少
原油・金相場
原油は一時71ドルまで上昇も、関税問題で下落
トランプ大統領とロシア大統領の摩擦でロシアへの制裁が予想され、原油供給減少懸念から再び上昇
金(ゴールド)は過去最高値の3148.88ドルを更新後、現在は3111ドル程度
金価格の上昇は市場の不確実性を象徴
結論
現在の市場は不確実性が高く、特に日本市場は弱い状態が続いている。明日(日本時間:4月3日朝)のトランプ大統領による関税発表が市場の方向性を決める重要な要因となるだろう。関税問題が落ち着けば株価が戻す可能性もあるが、米国の経済指標の弱さや雇用状況の悪化など、景気に良くない要素も多い。トランプ政権の政策の結果がまだ見えておらず、当面は不安定な相場が続くと予想される。
お知らせ:YouTubeでも外為マーケットビューを配信中
外為市場に長年携わってきたコメンテータが、その日の相場見通しや今後のマーケット展望を解説します。

野村雅道 氏
FX湘南投資グループ代表 1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行。82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。 87年米系銀行へ転出。外資系銀行を経て欧州系銀行外国為替部市場部長。外国為替トレーディング業務ヴァイスプレジデントチーフディーラーとして活躍。 財務省、日銀および日銀政策委員会などの金融当局との関係が深く、テレビ・ラジオ・新聞などの国際経済のコメンテイターとして活躍中。為替を中心とした国際経済、日本経済の実践的な捉え方の講演会を全国的に行っている。現在、FX湘南投資グループ代表。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
トランプ相互関税を前に弱い株式市場金 ゴールド は高値更新株価
田嶋智太郎氏 経済アナリスト 慶應義塾大学を卒業後、現三菱UFJモルガン・スタンレー証券を経て、経済アナリストに転身。現場体験と綿密な取材活動をもとに、金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産掲載まで幅広い範囲を分析・研究。 WEBサイトで経済・経営のコラム執筆を担当し、株式・外為・商品などの投資ストラテジストとしても高い評価を得ている。 また、「上昇する米国経済に乗って儲ける法」など書籍も手掛けるほか、日経CNBCレギュラーコメンテーターも務める。
米国株は高安まちまちでした。
■4営業日続落して取引を終えた。トランプ米大統領の関税を巡る発言を受け、世界的な景気減速への懸念が高まり、投資家のリスク回避の姿勢が強まった。STOXX欧州600種指数は月間で4.18%安。
■31日㈪のNY株式市場、ダウ平均は下げて始まったものの、プラス圏に浮上し大幅反発となった。この日の3月調査のシカゴPMIが予想を上回ったことをきっかけに、ダウ平均は下げ渋った。ダウ平均は先週末の流れを引き継いで下げて始まり、取引開始直後に一時435ドル安まで下げ幅を広げていた。 ■シカゴPMIは製造業とサービス業の両方の企業景況感指標だが、2023年以来判断基準の50を下回る状況が続いている。しかし、今年に入って改善の兆候も見せており、今回は47.6と2023年11月以来の水準に上昇した。消費者や企業の信頼感を示すソフトデータに弱い内容が相次ぐ中で、本日のシカゴPMIは一服感を与えたようだ。一方、IT・ハイテク株は上値が重く、ナスダックは大幅安から下げ渋ったものの、マイナスで終えている。 ■今週のトランプ大統領の関税計画に向けて警戒感を高めている。各国に相互関税が発動されるものと思われるが、その詳細も不明な中、明確化を待っている状況。トランプ政権が以前に発表した関税の多くも週内4月3日に発効される。その日はトランプ大統領が「解放の日」と呼んでいる日であり、その中には自動車に対する25%の課税も含まれる。なお、トランプ大統領は4月2日にホワイトハウスのローズガーデンで開催されるイベントで関税を発表する模様。 ■関税を巡る景気とインフレへの不透明感が株式市場の重石となっており、スタグフレーションへの懸念も高まっている。週末になってもトランプ大統領は不安を和らげるようなことはなく、一部では、大統領が最近、関税に関してより強硬な姿勢を取るようアドバイザーたちに迫っていると報じられている。トランプ大統領はTVインタビューで、外国の自動車メーカーが新たな関税により値上げをしても「気にしていない」と述べていた。 ■ストラテジストからは、「関税リスクは十分に伝達されており、市場の大部分で織り込み済みです。そのため、解放の日が訪れても、それほど大きな衝撃はないかもしれません。しかし、貿易戦争で勝者となる者はなく、世界経済の成長見通しには暗雲が立ち込めている」と述べた。 ■なお、本日で第1四半期が終了だが、S&P500は年初来で4.6%の下落となったほか、ナスダックは10%超の下落。四半期での下落は23年7-9月期(第3四半期)以来。
折しも、先週は1月の米消費者物価指数(CPI)と米生産者物価指数(PPI)の結果が強めに出たことで、インフレ再燃への警戒が強まり、米連邦準備理事会(FRB)による追加利下げが「年内は難しい」との見方も市場の一部で燻り始めていた。ただ、このような状況にあってはトランプ氏も「より緩やかな関税措置を採用せざるを得なくなるのでは」、「関税と移民政策の双方においてやや穏健な措置に留めようとするのでは」との見方も市場に浮上し始めており、少なくとも過度な不安は薄らいできている。
■米国債利回り(10年債)は、4.211(-0.038)と6営業日、続落へ。序盤は低下して始まったものの、この日のシカゴPMIをきっかけに米株式市場に買い戻しが入ったことから、利回りも下げ幅を縮小。一時プラス圏に浮上したものの、今週のトランプ大統領の関税計画の公表を控えて警戒感は根強く、利回りは低下している。2-10年債の利回り格差は+34(前営業日:+32)とイールドカーブはややフラット化。
■米金融大手ゴールドマン・サックスは、米関税の影響を考慮し、米国とユーロ圏の経済成長率予想をいずれも引き下げた。同時に、米連邦準備理事会(FRB)と欧州中央銀行(ECB)の年末にかけての利下げ回数について、いずれも従来予想より1回分多く利下げを実施するとの見通しに修正した。
実際、先週末にかけて米10年債利回りは4.5%割れの水準に低下しており、とりわけ13日の米株市場では米金利低下を好感して米主要3指数がともに大きく上昇。翌14日のNYダウ平均は反落となったものの、これはあくまで3連休前のポジション調整が主因と見られる。この日発表された1月の米小売売上高の結果がここ2年近くで最大の落ち込みとなったことで、それが投資家心理の重荷になった可能性もゼロではないが、1月は暴風雪や山火事の影響が小さくなかったことと、何より前月(12月)の数値が「トランプ関税を見越した駆け込み消費」によって嵩上げされたことに対する反動が生じた部分が大きかったと考えられる。つまり、ある程度の落ち込みは想定内であった。
トランプ関税が米国株を翻弄している。24日はトランプ米政権の関税政策への警戒感が後退しハイテク株を中心に上昇したが、貿易戦争の波が米景気悪化につながるとの懸念は根強い。景気敏感株で構成するダウ輸送株平均は直近につけた最高値からの下落率が15%超だ。運輸や小売りなどの業績見通しの下方修正も相次ぐ。景気に対する見方は交錯している。
■WTI NY原油先物(05月限)は、71.48㌦(+2.12㌦ +3.06%)と4営業日、続伸へ。ロシアとウクライナの停戦協議が滞っていることに苛立つトランプ米大統領が、ロシアが停戦に合意しなければ1ヶ月以内に追加制裁を科すと述べたことが手がかり。ロシア産原油を購入する国に対して、米国が25%から50%の追加関税を課す可能性がある。ウクライナ戦争が始まった後のロシア産原油の主な買い手は中国やインド。また、米国とイランが書簡をやりとりした後、トランプ米大統領がイランを空爆すると警告したことも懸念要因。イランの核開発を巡り、米国はイランに対して威圧的に協議開始を迫っているが、イランは応じなかったようだ。時間外取引で5月限は堅調に推移する場面はあったが、1バレル=70ドルの節目が引き続き抵抗となった。ただ、通常取引開始後に買い戻しが強まると、この水準を突破し71.83ドルまで上値を伸ばした。5月限は中心限月として2月21日以来の高値をつけている。
■トランプ氏は、4月2日に発表見込みの相互関税について、全ての国が対象と発言した。31日の取引では、主要な業種は全て下落もしくは横ばいだった。資源株指数は3.29%安と下げが目立った。投資家の不安心理の度合いを示すユーロSTOXX50ボラティリティ指数は22.15と、約3週間ぶりの高い水準だった。
■前週末28日㈮の米国株市場ではトランプ米政権が打ち出す関税政策への警戒感が高まる中、発表されたインフレ指標である2月のPCEデフレーターがコンセンサスを上回る内容だった事から、リスク回避目的の売りがかさみNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに急落した。
先週13日、トランプ米大統領が「相互関税」の導入を指示する覚書に署名した。トランプ政権はこれまでにカナダ、メキシコ、中国への追加関税や鉄鋼・アルミニウムへ製品に対する追加関税の全面適用を打ち出しているが、相互関税についてはその影響がより広範に及ぶ可能性がある。また、14日には自動車関税を導入する考えも示した。とはいえ、市場はこれを比較的冷静に受け止めており、総じて「想定していたよりはずっとマシ」との感が広がっているように思われる。カナダとメキシコについては今後の両国による対応次第で再延期の可能性もあると見られ、鉄鋼・アルミニウム製品については「適用除外」の余地がある。相互関税についても今後、国ごとの調査と個別の交渉という過程を経るなかで、最終的な影響は想定より和らげられると見る向きも少なくない。



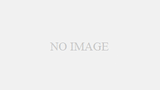

コメント