24年度の後継者難倒産 高水準続く
後継者がいないことで事業継続が困難になったことによる「後継者難倒産」(負債1000万円以上、法的整理)は、2024年度に507件判明した。2013年度に集計を開始して以降で最多の件数となった2023年度(586件)に比べると79件(前年度比-13.5%)少なかったが、2年連続で500件を上回り、過去2番目の高水準となった。業種別では、建設業が127件と全体の25.0%を占めた。建設業は他の業界と比較して労働環境が厳しいといった印象が強く、若年層から就業を敬遠される傾向がある。結果、後継者候補となる人材が不足していることや技術伝承の難しさが、後継者難倒産が多い要因と考えられる。次いで製造業(88件)、サービス業(87件)などが続いた。
2024年度の「後継者難倒産」は、507件発生した。過去最多だった2023年度(586件)から減少に転じたものの、2年連続で500件を上回った。社長の平均年齢は60.7歳(2024年)となり年々上昇が続いており、高齢化が進めば「不測の事態」に見舞われるリスクも高まり、今後も後継者難倒産は高水準で推移する可能性がある。
最も増加率が高かったのは『北陸』(前年241件→323件、34.0%増)で、能登半島地震の影響もあり、大幅に増加した。次いで、『東北』(同443件→569件、28.4%増)が続き、東日本大震災直後の2011年(446件)を超えた。
2024年6月に中小企業庁が取りまとめた、民間企業による中小企業向けM&A成約件数は2022年度時点で4036件、事業承継・引継ぎ支援センターによる件数は同1681件で、いずれも増加傾向にある。それでも後継者難倒産が相次ぐ背景には、深刻な社長の高齢化があげられる。帝国データバンクの調査では2024年時点の社長の平均年齢は60.7歳となり、34年連続で上昇を続けている。後継者難で倒産した企業を倒産時の社長平均年齢を算出すると、2024年時点で69.4歳に及び、過去10年でみても70歳前後で推移している。高齢になれば病気・死亡など「不測の事態」に見舞われるリスクも増加すると考えられ、社長平均年齢が上昇し続けた場合、今後も後継者難倒産は高水準で発生する可能性があり、早いタイミングで後継者の選定・育成を進めることが望まれる。
2024年に過去最多の件数を更新した「粉飾倒産」は、2025年も発生が相次ぐだろう。直近でも、歯科医療用器械・器材などの専門商社「ADI.G」は、11月に取引金融機関に“不適切な会計処理”を報告後、継続支援の同意が得られず、12月16日に民事再生法を申請した。同社は周囲から“良い会社”と見られていただけに、今後も、粉飾発覚を契機とした「優良企業の突発的な経営破綻」には警戒度を高める必要がある。
「後継者難倒産」は、540件(前年564件、4.3%減)判明し、4年ぶりに前年を下回った。2年連続で500件を超え、2023年(564件)に次ぐ過去2番目の件数となった。後継者難倒産のうち、「経営者の病気、死亡」が4割を占め、後継者不在を理由に事業継続をあきらめるケースが発生している。業種別では、『建設業』(124件)が最多で、『製造業』(95件)が続いた。
地域別にみると、2年連続で全地域が前年を上回った。また、『北海道』を除く8地域が過去10年で最多となった。最も件数が多かったのは、『関東』(前年3066件→3442件、12.3%増)で、「東京」(同1549件→1758件)が前年を大幅に上回った。次いで、『近畿』(同2106件→2542件、20.7%増)が続き、11年ぶりに2500件を上回った。『近畿』は全府県で前年を上回っており、「滋賀」(同88件→124件)や「奈良」(同64件→110件)の増加が目立った。都道府県別では、38都道府県が前年を上回り、各地域で増加傾向が見られ、全体の件数を押し上げた。「東京」が1758件で最多、「大阪」が1330件で続いた。
2025年も引き続き、企業倒産は緩やかな増加局面が続く見通しである。企業にとってのコストアップにつながる厳しい外部環境が好転する兆しはなく、1月にも予想される追加利上げや、さらなる賃上げの動きに対応しきれず、中小零細企業の「あきらめ倒産」「あきらめ廃業」が一段と広がるだろう。とくに、「2025年問題」(=団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となることで起こる諸問題)は倒産動向にも影を落とし、経営者の高齢化や人手不足に影響が色濃く出てくることが予想される。2024年は「物価高倒産」が倒産件数を押し上げたが、2025年はこれに加えて「人手不足倒産」や「後継者難倒産」への注目度が高まる1年となりそうだ。
2025年の企業倒産は「新陳代謝」と「優勝劣敗」が加速する1年になる。2024年の倒産件数は3年連続で増加したとはいえ、リーマン・ショックの影響が深刻化した2009年(1万3306件)のような危機的状況にはほど遠い。負債総額を見ても、上場企業や新興不動産デベロッパーの倒産が相次いだ当時と比べ3倍以上の開きがある。2025年の倒産件数が2009年の水準まで急増する事態は想定していないものの、引き続き緩やかな増加局面が続く見通しである。
飲食店の倒産が過去最多となった。2024年の倒産件数は894件で、前年(768件)比で16.4%増加。2020年(780件)を上回って過去最多を更新した。
続いて、「後継者難」倒産の推移を見てみると、2023年4月の43件は2013年以降最多。企業倒産は2023年1月から増加率25%超の高水準で推移。2023年4月は3カ月ぶりに前年同月を上回り、2022年9月の40件以来、7カ月ぶりに40件台となった。
後継者難倒産が相次ぐ背景には、深刻な社長の高齢化があげられる。帝国データバンクの調査では2024年時点の社長の平均年齢は60.7歳で、34年連続で上昇。後継者難で倒産した企業の倒産時の社長平均年齢を算出すると、2024年時点で69.4歳。過去10年でみても70歳前後で推移している。高齢になれば病気・死亡など「不測の事態」に見舞われるリスクも増加すると考えられ、社長平均年齢が上昇し続けた場合、今後も後継者難倒産は高水準で発生する可能性があり、早いタイミングで後継者の選定・育成を進めることが望まれる。
なかでも、人手不足の影響が2024年以上に広がるとともに、経営体力が限界に達した末の「賃上げ難型」倒産の多発も小規模事業者を中心に懸念される。利益で借入金の利息が賄えず、政府や金融機関の支援で延命を続けてきた推計20万社超の「ゾンビ企業」の淘汰もさらに進むだろう。金融機関の選別からふるい落とされる企業も一定数出てくるにちがいない。多くの企業が人手不足解消に取り組むなかで、法的整理や私的整理の手法を用いて事業や雇用を別会社に承継したうえで、長年の債務を処理するスキームもさらに活発化していきそうだ。
2024年6月に中小企業庁が取りまとめた、民間企業による中小企業向けM&A成約件数は2022年度時点で4036件、事業承継・引継ぎ支援センターによる件数は同1681件で、いずれも増加傾向にある 。それでも後継者難倒産が相次ぐ背景には、深刻な社長の高齢化があげられる。帝国データバンクの調査では2024年時点の社長の平均年齢は60.7歳となり、34年連続で上昇を続けている。後継者難で倒産した企業を倒産時の社長平均年齢を算出すると、2024年時点で69.4歳に及び、過去10年でみても70歳前後で推移している。高齢になれば病気・死亡など「不測の事態」に見舞われるリスクも増加すると考えられ、社長平均年齢が上昇し続けた場合、今後も後継者難倒産は高水準で発生する可能性があり、早いタイミングで後継者の選定・育成を進めることが望まれる。
2024年の企業倒産は9901件発生し、前年(8497件)を16.5%上回り、3年連続の増加となった。懸念された年間1万件には到達しなかったものの、2013年(1万332件)に次ぐ11年ぶりの高水準となった。月別推移を見ても、2024年12月は848件(前年同月比5.2%増)を数え、2022年5月から32カ月連続で前年同月を上回り、過去最長の連続増加記録を更新した。物価高、人手不足、後継者難に、新型コロナ支援策の終了やゼロゼロ融資の返済負担も加わり、企業倒産は負債5000万円未満の小規模事業者を中心に緩やかな増加が続いた。
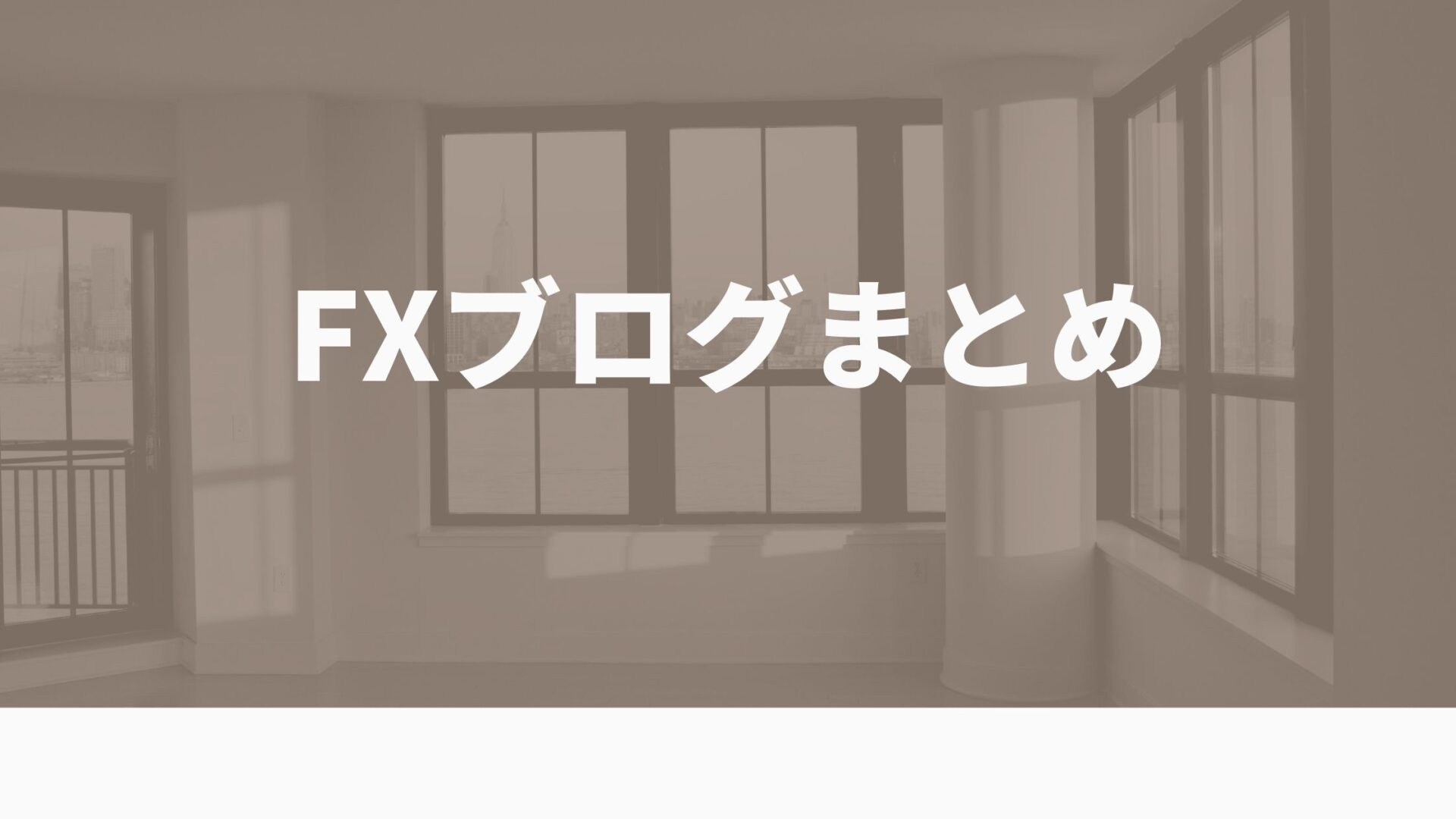

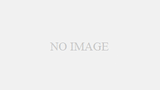
コメント