ホンダに激震 副社長辞任の影響
そのため、彼の辞任はホンダにとっても大きな打撃となり、業界全体にも波紋を呼んでいます。
1986年に入社した青山氏は二輪事業本部長など二輪事業を中心にキャリアを歩んできた。近年は四輪事業の本丸である北米統括会社やアメリカ子会社のトップ、四輪事業本部長などを歴任。2023年4月には副社長に就任し、三部敏宏社長に次ぐナンバー2としてホンダの電動化や提携戦略の策定に携わるなど経営の中枢を担ってきた。
まずは、昨年から始まったホンダとの経営統合交渉が破談に終わった真相、そして内田社長の退任が決まった内幕を探りたい。
共同持ち株会社方式の経営統合なら、事業会社の日産は経営戦略や人事について一定の裁量を持てるが、完全子会社化となればホンダの一部門になることを意味し、戦略立案や人事はすべてホンダの管轄となる。たとえるなら、トヨタ自動車とダイハツ工業の関係と同じだ。ダイハツはトヨタの小型車戦略の中に位置づけられ、社長をはじめ、主要役員はトヨタから派遣されている。
結果から振り返ると、その破談の大きな要因はホンダの強気な交渉姿勢にあったのかもしれない。
「株式交換によって日産をホンダの完全子会社としたい」
ホンダは「被害者のプライバシーを守るため詳細は差し控える」として事案の内容については明らかにしていない。青山氏は事実関係について認めており、「反省している」と述べているという。 ■電動化や提携戦略を担ってきたナンバー2 「この大変な時に、まさかこのようなことが起こるとは……」とホンダの中堅社員は言葉を詰まらせる。 1986年に入社した青山氏は二輪事業本部長など二輪事業を中心にキャリアを歩んできた。近年は四輪事業の本丸である北米統括会社やアメリカ子会社のトップ、四輪事業本部長などを歴任。2023年4月には副社長に就任し、三部敏宏社長に次ぐナンバー2としてホンダの電動化や提携戦略の策定に携わるなど経営の中枢を担ってきた。
「それでも日産は、社名を受け入れてでもホンダと組むべきだった」
だが、ホンダに惻隠の情はなかった。業績悪化に喘ぐ日産に、いきなり剛速球を投げ込んだのである。
「代表執行役の異動(辞任)に関するお知らせ」と題するリリースの冒頭では「当社は、取締役 代表執行役副社長 青山 真二から辞任届が提出され、これを受理しました」と説明。「異動(辞任)の理由」には、青山氏が業務時間外における懇親会の場で不適切行為を行ったとの訴えを受けていることが発覚したと記されていた。
ホンダのもう1人の副社長である貝原典也氏が人事などの管理部門や品質、購買を中心に所管していたのに対し、青山氏は営業や地域戦略、財務など経営でも肝となる領域を所管。日産自動車との経営統合に関わる協議にも中心メンバーとして関わっていた。 日産との経営統合は一旦は破談となったものの、EV(電気自動車)やソフトウェアでの協業は継続して議論している。何よりホンダ単独で成長戦略を描くのが難しいという現実は変わっていない。
ホンダの経営陣として、会社全体の信頼回復に向けてできる限りの対応をするという強い意志を感じさせます。
特に、最近ではホンダの電気自動車(EV)戦略において中心的な役割を果たし、業界でもその手腕を高く評価されていました。
青山真二副社長の辞任は、ホンダの経営にも大きな影響を与えることが予想されます。
ホンダは「被害者のプライバシーを守るため詳細は差し控える」として事案の内容については明らかにしていない。青山氏は事実関係について認めており、「反省している」と述べているという。


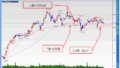
コメント