政府は ライドシェアの全面解禁に向けた論点整理を進めています
さらに、大阪府は2025年の大阪・関西万博に合わせて、府内全域で24時間運行が可能なライドシェアの実現を目指しており、政府に対して制度緩和を求めています。
筆者はこれまで、全国各地で地域交通に関する取材を定常的に行ってきたことに加えて、中央官庁や地方自治体において次世代交通のあり方についての議論に参加してきた。現時点で国が進めているライドシェアにかかわる議論の進め方は、明らかに拙速であると思う。さらに言えば、違和感の背景には「議論の順番が逆」という点を強く感じている。
MOOVマガジンでは、今後もライドシェアの動向を追い続け、読者の皆様に最新の情報をお届けします。東京都内でレンタカーやカーシェアの利用を検討している方々にとって、有益な情報を提供できるよう努めてまいりますので、ぜひ今後もご注目ください。
なお、ライドシェアとは、一般ドライバー、または普通自動車第二種運転免許(二種免許)を所持するタクシードライバーなどが乗用車を使って旅客行為を行うことを指す。
現在、119の自治体が加盟しており、各地のニーズに応じたライドシェアの仕組みづくりを進めています。これにより、地域ごとの課題に対応した柔軟な運行が可能となることが期待されています。
ライドシェア解禁に伴う課題として、まず乗客の安全確保が挙げられます。一般のドライバーが運行するため、タクシー業界と同様の安全基準をどのように適用するかが問題となっています。
ライドシェアの成功には、地域ごとのニーズに応じた仕組みづくりが不可欠です。各地域の特性や課題に応じた運行方法を導入することで、住民の移動手段を確保することができます。
また、ドライバーの確保も大きな課題です。特に、タクシーが不足する地域や時間帯において、どれだけのドライバーが確保できるかが重要です。さらに、ライドシェアの収益性も問題となっており、黒字化のハードルが高いとの指摘もあります。
政府は、ライドシェアの全面解禁に向けた論点整理を進めています。これには、乗客の安全確保やドライバーの確保、収益性の確保など、多くの課題が含まれています。
ライドシェアの解禁は、住民の移動手段を確保するための重要な一歩です。しかし、まだ多くの課題が残されており、これらを解決するためには、政府、自治体、事業者が一丸となって取り組む必要があります。
自家用車を利用して乗客を運ぶ「日本版ライドシェア」が導入されて8日で1年になる。「すきま時間の有効活用」「効率的に働ける」……。運行管理を担うタクシー会社のサイトには、そんなうたい文句が並び、実際に働く人はやりがいも感じるが、地方の「足」不足も課題として残る。
「守るべきは規制ではない。全ての地域で、必要な時に円滑に、移動が可能になる『移動の自由の確保』が必要だ」。河野太郎デジタル相は、ライドシェアの規制のあり方を議論する政府の作業部会などで度々こう発言。LINEヤフーの川辺健太郎会長ら一部委員も「移動の足の確保という社会課題の解決に対して(現行のライドシェアは)十分な制度になっていない」などと、さらなる規制緩和を求めてきた。
国が4月からタクシー事業者に限定して導入した「自家用車活用事業」は、事実上の「ライドシェア一部解禁」となった。それを受けて今、いわゆる「ライドシェア新法」制定に伴う「ライドシェア全面解禁」に向けた議論が急加速している。
「交通DXに向けて、河野(デジタル)大臣と齋藤(国土交通)大臣はデータを検証し、地域の移動の足不足の解消の状況を確認して、制度改善を不断に行ってください。あわせて、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業にかかわる法制度について、6月に向けた議論の論点整理を行い、5月中に規制改革推進会議に報告をしてください」
ライドシェアとは、移動の手段である車とそれを運転するドライバーをシェアリングする、新しい移動の形です。スマートフォンアプリなどで配車を依頼し、タクシーのように利用する形式が一般的なライドシェアの仕組みとなっています。
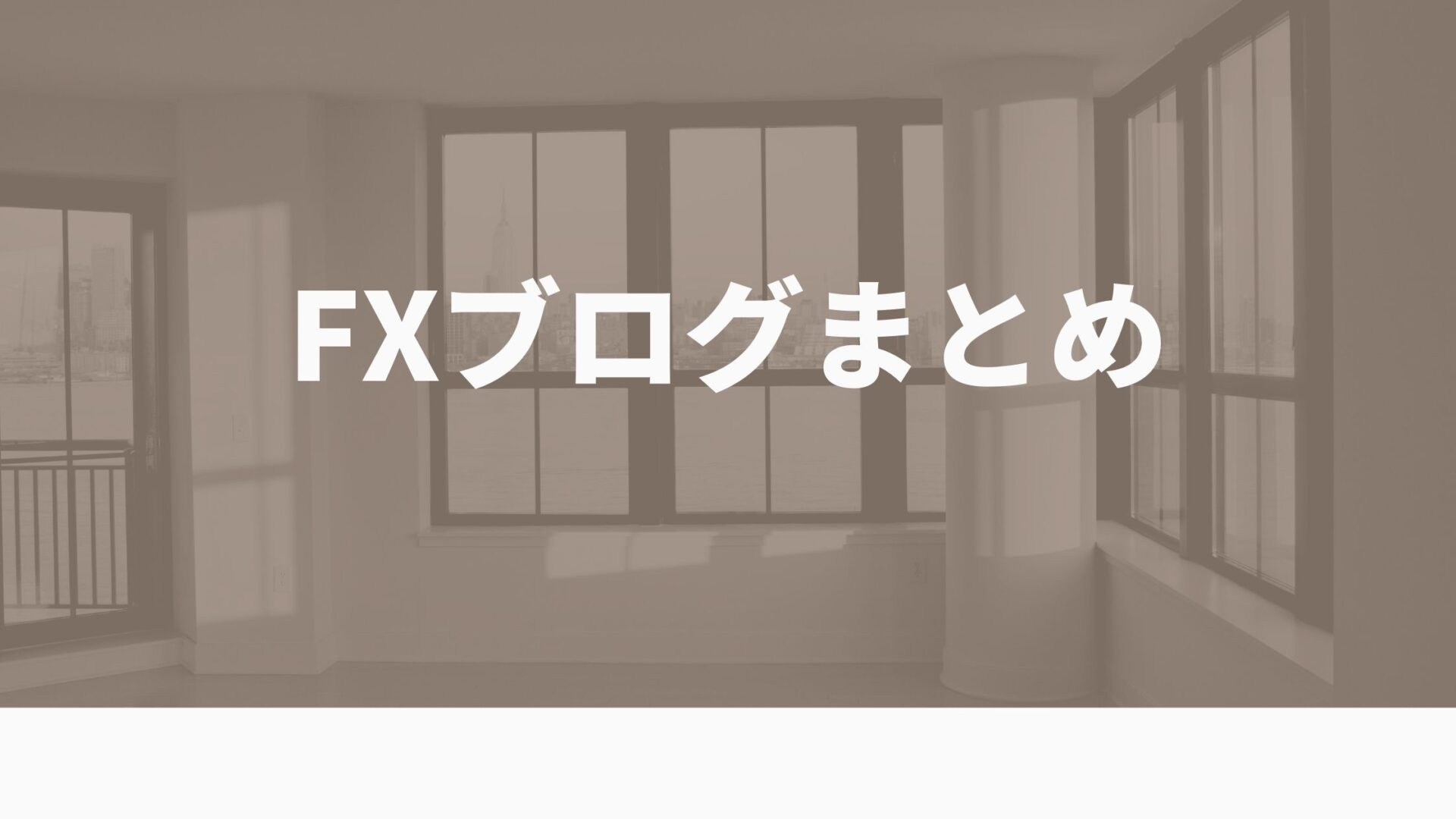

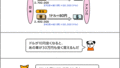
コメント