
中東に位置するトルコの通貨リラを取り巻く環境を分析し、トルコリラの今後の値動きを予想した。
執筆:株式会社外為どっとコム総合研究所 調査部長 神田卓也 X(Twitter)
野党党首、政権交代に向けて早期選挙を求める
トルコ最大野党・共和人民党(CHP)のオゼル党首が日本経済新聞の取材に応じている。次期大統領の有力候補で同党に所属するイマモール・イスタンブール市長が汚職などの嫌疑で逮捕されたことについて「証拠がない」と強調した上で「未来の大統領に対するクーデターだ」と語った。2028年までに実施される予定の次期大統領選については「我々は早期選挙を望んでいる」とし、選挙日程を年内に決め、遅くとも2026年までに実施するよう求めた。オゼル氏はまた、CHPが大統領を輩出した場合、エルドアン現大統領が拡大した大統領権限を弱める考えを示した。エルドアン大統領の強権的な政治と経済政策の失敗に対する国民の不満が高まる中、早期に選挙を行なえば政権交代が見込めるとの思惑があるようだ。
政権交代なら市場はポジティブに反応か ただし早期選挙の可能性は低い
市場では(特に為替市場においては)、エルドアン大統領の失脚はポジティブ材料と捉えられるだろう。2023年5月の大統領選でエルドアン氏の苦戦が伝えられるとリラが買われる場面があったが、最終的にエルドアン氏が勝利したため買いは失速した。2024年3月の統一地方選挙でエルドアン氏率いる公正発展党(AKP)が敗北した際も一時リラが買われた。もし今回、大統領選挙が前倒しになるようなら、その時点からリラが強含み始める可能性もあるだろう。もっとも、日本経済新聞はオゼルCHP党首への取材記事で、いまのところ与党AKPが早期の選挙実施に応じる可能性は低いとの見方を示している。また、CHPが選挙で勝利するには対エルドアン氏で結束を維持し、党として有力な対抗馬を擁立できるかがカギとなると結んでいる。
外務省 トルコ基礎データ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/turkey/data.html
トルコリラ/円(TRY/JPY) 日足チャート

ドル/トルコリラ(USD/TRY) 日足チャート

ユーロ/トルコリラ(EUR/TRY) 日足チャート

【トルコリラに関する外為どっとコムのキャンペーン】
【トルコリラの最新チャート】
「為替チャート|トルコリラ/円(TRYJPY)|60分足」はこちら
「為替チャート|米ドル/トルコリラ(USDTRY)|60分足」はこちら
「為替チャート|ユーロ/トルコリラ(EURTRY)|60分足」はこちら
お知らせ:FX初心者向けに12時からライブ解説を配信
外為どっとコム総合研究所の調査部に所属する外国為替市場の研究員が、FX初心者向けに平日毎日12時ごろからライブ配信を行っています。前日の振り返り、今日の相場ポイントなどをわかりやすく解説しています。YouTubeの「外為どっとコム公式FX初心者ch」でご覧いただけます。

株式会社外為どっとコム総合研究所 取締役 調査部長 上席研究員
神田 卓也(かんだ・たくや)
1991年9月、4年半の証券会社勤務を経て株式会社メイタン・トラディションに入社。 為替(ドル/円スポットデスク)を皮切りに、資金(デポジット)、金利デリバティブ等、各種金融商品の国際取引仲介業務を担当。 その後、2009年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画し、為替相場・市場の調査に携わる。2011年12月より現職。 現在、個人FX投資家に向けた為替情報の配信を主業務とする傍ら、相場動向などについて、経済番組専門放送局の日経CNBC「朝エクスプレス」や、ストックボイスTV「東京マーケットワイド」、ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」などレギュラー出演。マスメディアからの取材多数。WEB・新聞・雑誌等にコメントを発信。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
トルコリラの焦点 最大野党党首 未来の大統領へのクーデター
大統領制移行に伴う省庁再編は、エルドアンやトルコのイスラム復興勢力の多くにとって積年の課題だった、軍部に対する文民統制の完成という点でも、大きな意味をもった。まず、大統領令第4号により国防省の管轄下に軍が置かれることが明記された(第799条i項)。この大統領令以前には、トルコ国軍は多くの国に一般的な国防省の管轄下ではなく、議院内閣制における最高政治責任者としての首相に対して、内閣が策定した軍事政策の実施に関わる責任を負っていた。他方で2013年夏に「国軍内規に関する法」(Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu)が改正されるまでは、対外脅威に対する国土防衛と並んで、「憲法に規定されたトルコ共和国体制を守ること」が国軍の主要任務であった。これはイスラム復興運動やクルド民族主義運動が従来の政治体制の変更、つまり、世俗主義を放棄してイスラム的政策を容認したり、トルコ民族主義的中央集権体制を緩和して国民の多様なアイデンティティに応じた多元主義的・地方分権的統治システムを取り入れる、といった政治要求の高まりを阻止するために、内政に干渉し、場合によってはクーデタを実行して軍事政権を敷き、そうした「国内的脅威」を除去することも、軍の主要任務であることを意味する。実際、内政への軍の介入は様々な形で実施され、トルコの民主主義の成熟という点で、長く主要な課題とされてきた。
トルコ共和国は1923年10月に樹立が宣言されて以降、1924年3月にカリフ制を廃止し、大統領を国家元首とし、西洋世界を見習って国民主権や世俗主義を柱とする国家建設を進めた。世俗主義は、国家の正当性原理に留まらず、国民アイデンティティの脱宗教化や、教育や法体系の世俗化(近代西洋的制度の導入)にまで及び、1937年には世俗主義条項が憲法に挿入された。加えて、オスマン帝国が民族分離独立運動によって瓦解した経緯から、建国エリートはトルコ民族文化への同化による国民建設こそが国家の存立基盤だと考えた。その結果、非トルコ系民族文化の主張や、国境を越える労働者の連帯活動を唱える共産主義運動は新生国家への主要脅威とみなされ、抑圧された。共和制樹立から1945年までは、共和人民党の一党制が敷かれ、体制基盤の確立に注力された。
民主社会党は欧州司法裁判所に提訴したが、民主社会党の前身である人民の民主主義党の裁判も結審しておらず、判決はかなり先のことになると見込まれる。ちなみに、人民の民主主義党以前に閉鎖された3党についてはいずれもトルコが敗訴している。
HDPは、トルコ全土の民主化・文化多元主義化を主張するものの、支持層の観点からいえば、圧倒的にクルド政党である。しかし、KONDA社は選挙直前の調査を根拠に、トルコのクルド人の大多数を占めるクルマンジ語系(本人の母語がトルコ語に同化していても自認としてここに含まれる者もいる。全人口14%程度と推定)の53%、クルド少数派のザザ語系(全人口の2%程度と推定)の23%はHDPを支持したが、クルマンジ語系の24%、ザザ語系の31%はAKPを支持したと推定する。ちなみに、シリア国境地域に多くが住むアラブ系住民のうちHDP支持は6%にすぎず、AKPが37%、CHPが29%を支持していた(前掲文献pp.40, 103)。
エルドアンは、自らは首相から大統領へ鞍替えし、大統領職もシステム変更によって2選禁止の適用をかわして権力ポストを維持しつづけている。その一方で、党が継続的・漸進的に人員刷新や世代交代を進める必要を説いて、国会議員の4選を党規で禁止し、現役議員の1/2から2/3を選挙の度に候補者リストから外し、被選挙権年齢を引き下げてきた(最新状況は18歳)。しかしこれは同時に、党組織や国会議員候補選定という人事をエルドアンが掌握し続けながら、ライバル候補の権力ポジションでの滞留を防ぐという効果(おそらく意図)もある。これは党や国政、地方行政にまつわる利権の受益者が全体として増加することを意味しており、そのおこぼれにあずかろうとする潜在的待機者の支持を取り付け、自分や親族がそこから弾かれないように批判を自己規制する人々を繋ぎ止めるのに役立ってきた。しかし、かつての「ムスリム国民の視座」運動の精神を根っこのところで共有しない中道右派やトルコ民族主義の人々、公正と発展党政権が利権政治の旨みを享受する時代に育った若い世代が、党の主流となることを懸念する声も、その時代を経験してきた世代からは漏れ聞こえてくる。
クルチダルオールの行進に芸能関係者や政治評論家、ジャーナリスト、政治活動家らが参加した。党首として参加した人はいなかったが、IP、SP、HDPは党幹部が賛同するメッセージを発したり、著名な党活動家たちが参加し、政府の権威主義化への批判に対する連帯姿勢を示した。ここに名を連ねた政党は、イデオロギー的にいえば、トルコの主要イデオロギー勢力のすべてを包摂している。つまり、左派勢力に加え、与党連合とイデオロギー的に競合する右派勢力を擁しており、与党連合以上のイデオロギー的広がりを有していた。CHPは世俗主義者や世俗派リベラルの都市中間層に、IPは中道右派から極右トルコ民族主義に、SPはイスラム系の保守系と革新系の両方の層を、HDPは左右のクルド系にアピールし得た。そのため、これらの政党が民主的原理で協力しつつ勢力を拡大することは、トルコが権威主義に急速に傾く中で、それへのアンチテーゼを体現するという観点で意義深いことだった。
また、種々のアンケート結果に直接的に出てくることはないが、政権支持層も含めて、シリア難民がトルコ国民の本来享受すべき社会保障予算を圧迫しているとか、彼らが非正規の低賃金で働くことが国民の職を奪い、彼らの流入した地域の住宅賃料を押し上げているとして、政府のシリア難民受け入れ政策に批判的な声も蔓延していた。筆者が選挙期間中のアンカラで直接目にした例であるが、物乞いのために歩道上に座り込んでいる老婆の前を通り過ぎたとき、ちょうど後ろから追い越していった男性が、「トルコ国民がこうして困難な状況に置かれているのに、シリア人は気楽に暮らしている」と、携帯電話で話していた。こうした不満は時として社会不安の暴力的表出として現れている。たとえば、路上でのちょっとした諍いや、シリア難民が強姦事件を起こしたなどのデマをきっかけとして、住宅街でシリア難民へのリンチ事件が散発してきた。そうした状況がどう改善されるのか、選挙戦で明確なメッセージが発せられることはなかった。さらにいえば、トルコ民族主義的世論からすれば、トルコ軍兵士がシリア内戦で犠牲を払っているのに、シリア難民はなぜトルコで保護されているのか、という不満もある。これはシリア側からすれば、越境侵犯しているトルコ軍が撤退すればいい、ということになりそうだが、トルコ民族主義的世論にしてみれば、シリアとトルコのPKK系クルド系勢力が、欧米諸国と連携して自治や将来的独立を画策していると考えられるため、シリアに軍事介入して現地のクルド系武装勢力を一掃し、シリアでの自治獲得に勢いを得てトルコを含む周辺各国のクルド民族主義がさらに高揚することを何としても防がねばならないのである。つまり、シリアのPKK系クルド勢力の勢力拡大は、トルコの国家安全保障を揺るがしかねない最大級の脅威と認識されているのである。それゆえに、越境作戦による殉職者が多く出ているにもかかわらず、そしてそれ自体は政府にとっては支持低下のリスクを伴うにもかかわらず、シリア内戦後の秩序がトルコのクルド問題との関連で受け入れられるものだと確信できない限りは、もはやそう簡単に撤退できない問題となっている。
国会第3党として新しく議席を確保したのは、極右トルコ民族主義の民族主義行動党(MHP)である。同党の勢力バロメーターは左派クルド民族主義ゲリラのクルディスタン労働者党(PKK)の活発度である。国軍とPKKの交戦が激しさを増していた1990年代を通じて10%に迫る勢いを維持していたが、1999年の選挙直前にPKK党首が逮捕されたことを受けて国民のトルコ民族主義感情が高まり、MHPは得票を一気に伸ばした。その後、2003年のイラク戦争後にイラク北部のクルド自治区(クルディスタン地域政府)の安定と自律性が強まると、そこを拠点としたPKKのトルコ国軍への攻撃やトルコ主要都市での爆弾爆破事件が2004年頃から活発化し、トルコ国内での反クルド的トルコ民族主義・国家主義の世論が再び高揚してきた。こうした世論を背景として、MHPは再び票を伸ばした。
2005年11月の民主社会党設立の動きは、旧民主主義党幹部で投獄されていたレイラ・ザーナ(Leyla Zana)らの釈放とともに始まった。ザーナらは、1991年に社会民主人民主義党との選挙協力で議員に選出されたものの、国会での宣誓をクルド語で行ったために党籍を剥奪され、その後、民主主義党を設立したものの、1994年以来、PKKメンバーだとして党が非合法化されたのと同時に投獄されていた。そこで民主社会党の設立に際しては、ザーナらは公式の党幹部にはならず、クルド民族主義運動の外部から著名な左派トルコ人政治家を迎え入れることにより、両民族が協力し民主的で自由な政治社会の実現を目指す政党づくりをアピールしようとした。しかし、その試みは結局、実現せず、PKKシンパの政党というイメージを払拭できなかった。
こうした状況と政党の得票との関連でいえば、前述の、HDP系首長が逮捕され、代わりに政府が首長代理を任命した自治体では、KONDA社調査(pp.78-82)によれば、AKPやMHPの支持率が若干ながら上昇したところもあり、そうした地域ではHDPは支持を減らしている。各選挙区の有権者プロフィールをある程度知っている人によっては、これまで棄権してきた地元のトルコ系マイノリティが今回は投票に行ったのだ、とか、地域の治安対策のために軍や警察関係者が多数配置されたために、彼らの票が「共和連合」の支持率上昇をもたらしたなどの指摘がある。KONDA社(p.32)は前回選挙でHDPに投票した人の5%は棄権したと推定する。このあたりについてのより詳細は、投票所別の選挙結果と世論調査やフィールド調査を組み合わせた分析を待つ必要があるだろう。
近年の選挙では多様な候補の擁立が多くの政党によって宣伝材料として用いられるようになってきたが、今回はキリスト教系マイノリティが複数政党で擁立され、最終的にBDPの後押しでマルディン県からトルコ政治史上初のシリア・カトリック教徒の議員が誕生した。
CHPは今回初めて党員による立候補者選定選挙を行った。55%の投票率により、世俗主義的トルコ民族主義者(Ulusalcı)がかなり駆逐され、宗教マイノリティのアレヴィが多くの支持を集めたという 。CHPはこれを基礎に党幹部による任命候補を加えて候補者リストを作成し、支持層から好評を得た。マイノリティからの支持拡大を目指すHDPとの間でアレヴィ票をめぐる奪い合いが予想されたが、後述のように、アレヴィの多数はCHPを支持したとみられている。
ただし、現実には、下からの決定の積み上げによる民主的組織とはいかず、トップダウンの権威主義的組織構造であることが、党内外からしばしば批判されてもきた。しかも、党幹部や議員候補者リスト選定もPKK中枢部を中心に行われてきたといわれる。その軋みは、運動のリーダーであるオジャランが逮捕されて以降、カリスマとしてのオジャラン、武装活動によって血を実際に流してきたという点で説得力を持つPKKの幹部たち、合法政党幹部として弾圧に立ち向かいながら言論活動を通じて党勢拡大の立役者となった若きカリスマのデミルタシュ、という3者のバランスのなかで、合法政党リーダーとしてトルコ世論とクルド世論の両方に対する説明責任を負わされるデミルタシュに重くのしかかってきた。
他方で、被選挙権の面では、少なくともHDPから欧州移民が2名、国会入りした。一人はドイツを中心にアレヴィ系移民の組織化でリーダーシップをとってきたトゥルグト・オケル(Turgut Öker)、もう一人はヤジード派移民家庭に生まれ、ドイツ語とクルド語、英語を話すがトルコ語をほとんど話せないフェラクナス・ウジャ(Felaknas Uca)前欧州議会議員である。ウジャはトルコ語での宣誓のために事前に練習を積んだとされ、宣誓の模様は注目の的となった。
1987年に選挙プロセスが大幅に民主化されたものの、民主化課題は山積していた。しかし、トルコが1987年にEU正式加盟を申請したことが契機となり、今日に至るまでEUの民主化基準を物差しとして民主化改革が進められた。
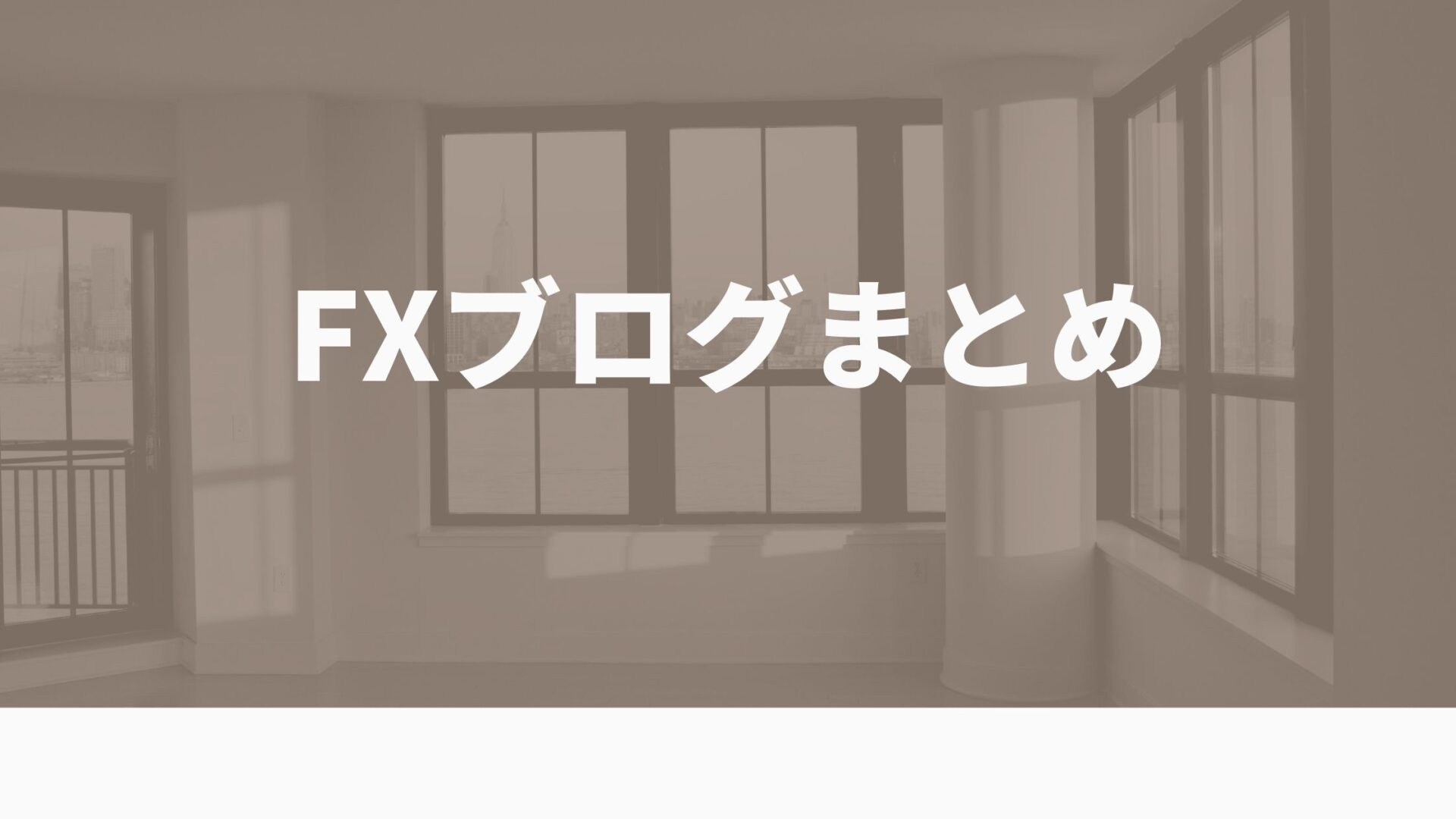

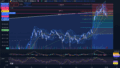

コメント