P&Fでは~
ドル円が上に3枠転換。
豪ドル円が上に3枠転換。
ポンド円が上に3枠転換。
豪ドルドルが上に3枠転換。
<日足P&Fの状況:(04月07日)~(04月11日)>に追記しました。
昨日は、<ガラリ一変はいつあっても状態>というタイトルにしましたが、まさにガラリ一変
となり相場は148円台まで一気に上昇。
現在は、なぜか1487円台前半まで押し戻されてます。
やはり、ガラリ一変が怖くて戻ったら利食いということになってそうな気がします。
トランプ大統領は、報復措置をとってない国の上乗せ関税を90日間の停止ということで
一気に反転し、特に株は大きく戻しています。
しかし、中国に対してはさらに上乗せ関税をするということでの貿易戦争状態です。
また、中国が対抗措置でレアアースなどの輸出を停止したりとなれば株がまた大きく下がり
リスク回避の動きになるのではと考えます。
まだまだ安心できないどう動くか不透明な状態が続くと思います。
やるなら短期でやっていくしかなさそうな状況は続きそうですね。
何度も書きますが資金管理はしっかりと。
本日は、米国のCPIがあります。
ここら辺は動くかもしれませんが、やはりトランプ次第でどうにでも動く相場です。
(個人的な見解ですので、投資は自己責任でお願いします。)
04月10日 ガラリ一変再び短期で勝負しかない
先週フランス、オランダが相次いでEU憲法の批准を否決した、というニュースがありましたね。EU憲法は2年間の討議を経て、EU首脳会議が2004年6月に採択、10月に調印という段階まできています。その後、各国にて議会または国民投票による批准手続きに入り、これまでドイツ・スペインなどが批准を終えています。ただし、EU憲法の発効には25カ国全ての批准が必要なため、仏・蘭両国の否決は大きな打撃となったわけですね。
EU憲法は448条に及ぶ長大な憲法で、2004年に25カ国に拡大したEUの目的・市民の権利・共通外交安全保障政策等に関する規定があります。欧州安全保障政策(ESDP)に関する条文を見てみると、「相互防衛条項」(I-40-7)を定めて、EU加盟国間の集団防衛を明確化し、また「欧州装備・調査・軍事能力庁」を設置し(I-40-7)、欧州防衛能力を強化してペータースベルク任務(その1参照)を拡大し、さらに欧州域内における国防産業・技術基盤を強化することが謳われています。欧州理事会の議長が対外的には「EU大統領」として欧州委員会の委員長が「EU外相」としての位置づけになり、EUが地域の代表として大きな政治主体になるための、基盤づくりという意味を持っています。
さて、「07大綱」から10年経った2004年12月に「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」(新大綱)が閣議決定されました。この10年間にも、安全保障環境は刻一刻と変動を続けました。1996年には台湾海峡における中国人民解放軍の大規模ミサイル演習があり、1998年には北朝鮮からテポドン・ミサイルの試射がありました。そして、2001年には米国における同時多発テロ事件が起こり、その後米国は「対テロ戦争」という新しい軸のもとで、安全保障政策を改編していくことになります。安全保障環境の大きな変化に、日本の防衛力整備がどう対応していくべきか、その答えを出したものが新大綱であるといえるでしょう。
最後は「機構改革」です。ここでは2002年11月のプラハ首脳会合、そして2004年6月のイスタンブール首脳会合に注目してみましょう。プラハ首脳会合では、①対テロ防衛に関するNATO軍事概念の導入、②「プラハ軍事能力コミットメント」(PCC)の採択、③作戦連合軍への統合、④NATO即応部隊(NRF)の創設が決定されます。9.11事件と新しい脅威への対応に向けて、NATOもその自己変革を進めてきた様子を見ることができます。
数名がいけにえになりましたが、あ~ら不思議、合わせる色で、印象がガラリと変わります。地味な色選んじゃうと、性格まで暗くなっちゃうのね。
さてGPRに伴い、アジアにおける米軍の再編はどうなるのでしょうか?ブッシュ大統領は2004年8月16日に「海外駐留米軍再編の基本方針」に関する政策演説を行い、今後10年間にわたる前方展開兵力の再編に関する方向性を示唆しました。その基本的考え方としては、アジアと欧州に駐留する米軍約20万人の3分の1に当たる、6~7万人を今後10年で撤退させることが謳われています。このうちアジアでは、既に削減を公表している在韓米陸軍12500人を含め、2万人規模の再編が検討されるとのこと。
米国では9.11事件以降、国民のテロリズムに関する関心が著しく高まり、米政府もテロリズムに関する情報を米国市民に浸透させる努力を行っています。例えば、2004年に作成された国土安全保障省におけるホームページ「READY.GOV」はT.V.コマーシャルを通して広く米国市民にテロリズムに関する知識を浸透させ、テロ時の対応方法を詳細に記しています。本土安全保障省のHPでは、現在の米国のテロ脅威について5段階で表示し、米国民にテロの脅威の度合いについてリアルタイムで情報を提供しています。また、米国国務省では、テロリズムに関する年次報告を行っており、世界中のテロ活動を統計化・分析したPatterns of Global Terrorismをはじめ、テロ組織の名称やテロ活動のクロノロジー等を記したFact Sheetを刊行しています。その中でも、米国ホワイトハウスが2003年2月に打ち出した「テロリズムに対抗するための国家戦略」(National Strategy for Combating Terrorism) は、現在の米国の対テロリズム戦略を知る上で必読の資料です。
2004年10月には首相官邸での諮問機関である「安全保障と防衛力に関する懇談会」(座長:荒木浩東京電力会長)が、最終報告書を提出し、①伝統的脅威と非伝統的脅威の「あらゆる組み合わせ」が存在する国際情勢、②「多機能弾力的防衛力」の導入、③国際平和協力任務の主任務への格上げ、④武器輸出三原則の柔軟運用、などを提案しています。この資料は、将来の日本の防衛力の方向性を示す文書ですので、ぜひ熟読してみてください。
さらに「米国の介入」にも雲行きが怪しくなってきました。ブッシュ政権は2000年の選挙キャンペーンでは「戦略的あいまい性は存在しない」(ライス国務長官)という強い表現で、台湾を防衛する意思を示していました。しかし、2003年から04年にかけてずいぶんその表現を変化させています。中国首脳には「一つの中国」を再三確認するとともに、台湾に対して「一方的な独立は認めない」という立場を強化するようになったからです。この背景には、中国の急速な台頭と米中の経済的な相互依存関係が増大したことがある、といわれています。その中で、やみくもに台湾が政治ゲームにうってでることは、地域の安全をおとしめ、中国の成長市場をも失わせることにつながるからです。
〔さらなる学習のために(英語)〕 [1] Kurt M. Campbell, "The End of Alliances? Not So Fast" Washington Quarterly (Spring 2004) [2] Bruno Tertrais, "The Changing Nature of Military Alliances" Washington Quarterly (Spring 2004) [3] Paul Dibb, "The Future of International Coalitions: How Useful? How Manageable?" Washington Quarterly (Spring 2002).
次に「加盟国の拡大」です。冷戦後のNATOは域外への対処とともに、NATO自体の拡大によって、欧州の安全保障を安定化に導こうとしました。1999年3月の第1次拡大としてポーランド・チェコ・ハンガリーの3カ国が加盟し、さらに2004年6月の第2次拡大ではエストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニアの7カ国が加盟しました。
それにより、ブッシュ政権の軍事費は増大を続け、2004年度の会計年度では4013億ドル(約45兆円)という未曾有の巨額予算になっています。世界の軍事支出総額は8000億ドルですから、米国は一国で世界の軍事支出の半分を占めていることになります。新規の研究開発(R&D)への投資額も重視され、世界最高の軍事技術を誇る米国の軍事産業には、常に新しいテクノロジーの発掘が求められています。こうしたブッシュ政権の姿勢は、旧約聖書の「バベルの塔」に近い発想なのかもしれません。ただ、これが9.11後の安全保障環境に対する、米国の覚悟だということでしょう。
オーストラリアについては、2004年7月にオーストラリア北部にある豪州軍の既存の基地に米軍の訓練施設を設置することで合意に達しています。クイーンズランド州ショールウオーター湾訓練施設(SWBTA)をはじめ、北部準州にあるデラミラー訓練空域、ブラッドショー演習場の計3カ所の共同使用を念頭に、3年後をめどに施設整備を図る考えとされています。同施設については、すでにシンガポール軍も利用しており、沖縄駐留の米海兵隊の訓練にも利用されるとともに、多国間の共同訓練にも利用する方向みたいですね。
【英検を利用した奨学金の活用法】 大学は専門知識を学ぶ場です。 しかし、学費や生活費のため、アルバイトに追われる学生も少なくありません。 特に3、4年生では研修や卒業研究が始まり、アルバイトとの両立は難しくなります。 そのため、大学入学時点で給付型奨学金を確保し、勉学に集中できる環境を整えることが理想的です。■英検で広がる可能性 ここで注目したいのが英検です。英検は入試だけでなく、奨学金や学費免除にもつながります。 例)愛知学院大学の例 愛知学院大学の文学部では、「グローバル特待生制度」を導入しています。 この制度を利用すると、次のようなメリットがあります。1. 初年度学費の大幅免除初年度学納金1,349,000円が特待生になると59,000円に。1,290,000円が免除されます。2. 資格基準を満たせば選考対象英検準1級(CSEスコア2,304点以上)などの基準を満たせば、対象になります。3. 英語力を活かした単位認定グローバル英語学科では入学後に、単位の一部が認定されます。■英検取得の価値 英検は多くの大学で、入試優遇や奨学金の条件とされています。 1. 入試得点の加算英検準1級や2級取得者は、入試での得点加算があります。2. 進学後の学費軽減給付型奨学金の条件として英検を指定する大学も多いです。3. 大学生活を充実英語力を認められることで、留学や国際交流のチャンスも広がります。充実した大学生活を送るためには、早期の準備が重要です。 特に、志望大学の奨学金制度を調べ、英検資格が条件の場合、早めに準備を始めるのがお勧めです。英検取得には、早くても1ヶ月は最低かかります。 英語力は、進学や就職において、不可欠なスキルです。 大学生活をより充実させるために、英検を取得し、奨学金の恩恵を最大限活用しましょう。教育相談・セカンドオピニオン・転塾相談・他塾との併用相談受付中!
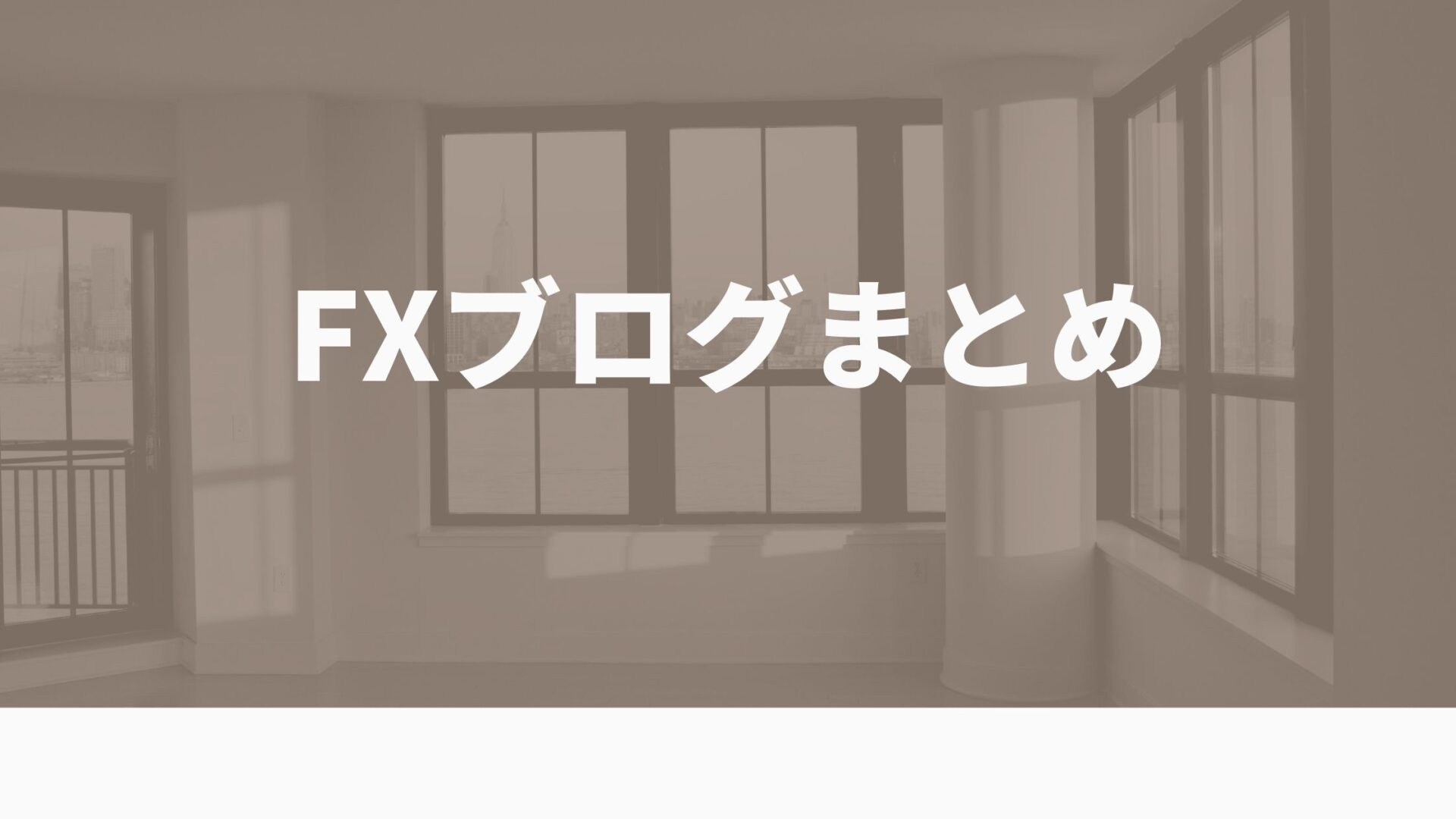


コメント