
参考レート 186.87円 4/11 1:36
パラボリック 193.65円(実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆)
移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆)
5日移動平均線 188.11円(前営業日189.00円)
21日移動平均線 192.20円(前営業日192.46円)
90日移動平均線 192.63円(前営業日192.68円)
200日移動平均線 193.44円(前営業日193.53円)
RSI[相体力指数・14日]
36.85%(売られすぎ目安30%・買われすぎ目安70%)
ボリンジャーバンド(買われすぎ・売られすぎ水準目安 周期20日)
2σシグマ[標準偏差]上限 197.43円
2σシグマ[標準偏差]下限 187.05円
MACD指数平滑移動平均・収束拡散指標
MACD[12、26] -0.96 vs -0.15 MACDシグナル[かい離幅 -0.81]
(MACDがシグナルを上回れば買い・下回れば売り示唆。かい離幅も反発・反落の目安)
注;テクニカル指標の解釈の説明は一般例のひとつで、同一の指標でも上記以外に様々な判断基準があります。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
ボリンジャーバンドは テクニカル分析指標の一種です
RSIは相対的な相場の強弱を測るものです。上昇変動と下落変動のどちらの勢いが強いのかを測定する、テクニカル分析の代表的な指標です。
ダイバージェンスとは、価格の動きとインジケーターの動きが逆行する現象です。MACD以外でもRSIやストキャスティクス、RCIなどのテクニカル指標でも使うことができます。
しかし同時に、リスク要因も軽視できません。米中関係やウクライナ情勢といった地政学リスクはいつ表面化してもおかしくなく、その際には一転してリスクオフの円買いが強まる可能性があります。また市場ポジションが円安方向に片寄っているため、いったん円高方向へ動き出すと調整圧力が急激に高まるリスクも抱えています。このように上下双方向に振れ得る材料が混在する中で、短期見通しとしては「慎重な強気」スタンスが妥当と思われます。すなわち、大崩れはしにくいものの上昇余地も限定的で、160~163円程度のレンジ内で緩やかに高値圏を維持するイメージです。テクニカル面でも過熱感があるため、仮に上昇しても一服や調整を挟みながらのゆるやかな上昇になるでしょう。逆に急落局面があれば絶好の押し目買い機会と捉える向きも多いと考えられ、下値では強めの買い支えが入ると予想されます。
MACDは、相場の勢いを確認するためのテクニカル指標です。2本の移動平均線の動向で相場の状況を判断します。相場が上昇しすぎて加熱のシグナルが示現する場合は売り、逆に売られすぎのシグナルが示現する場合は買いを仕掛けます。 2つの移動平均線が近付いている状況を「収束」といいます。逆に拡大している時は「拡散」といいます。
ツール面はシンプル寄りで上級者には不向きとの声があります。テクニカル的にがっつり分析をしたい場合は、GMO FXネオやヒロセ通商がおすすめです。
テクニカル分析の初歩であり、今回利用したMACDとシグナルについて軽く説明したい。
総合的に見れば、ユーロ円は短期的にやや円安(ユーロ高)優勢ながら、不透明要因が多いため上値追いには慎重にならざるを得ない状況です。米欧のインフレ鎮静化と金融緩和期待がリスクオンを支える一方、地政学リスクや米中関係の先行き不安など下押し要因も顕在化し得ます。テクニカル面では上昇トレンドを維持しつつ短期過熱感を示唆しており、160~163円程度でのレンジ形成や調整を経ながらの緩やかな上昇がメインシナリオと考えられます。
オンバランスボリューム(OBV)は、過去の出来高に基づいて将来の値動きを予測するテクニカル分析の1つです。株式市場の出来高は株価の値動きに特に大きな影響力を持つため、OBVは主に株取引で用いられています。 出来高とは、ある資産において特定の期間中に売買が成立した数量のことを指します。OBVを使用しているトレーダーは、資産価値の上昇を伴わない急激な出来高の増加によって市場価格の急騰や急落が引き起こされると考えています。
留意点: ユーロ円が下落トレンドに転じた場合、158円台(21日線付近)や156円台半ば(過去厚い買いが並んだ水準)で下げ止まるかが焦点です (ユーロ/円見通し(為替/FX ニュース):ユーロ円は円安で159円台前半|欧州の軍備をめぐる要人発言が影響か(2025年3月5日) |OANDAマーケットニュース)。これらのサポートを明確に割り込むとテクニカル的には売り圧力がさらに高まり得ます。ただし、急落局面では日銀のレートチェックや当局姿勢にも市場の視線が集まります。特に155円を大きく割り込むような急激な円高が進むと、日本当局から何らかの牽制発言が出る可能性もあり、下値追いにも限界があるかもしれません。従って弱気シナリオでは155~156円を下限目処としつつ、戻り局面では160円近辺が新たなレジスタンスに転換する展開を想定しています。
いまだトレードができておらず、少し焦りを感じていますが、中長期では「負けない」トレードをするためにも、落ち着いて基盤を作り、テクニカル指標についてRCI(順位相関指数)かRSI(相対力指数)も試してみるべきとのアドバイスをいただきましたので、反映しつつ、落ち着いて分析・トレードを試みます。「成行+OCO(2つの注文を同時に発注。一方の注文が約定するともう一方の注文がキャンセルされる注文)」の注文で、徹底した利益確定と損切を行うつもりです。
WikiFXでは、テクニカル分析のやり方から、FX会社の安全性に関する情報まで『今日から役立つFXの情報』を幅広く発信しています。 そして私たちは、FX会社アフィリエイトを一切していません。 だからこそ、正しく・信頼性の高い情報を読者の皆様にお届けする自信があります。
ボリンジャーバンドは、テクニカル分析指標の一種です。この指標は単純移動平均線(SMA)を中心とし、上下に上限のバンドと下限のバンドがSMAを挟むかたちでチャート上にプロットされます。一般的に上下のバンドは、SMAから±2標準偏差(±2σ)となります。また、上限のバンドは抵抗線、下限のバンドは支持線となります。
RCI(Rank Correlation Index)とは、相場の過熱感を測るオシレーター系テクニカル指標のひとつです。日本語では順位相関指数といいます。似たような指標に、RSIやストキャスティクスがあります。
トリガー要因: このシナリオの背景にはいくつかの好材料が想定されます。まず米インフレ指標の鈍化継続やECB高官によるハト派発言などで主要中銀の緩和的スタンスが再確認されれば、市場に安心感が広がりそうです。例として、13日発表の米生産者物価指数(PPI)などでインフレ抑制傾向が示され、来週のFOMCで利下げ観測が高まるような場合、株価上昇・リスクオンで円安が進む可能性があります。またウクライナ停戦交渉の具体的進展や、米中通商協議に関する前向きな報道が出ることもリスクオン材料です。これらが重なれば安全通貨の円は売られやすくなり、投機筋の円ショート積み増しによる自己強化的な円安トレンドが続くでしょう。テクニカルにも162円台のレジスタンスを突破すれば上昇に弾みがつき、買い遅れた投資家の追随買いやストップロスの誘発で一段高となるシナリオです。
ボリンジャーバンド(20日標準偏差±2σ)も確認すると、バンド幅自体は2月下旬以降のボラティリティ上昇に伴い拡大傾向にあります。3月12日時点の価格はバンド上限付近に位置しており、短期的な行き過ぎを示唆しています。実際、直近のユーロ円はボリンジャーバンドの+2σ近辺まで急伸する局面がみられ、RSIと併せ短期的な過熱感をテクニカル指標が示しています (〖テクニカル〗ユーロテクニカル一覧=引き続きRSI・ボリンジャーバンドともに買われすぎ示唆 - 外為どっとコム マネ育チャンネル)。これは上値余地がやや限られる可能性を示す一方で、強いトレンド下ではバンドウォーク(バンド上限に沿った推移)が続くこともあるため、慎重な判断が求められます。

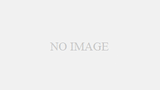

コメント