動画配信期間:公開日から2週間
外為市場に長年携わってきたコメンテータが、その日の相場見通しや今後のマーケット展望を解説します。
主要ポイント
市場状況と概観
4月11日金曜日朝の段階でのマーケット、現在はトランプ大統領の発言に振り回される状況が続いている
特に昨日の「90日間の関税猶予」発言を受け、ドル円相場は144.80円から148円まで急上昇(約4円の変動)
しかし、その後は再び下落し、144円を割る水準まで戻る動きとなり、木曜日の上昇をすべて取り戻す展開に
このような急激な値動きから、短期的に底入れの可能性も示唆されているが…
通貨市場の異常な動き
ドル円以上に大きな動きを見せたのはユーロドル。急激な上昇を記録し、市場関係者を驚かせる
また、ドルスイスフランは特に激しく動き、一日で約330〜340ポイント(ドル円換算で約5円以上)の大幅な値動き
現在のドルスイスフランは0.82レベルで推移。過去の「スイスショック」時には0.7まで下落した経験あり
2011年頃にもスイスフランが異常に強くなった時期があり、当時はスイス中央銀行総裁の辞任騒動にも発展
今回も同様のスパイク(急騰)が起こる可能性があり、まだ1200ポイント以上の下落余地が残されている
金融市場の深刻な懸念材料
米国債金利は連日上昇を続け、3.85%から4.5%への急激な上昇で短期トレーダーは耐えられない状況に
通常であれば「何かが間違っている」とされる米国債、米ドル、米国株式の「トリプル安」が発生
金(ゴールド)が一日で約100ドル上昇し、3188ドル付近まで高騰
米国のCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)が上昇傾向を示し、米国債の信用リスクが高まっている
トランプ政策による経済への影響
トランプ関税が掲げる145%の対中関税政策により、中国から米国への輸出は事実上不可能な状況に
中国からの輸入に依存している医療品、各種部品、半導体などの供給が止まれば米国経済に深刻な打撃となる
毎月多額の貿易黒字を出している中国との貿易が遮断されることによる影響は計り知れない
アメリカでは英国の「トラスショック」と呼ばれる景気後退(リセッション)が発生する可能性が高まっている
米国債市場の異変と今後の見通し
米国債が急落した理由として中国の売却が疑われるが、ベッセント財務長官はこの可能性を否定
米国債の下落はレバレッジ解消(デレバレッジ)やベーシス・トレードの清算、投げ売りが原因との見方も
チャート分析からは、米国債金利は今後5.5%や6%まで上昇する可能性も示唆される
そうなれば現在より1〜1.5%ポイント金利が上昇し、株式市場はさらに10%程度の下落もあり得る
中国との対立と市場の今後
トランプ大統領が90日間の関税猶予を決定したのは、金融市場の混乱に対して実質的に「負け」を認めた形
中国はこの反応を注視しており、金融市場を混乱させることで米国に対抗できると判断する可能性がある
明確な証拠はないものの、中国が意図的に金融市場を混乱させる戦略に出る可能性も否定できない
米国債の信用度低下がトランプ氏の方針転換を促した要因であり、今後も市場の反応次第では政策変更の可能性も
投資家への示唆と結論
現在の市場混乱は投資家にとっては大きな収益機会でもある
特にドルショートやドルスイスのショートポジションが有望な投資戦略として考えられる
市場は引き続き不安定な状況が続くと予想され、投資家は警戒感を持ちながらも機会を見極める必要がある
トランプ政策と金融市場の綱引きはこれからも続く見通しで、更なる市場の乱高下も予想される
最新のマーケット情報

お知らせ:YouTubeでも外為マーケットビューを配信中
外為市場に長年携わってきたコメンテータが、その日の相場見通しや今後のマーケット展望を解説します。

志摩力男 氏
慶應義塾経済学部卒。1988年ー1995年ゴールドマン・サックス、2006-2008年ドイツ証券等、大手金融機関にてプロップトレーダーを歴任、その後香港にてマクロヘッジファンドマネージャー。独立した後も、世界各地の有力トレーダーと交流があり、現在も現役トレーダーとして活躍。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
ドル円は下落を予想 これから起こることは 米トリプル安
25年の豪ドル/NZドルはいずれ下落傾向になるかもしれません。RBNZの利下げペースは鈍化、あるいは利下げが打ち止めになる可能性も考えられる一方で、RBAは利下げを開始するとみられるからです。豪ドル/NZドルの下値メドとして、24年2月安値の1.05655NZドルが挙げられます。
■「プラザ合意2.0」の可能性がまことしやかに語られる背景には、①米国の貿易赤字が歴史的な高水準にあること(図表3)、そして、②貿易加重で見た米ドルの価値を示す実質実効為替レートがプラザ合意以来の歴史的なドル高水準にあること(図表4)が挙げられます。
図3より、1) 20カ月MA(移動平均線)が右肩上がりであること、2) 遅行スパンがローソク足を上放れる“好転”が示現していること、3) ローソク足が青色雲(=先行スパン、サポート帯)の上方にあること、そして4) パラボリック・SAR(ストップ・アンド・リバース)がローソク足の下方で点灯していることから、本稿執筆(24年12月)時点の米ドル/カナダドル・月足チャートは、上昇トレンドを示すチャート形状であると判断します。
つまり、米ドルに対して日本円の価値が下がり、米ドルの価値が上がった状態ということから「円安(=ドル高)」と表現されます。
■こうしてみると、一つの大まかな目安として、日米の短期金利差が5%を下回り、更にドル円の1カ月のヒストリカル・ボラティリティが8%を超えてくると、「行き過ぎた円安」が大きく巻き戻すきっかけとなる可能性が出てきそうです。ちなみに、足元の日米の同3カ月物金利の差は5.31%(6月5日現在)ですので、政策金利に概ね連動して動く短期金利の差は、日米の政策金利が0.31%以上反対方向に動くと、5%の閾値を下回ってくる可能性が高まります。
こうした日本経済の低迷や物価の落ち着きを見て、日銀は、3月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除したものの更なる金融緩和姿勢からの転換に踏み切れずに量的緩和を継続し、6月の金融政策決定会合で国債の買い入れ額を減額することを決めたが、減額の規模は7月に先送りし、慎重姿勢を維持している。本来、金融政策は、為替ではなく経済の状況で決まるのだから、日銀の姿勢は当然である。もちろん、為替市場は、それを見て円安ドル高の動きを強めている。これも、自然の流れである。
最近、起こっている株安・円高はこの逆の事情が働いていると考えられる。海外投資家の中には、日本株の下落に驚いて、日本株を売ると同時に、ヘッジしていた円売りポジションを解消する。これが同額であれば、為替にはニュートラルだが、株価が下落して損失が生じていると、ヘッジした金額の解消の方が大きくなる。ヘッジ解消の円売り=円の買い戻しが円高圧力を生じさせる。
未来のこと、これから創り出していく社会のことを、「&N 未来創発ラボ」で共に考えてみませんか?
野村証券の後藤祐二朗チーフ為替ストラテジストは10日付リポートで、米国は株高、国債利回りのツイストフラット(平たん)化、対円や対ユーロでのドル高と「トリプル安を巻き戻す動き」と指摘した。
日米金利差変化で説明できない160円を超える米ドル高・円安をもたらした原因は、すでに見てきたように過去最大規模に拡大した投機筋の米ドル買い・円売りでした。以上のことから、投機筋による強引な米ドル買い・円売りの反動により急激な円高になったのは当然でしょう。
「トランプ政権2.0ではドル高が進行する」という説をよく見聞きしますが、本当にそうなのでしょうか? 実際、トランプ政権1.0でみられたレンジ相場こそ、28年4月までの 米ドル/円の展開イメージにもっとも合致するものです。
ほかにも、①トランプ減税、②化石燃料使用に寛容なところ、③イスラエル支持で中東情勢が緊迫化しそうな側面、④移民の強制送還、などなどいずれもインフレ要因と見られる。インフレになると、FRBは利下げが進めにくくなる。この思惑が中長期金利の高止まりを招き、ドル高を引き起こしている。
あくまで単純な一例ですが、アメリカが好景気に沸く一方で日本の景気が思わしくないと仮定した場合、日米の金利差が拡大すると予測されます。基本的に高金利の通貨で運用した方が高い利益が見込めるため、お金は金利が低い方から高い方に流れ、米ドルを買う動きが強まって「円安ドル高」になります。
円高とは外貨に対して日本円の価値が上がること、円安とは外貨に対して日本円の価値が下がることです。米ドル/日本円の場合、「1ドル=110円」から「1ドル=100円」に変動した場合を円高、「1ドル=120円」に変動した場合を円安といいます。
すなわち、「1ドル=〇円」の〇の数字が基準よりも小さくなればなるほど、価値が上がるため、「円の数が減ったら円高」「円の数が増えたら円安」と覚えましょう。


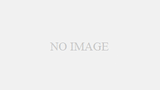

コメント