牛乳安売りする店 物価高でなぜ
しかしそれだけでは、ハンガリーの物価高が EU 1 位である説明はつかず。
プライベートブランド(PB)商品については、価格調査に際して品目ごとに定めた銘柄規定(同品質のものを比較できるように定めた商品の特性等)に合致し、かつ調査店舗で最も売れていれば、基本的に調査対象となり、消費者物価指数に反映されます。例えば、牛乳、食パン、食用油、果実飲料などの食料品では、多くの品目(約7割)でPB商品が銘柄規定に該当しており調査対象に含まれています。
また側面にも『種類別名称:牛乳』と記載しているので、こちらを確認しても判断できると思います!
消費者物価指数で採用している品目は、世帯の消費支出上一定の割合を占める重要なものから構成されており、582の品目があります。世帯が購入する無数の種類の財・サービスは、その機能や価格の動き等の類似性によりまとめられ、各品目に分類されることになります。この品目の中には、品質、規格、容量などの銘柄(スペック)が異なる複数の商品が含まれています。消費者物価指数の作成に当たっては、各品目について、その品目を代表すると考えられる銘柄(スペック)を「基本銘柄」として指定し、毎月、原則としてこの「基本銘柄」に該当する商品の価格を調査します(価格調査に当たっては、「基本銘柄」に該当する商品の中から、各調査店舗で最も売れている製品等を選定し、その価格を継続して調査します。)。品目は5年に1度の基準改定の際に、直近の家計調査結果に基づいて見直しが行われます。ちなみに、2020年の基準改定では、ノンアルコールビール、ドライブレコーダーや葬儀料などを品目に追加しました(D-1参照)。なお、基準改定後に新製品の急速な普及や消費パターンの急激な変化があった場合には、基準改定以外の年においても品目の見直しを行うこととしています(E-1参照)。
「山村牛乳」の1L紙パックの表記ですが、表面の画像赤枠内に『種類別:牛乳』と記載しています。
一見牛乳に見えるのですが、『加工乳』という記載が確認できると思います!
⇒ 選定したスペックを固定し、毎月のPOS情報から全てのスペックに合致する機種を抽出具体的な計算方法については、「2020年消費者物価指数の解説」の「付2 POS情報を用いた品目別価格指数の算出(PDF:597KB)」に掲載されています。
消費者物価指数の価格データを取集する小売物価統計調査では、各調査地区内で、品目ごとに「販売数量の多い代表的な店舗」を選定し、価格を調査しています。したがって、ディスカウント店が販売数量の多い代表的な店舗である場合には調査店舗となり、その価格が反映されることとなります。
消費者物価指数では、基準改定によって採用する品目や計算に用いるウエイトを新しいものに更新するため、改定前と改定後の指数は厳密には内容が異なります。しかしながら、長期的な物価変動を時系列的に分析できるようにするため、基準改定時においては、新旧指数を接続する処理を行っています。新旧指数の接続は、基準年における旧基準と新基準の年平均指数値(新基準は100)の比で、旧基準の指数を換算することにより行っています。接続処理は項目ごとにそれぞれ独立に行い、接続した指数による上位類指数の再計算はしていません。なお、変化率(前月比、前年同月比、前年比及び前年度比)については、接続した指数により再計算することなく、各基準年において公表された値をそのまま用いることとしています。また、各基準の基準年の1月の前月比、1〜12月の前年同月比、前年比及び前年度比についても、旧基準の指数によって計算されたものを用いています。
消費者物価の基調をみるために、「生鮮食品を除く総合」指数や「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」指数が用いられることがあります。「生鮮食品」は天候要因で値動きが激しいこと、「エネルギー」(ガソリン、電気代等)は海外要因で変動する原油価格の影響を直接受けることから、これらの一時的な要因や外部要因を除くことが消費者物価の基調を把握する上で有用とされています。このほか、アメリカ等諸外国で重視されている指標と同様のものとして「食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合」指数が用いられることがあります。なお、「生鮮食品を除く総合」指数は「コア」指数と呼ばれる場合があります。また、このほかにも、「コアコア」指数と言われている指標などがありますが、生鮮食品のほかにエネルギーなどを除く様々な指標に対して様々な名称が用いられているようですので、それらの指標を利用する際は、定義等を御確認ください。
食料品と回答した人が、具体的に物価高を感じているものは「たまご」(92.4%)が最多。以降は「油」(74.1%)、「牛乳・乳製品」(57.7%)の順に多かった。
消費者物価指数には、企業物価指数が対象としていない授業料、家賃、外食などのサービスの価格もウエイトにして5割程度含まれています。サービスの価格は、財に比べて人件費の割合が高いため、財の価格が上昇・低下しても、財と一致した動きをするとは限りません。また、消費者物価指数が対象としている財は世帯が購入するものについてであり、原油などの原材料、電気部品などの中間財、建設機械などの設備機械は含まれていません。したがって、これらの財が値上がりしても、消費者物価が直接上がるのではなく、間接的にしか影響を与えません。このような理由から、消費者物価指数と企業物価指数の総合指数は必ずしも一致した動きをするとは限りません。なお、両指数をできるだけ同じ対象範囲にして比較するため、消費者物価指数の「生鮮食品を除く財」と、国内企業物価指数を「最終消費財」に限定した指数とを比較すると、両者はほぼ同じ動きをしています。
ハンガリー中央統計局によりますと、2022 年 12 月の消費者物価は前年同月比で 24.5 % でした。これほどインフレがひどいのは 1996 年以来のこと。
住宅や土地の購入は、財産の取得であり消費支出ではないことから、消費者物価指数に含まれていませんが、持家に住んでいる世帯(持家世帯)が、自分が所有する住宅からのサービスを現実に受けていることは確かです。そこで、何らかの方法で持家世帯の住宅費用を測れないかという問題がでてきます。持家世帯が住んでいる住宅を借家だと仮定すれば、そのサービスに対し当然家賃を支払わなければなりません。そこから、持家の住宅から得られるサービスに相当する価値を見積もって、これを住宅費用とみなす考え方が成り立ちます。このような考え方に基づいて、持家を借家とみなした場合支払われるであろう家賃(これを「持家の帰属家賃」といいます。)を消費者物価指数に算入しています。指数の計算に当たっては、総務省で実施している全国家計構造調査において推計された持家の帰属家賃額を基に、住宅の構造及び規模ごとにウエイトを求め、それに対応する持家の帰属家賃の価格変動は、小売物価統計調査で調査している民営借家の家賃の価格変動を用いています。このように、消費者物価指数には、土地や住宅の購入費そのものは含めていませんが、帰属家賃方式により持家世帯の住宅費用を算入しています。 なお、この帰属家賃方式は、多くの主要国で消費者物価指数のほか国民経済計算(SNA)でも用いられています。
現在物価高を感じている項目の1位は「食料品」(98.3%)だった。以降は「電気」(88.5%)、「日用品(洗剤やトイレットペーパーなど)」(70.6%)と続いた。

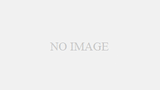
コメント