動画配信期間:公開日から2週間
動画の内容をギュッと要約
トランプ相場の状況と影響
トランプ氏の「関税」方針による市場への影響が継続している状態
4月2日に「開放記念日」として関税政策を打ち出したが、その後の市場反応は良くない
具体的影響:ドル安進行、アメリカ株式市場下落、日本株式市場下落、円高傾向が継続
トランプ大統領は「私のおかげで物価が下がった」と自賛しているが、これは前向きな物価低下ではなく
アメリカが景気後退に陥るという懸念の下でのインフレ低下であり、むしろ悪い兆候と言える
関税政策の実施が二転三転し、市場に不安定さをもたらしている
関税政策の混乱と延期
当初2月に発表予定だった関税政策が3月、4月と延期され続けている
現在は「相互関税を90日間停止する」方針を表明している状態
スマートフォンの関税免除など時に譲歩する発言を出すものの、翌日には否定するパターンが繰り返されている
この政策の揺れ動きが市場の不安定要因となっている
植田日銀総裁の発言と円相場
植田日銀総裁は関税による「悪いシナリオ」の方向に経済が向かっていると警告
インフレは低下傾向にあり、実質賃金が上昇するとの見方を示した
この発言を受けてドル円は一時142円台から143円台に円相場が変動
しかし143円台からの上昇(円安)は進まない状況が続いている
トランプ政権の政策矛盾と課題
トランプ政権は減税政策実行のために巨額の資金調達が必要な状況
議会には債務上限引き上げを求める必要があり、政治的駆け引きが発生
関税収入でアメリカを潤すという政策選択は経済学的に疑問視される
イエレン元財務長官は「自損事故であり、海外企業がアメリカに戻ることはない」と強く批判
「関税をかけてアメリカの製造業を取り戻す」という主張には論理的矛盾がある
製造業が戻れば関税収入はなくなるため、両立しない政策目標
関税や保護主義的政策はアメリカ経済にとって長期的にマイナスとの見方が一般的
トランプ政権誕生の背景分析
コロナ禍による物価上昇がトランプ支持の大きな要因
アメリカ人はバイデン政権下でのインフレ抑制失敗を批判
実際にはバイデン政権は8-9%のインフレを3%程度まで抑制しており、国際的に見ても悪くない成果
しかし、物価上昇による生活苦を抱える有権者をトランプ氏の演説が引き寄せた
イーロン・マスク氏の資金提供なども影響し、政権交代に至った
政策の良し悪しよりも、現状への不満が投票行動を決めた面が大きい
米中関係の悪化とグローバルサプライチェーンへの影響
中国政府がボーイング社製航空機を今後購入しないと表明
以前は300機以上購入していた中国が欧州エアバス社に調達先を切り替える可能性
これはアメリカ航空産業に大きなダメージをもたらす可能性がある
関税政策によって中国の敵対心が高まっており、様々な分野での報復措置の懸念
重要イベント:パウエルFRB議長講演
日本時間明日の2時30分頃に予定されている講演に市場の注目が集まる
FRB地区連銀総裁たちは慎重姿勢を強めており、経済悪化すれば利下げの方針を示唆
大手銀行CEOも「リセッションにならない」「パニックにならない」と言及しているが
このような発言自体が危機感の表れとも解釈できる
実際に経済指標は悪化傾向にあり、FRBの政策転換の可能性が高まっている
日本経済の構造変化の兆し
貿易統計の好転:2月が黒字、3月も黒字に転じる見込みが高まる
原油価格の下落が最大の要因(60ドル台に低下、一時60ドルを割る場面も)
日本の貿易赤字は大幅に縮小傾向にある
歴史的背景:日本は1981年から2010年まで30年間連続で貿易黒字を記録
この期間は円高が進行し、240円から75円まで円高になった時期と重なる
もし原油がさらに下落し50ドルを割れば、日本の貿易黒字時代が再来する可能性
トランプ氏は「貿易黒字は良く、赤字は悪い」という見方をしているが
実際には貿易黒字時代の日本は「失われた20年」と呼ばれる低成長期だった
貿易赤字は物を購入して自国の資産が増えていることを意味し、必ずしも悪いことではない
日本の貿易黒字時代は製品の「叩き売り」状態で収益が上がらず、デフレが進行した時代でもあった
日本の個人投資動向:外貨投信の状況
NISAの影響で拡大してきた外貨投信残高が1月、2月と減少傾向
外貨投信は相対的に予測が難しく、為替変動の影響を受けやすい
昨年は28兆円程度のネット買い越し状態で、円安を支える要因となった
今年はその勢いが減速している
政府は65歳以上の高齢者向けに優遇条件付きの投資制度を検討中
しかし、円が大きく介入されたり利上げされれば、株式市場は大きなダメージを受ける可能性がある
日本の経済指標の悪化傾向
最近の経済指標は概ね悪化傾向:
製造業の景況感悪化が続いている
製造業・サービス業のPMI指数も悪化
景気動向指数が下降
消費者態度指数も悪化傾向
インフレだけに注目していると景気全体の悪化を見落とす危険性
植田日銀総裁の「インフレは低下してきて実質賃金が上がる」との発言は
インフレ上昇が止まりつつある可能性を示唆している
日本の政治と為替政策への懸念
自民党も野党も円高志向の発言が増えている
NHKの「日曜討論」では両党とも円高を肯定する姿勢
石破首相の政権において、赤沢経済再生大臣の発言も注視される必要がある
為替市場において日本側があまり発言しない方が良い状況にもかかわらず
「円高」に向けた政治的発言が増えていることは懸念材料
ベッセント財務長官は「強いドル」を望んでいる状況で、日本側の為替発言は摩擦のリスク
グローバル経済の構造変化の可能性
アメリカの保護主義的政策によって世界経済の分断化が進む可能性
トランプ氏の減税政策実現のための関税政策は様々な困難に直面している
製造業の海外移転は比較優位の理論に基づく経済合理性があり、政策的に戻すのは困難
工場や人材の移転には大きなコストがかかり、簡単に戻せるものではない
日本でさえ円高で海外移転した工場を円安になっても国内に戻していない現状がある
中国の報復措置などによる予期せぬ悪影響も懸念される
欧州経済圏の状況
ECB(欧州中央銀行)は今週0.25%の利下げを予定している
ユーロ圏の経済指標も悪化傾向にあり、金利上昇だけでは景気回復は難しい状況
イギリスは2月のGDPが予想を上回る改善(前月比0.5%増、予想0.1%増)
欧州通貨(ポンド、ユーロ、スイスフラン)は全体的に強い傾向
スイスフランが安全資産として買われている状況
中国も金を積極的に購入しているという報告がある
全体としてトランプ政権の不安定さから安全資産への逃避が進んでいる
オーストラリア・ニュージーランドの状況
両国とも中国への貿易依存度が高く、中国への課税政策に対して敏感に反応
株価は全体的に安い傾向が続いている
オーストラリアは5月3日に総選挙を控えている
世論調査では保守連合39%、労働党31%、緑の党12%と接戦状態
どちらが勝っても連立政権になる可能性が高い
与党は171億5000万ドルの追加所得減税を打ち出している
オーストラリア・ニュージーランドの経済は中国市場と資源価格に大きく依存
ニュージーランドは5回連続で利下げを実施中で、5月も利下げの可能性が高い
インフレは前年比2.3%と落ち着いている状況
総括と今後の展望
トランプ政権の関税政策を軸とした「トランプ相場」は市場に不安定要素をもたらし続けている。原油価格の下落により日本の貿易収支は改善傾向にあるが、各種経済指標の悪化や円高志向の政策発言は懸念材料である。
世界的には、アメリカの保護主義的政策により国際関係の悪化と経済分断が進行しており、特に米中関係の悪化が様々な産業に波及する可能性がある。製造業の「国内回帰」はコスト面から実現困難であり、関税政策による経済的メリットは限定的と見られる。
当面は今夜のパウエルFRB議長講演が最大の注目点となり、FRBの金融政策転換の可能性が市場の焦点となる。欧米の利下げ傾向が強まる中、日本の金融政策と為替政策のバランスも重要な局面を迎えている。
トランプ政権の関税政策は実施が先送りされる傾向にあり、完全に撤回される可能性も否定できない。世界経済は、この不安定要素を抱えながら、インフレ抑制と景気維持の難しいバランスを模索する状況が続くと予想される。
お知らせ:YouTubeでも外為マーケットビューを配信中
外為市場に長年携わってきたコメンテータが、その日の相場見通しや今後のマーケット展望を解説します。

野村雅道 氏
FX湘南投資グループ代表 1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行。82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。 87年米系銀行へ転出。外資系銀行を経て欧州系銀行外国為替部市場部長。外国為替トレーディング業務ヴァイスプレジデントチーフディーラーとして活躍。 財務省、日銀および日銀政策委員会などの金融当局との関係が深く、テレビ・ラジオ・新聞などの国際経済のコメンテイターとして活躍中。為替を中心とした国際経済、日本経済の実践的な捉え方の講演会を全国的に行っている。現在、FX湘南投資グループ代表。
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
裏目に出たトランプ関税 ドル安 世界の経済分断が進行原油下落が日本にもたらす事
駒澤大学法学部教授 2025年、先の敗戦から80年を迎える。本年は同じく1945年の女性参政権実現80年であり、1925年の男子普通選挙制導入100年にもあたっている。2024年は世界的な選挙の年として注目された。日本でも与党が衆議院で過半数割れを起こして難しい政権運営を迫られている。また地方でも震災・豪雨災害の発生や県知事の辞任と再選など高い関心が注がれた一方、地方メディアが地方の問題を地方の文脈で報じる体力の低下が危惧されている。 日本のデモクラシーは占領下で与えられたものか。都道府県知事の公選も占領下で始まった。しかしアフガニスタンを見ても、デモクラシーは与えられたからといって長く続くものではない。日本の場合は19世紀半ばの対外関係の激変を受けてまず立憲政治が選択導入され、その後の政治過程の中で第一次世界大戦後には政党間での政権交代が「憲政常道」と呼ばれ、当時の国際協調の中心国の1つともなっていた。しかし、満州事変、そして自ら招いた戦争の時代が押し流してしまった。 敗戦後に民主主義的傾向は復活強化された。しかし物語はなお終わらない。立憲政治の習熟に時間がかかったように民主政治も同様であった。再建された国際協調にも、国民との絆にも時間がかかった。戦前、婦人参政権獲得運動に尽力し、戦時の言論人、戦後は参議院議員として長く女性の権利擁護に努めた市川房枝は、戦争はもとより政党政治の喪失を悔やみ、戦後の民主主義の健全化、実質化に努めた。私達日本社会はこの80年間も民主政治の下でマドルスルー(泥をかき分けるように進む)してきた。2025年は阪神・淡路大震災から30年の年でもある。デモクラシーを育て、世界の中で善政と調和を求める私達の取り組みは続く。
多摩大学情報社会学研究所客員教授 近年、新しい組織のあり方を模索する取り組みが世界的に盛んになっている。キーワードは「分散型」である。ブロックチェーンを応用したDAOも分散型組織の例である。分散型組織に注目が集まっているのは、中央集権型組織よりも分散型組織のほうがヒトにとって低ストレス、いわば、よりヒューマンセントリックであるから、という見方がある。これは進化の観点からも予想されることである。中央集権型組織が一般化する以前の数十万年の間、ヒトの祖先は分散型の狩猟採集社会で生活していた。狩猟採集社会での役割分担はメンバー同士の横のコミュニケーションに基づいて決められ、自分の役割以外の領域にまでも強い発言力を有する中央集権的な決定権者は生まれにくかった。ヒトの性質はこうした分散型組織に適応して進化してきており、中央集権型組織に適応するようにはできていない可能性が高い。中央集権型組織にストレスを感じる人が多いのも当然と思われる。それにもかかわらず多くの国で中央集権型組織が存続していることには、相応の理由(必要性)があるであろう。シンガポール国立大学のナラヤナン准教授の研究チームは、AI技術により中央集権型組織の必要性を低下させ、分散型組織への移行を促進する具体的方策を複数提案している。例えば、マネージャー業務をAIで支援し、1人のマネージャーが管理できる部下の人数を増やすことで組織階層の平坦化を図る、などである。このように今日では、進化の観点とAI技術の活用により、ヒューマンセントリックな組織を実現するためのさまざまな具体的方策を作り出すことが可能となった。働き方改革を掲げる本邦もこうしたアプローチを積極的に導入すべきである。
慶應義塾大学経済学部教授 世界的なインフレ、気象災害の多発、ウクライナ侵略やイスラエルでの悲惨な戦争による核の脅威の高まりなど、私たちが直面する政策課題は、長期的な持続性の問題に直結している。財政や通貨価値、地球環境、核兵器管理などの分野で、世代を超えた時間軸での持続性をどのように維持するかが問われている。 世代を超えた時間軸の政策課題を、現在世代だけが意思決定する政治システムで解こうとすると、問題を次世代に先送りする誘惑に抗することができない。財政の健全化、地球温暖化など世代間問題への取り組みが遅れることは、現代人が将来世代の利益を十分に考慮に入れた倫理観や公共哲学を身に着けていないことの自然な結果である。 哲学者サミュエル・シェフラーは、思考実験として「自分の死後に世界が滅びる」と仮定したら人はどう感じるか、と問いかけた。自分の死後に世界が滅びるなら、いま自分がしている仕事や活動の大半が無意味に思われ、人生に価値を見いだせなくなる。自分の死後も将来世代が存続し続けるという確信があり、自分の人生は、世代を超えた人類の営みの一部なのだという確信があって初めて、私たちは日々の活動に価値を感じることができる。 このシェフラーの議論と関連して、「将来世代からの承認」という概念も考えることができる。アクセル・ホネットは人間の活動は他者からの承認を獲得することを目的とする「承認をめぐる闘争」であるという。生の価値が他者からの承認に根拠を持つとしたら、私に承認を与える他者は誰から承認されるのか、とたどっていくと、究極的にはまだ生まれない将来世代に行きつく。無限遠の未来の将来世代からの承認が、われわれ現在世代の生の価値を与えるという「将来世代からの承認」を認めるならば、持続性の問題はわれわれの現在の生に直結する。こうした発想に基づく新しい社会契約論が求められている。
ドイツ在住ジャーナリスト 民主主義の根幹を支えるジャーナリズム。「イズム」という語尾に着目すると、批判的思考や事実と意見の区別など、民主主義の価値観に基づく情報の扱い方を指す。この考えを「情報哲学」と呼び議論を進める。 今日、世界中で民主主義が揺らぎ、SNSの影響力が急増している中、メディア環境は大きく変化した。情報の流通量が爆発的に増え、誰もが情報の受け手であり発信者でもある。このため、多くの国で学校や社会人教育において情報哲学(ジャーナリズム)を学び、読解力と発信力を身につける必要が高まっている。 この観点で日本に目を転じると、「マスゴミ」といったメディア批判に違和感を覚える。というのも、メディアは「ジャーナリズムの容れ物」にすぎないからだ。従来型メディアでも電子メディアでも、大切なのは解読・発信する情報がどういう考えに基づいているかだ。容れ物の批判も時には必要だが、本質的には情報思想を問うべきだ。 さて、投票は民主主義の氷山の一角で、自主的な共同体が、より重要な役割を果たす。趣味の集まりから社会貢献まで、形はさまざまでいい。そこで情報哲学を身につけた人々が実際に交流を深めることで、意見形成の力や情報発信する能力が磨かれていくだろう。 そのためには、地域のコミュニティ活動を支える環境づくりが欠かせない。「場づくり」など具体策に加え、例えば労働時間・通勤時間の短縮を「個人の可処分時間増加」政策とすると、コミュニティの参加が容易になる。社会構造をデザインする観点がカギだ。 信頼でき、活気のある民主主義。それは民主主義に沿った情報哲学の教育と、地域のコミュニティ環境への投資にかかっていると思う。
Forbes JAPAN執行役員 Web編集長 「食ほどその国のエンジニアリングを具現化したものはない」、そんな風に感じることがある。 電子国家として注目されるエストニアを訪ねたとき、スルトゥという伝統料理があることを知った。それは、豚肉や玉ねぎ、人参等の素材を活かしたまま煮込み、ゼラチンで固めたゼリー寄せだ。仏の食文化であるパテのようにすりつぶして複雑化させるわけでもなく、ゼリーという半透明で弾力に富んだ枠組みの中で、1つひとつの素材を十分に活かす。これが他国の人をも電子住民として受け入れる、垣根の柔軟性ある彼の国のあり様を象徴しているように見えた。 では我が国家はどうだろう。和食は、素材本来の持ち味を大切にし、精緻な技術を使いながら立体的に表現していく。また、「混ぜる」ではなく「和える」という言葉を用いる。これはミックスして別のものを作るのではなく、それぞれの違いを尊重しながら、調和をさせるということらしい。 日本は聖徳太子の時代から「和」を尊重してきた。 この精神はこの今の時代こそ活きてくるようにも思う。 昨今、コンヴィヴィアリティという言葉が盛んに聞かれるようになった。「自立共生」と訳されたり、「共愉」などとも表現される。マズローの5段階欲求を見ると、テクノロジーの進化により、少なくとも先進国においてはそれぞれの欲求が満たされるようになってきた。この最後の欲求たる「自己実現」の先にある欲望こそがこの「コンヴィヴィアリティ」、つまりは共に喜びを分かち合える社会なのではないか。 そんな社会において、私たちの持つ互いを尊重、協力し合う「和す」精神はこの国内のみならず、混沌を増す世界の中においても一種の調和的な役割を担えるはずである。
公益財団法人国際金融情報センター理事長 気候変動と少子化という2つの構造的課題には、共通した側面が多い。どちらも静かにしかし確実に事態は進展していくが明白な危機が訪れることは無く社会変革への起爆剤に欠けるため、とめどなく状況は悪化していく。両者の決定的な違いは、気候変動については誰が(全世界が)何を(温室効果ガスの排出を止める)すればいいかがわかっているのに対し、少子化はそれぞれの国単位で取り組まざるを得ず、かつ明快な処方箋が無いことである。かつて少子化対策のモデルとされその政策に関心が集まった国々でも出生率が再低下している。これまで少子化対策として議論し実行してきた政策と出生率との関係ははっきりしない。必要な取り組みが科学的にも証明されている気候変動でも、それがエネルギー転換のみならず人々の考え方・行動に至るまで広範な社会的・経済的変革を迫るものだけに、対応が順調に進んでいると考える人はいないだろう。 こうした課題に対し、問題の根本原因に取り組まねばならないと考えるのは当然だ。温室効果ガスの排出を止め出生率を劇的に上昇させることこそが必要で、そのための努力を怠ってはならないという議論にはあらがいにくい。しかしわれわれの「勝利」への展望は開けていないのだから、おそらく不可避である気候変動の激化や人口減少に現在のシステムをいかに対応・変化させていくかの議論も同時に進めなければならない。気候変動で言う「緩和」への努力と「適応」のバランスを考える時期に来ている。人口減や自然災害の激化・気候難民の発生などを前提にするとわれわれは何をしたらいいか、敗北主義と言わずに選択肢を考えてみよう。つらいけれど。
慶應義塾大学名誉教授 パノフスキーは「人間はその背後に記録を残す唯一の動物である」と言っている。15世紀の印刷技術の普及により「出版物」となった知識は世界に流通するとともに図書館で保存されてきた。現在、社会における情報のデジタル化が進み、紙の出版物をデジタル化することでいつでもどこからでもアクセスできる知の基盤の構築は部分的にではあれ進んでいる。 これまで偶然もしくは特殊なものしか残ってこなかった個人の多様な記録は、ウェブやSNS等で社会全体に拡散されている。出版物はオングのいう「閉じたテクスト」であり、そこでは情報を構造化して示し、利用しやすくする多様な試みがなされてきた。しかし、デジタルで生み出され流通する情報は常に流れ続けるのが特徴で、この固定化しない大量の情報を保存する意義は理解されず、社会的な制度としてはほぼ保管されていない。 人類はその活動とともに記録を生み出す存在であるなら、その記録を保存することの意味は将来への信頼ではないのか。今、利用されなくても、将来その膨大な情報が体系化され役立つ可能性を信じて、この社会における課題を解決するために、新たな知識を生み出していくために、過去のそして現在の記録の集成は必須ではないのか。現在のデジタル化した社会において、伝統的な出版物の保存の制度だけではデジタル知の基盤を構築することは不可能である。デジタルな情報の収集や保存に関する多様な反対や漠然とした忌避感は、技術的な問題以上に大きな課題である。デジタルな知の基盤は将来の人々への贈り物であり、現在を生きるわれわれから将来への信頼の証であることをいかに伝えていくかが問われている。
トランプ大統領は日本との貿易交渉の担当者に、ラトニック商務長官ではなくベッセント財務長官を指名した。しかも、自動車やコメに加えて為替(ドル/円相場)のありようが、中心議題の1つになる見通し。ベッセント長官は日本に強い関心があり、「アベノミクス相場」で稼いだ人物。長官就任後には植田日銀総裁と電話会談を行っており、日銀の金融政策正常化の遅さに不満を抱いているようだとの話もある。そして、参院選を控えて物価高につながる円安地合い継続に苦慮する石破首相と、円安に不満を抱いているトランプ大統領の組み合わせである。円高を促す方向で、日銀も巻き込む形で何らかの動きがあるのではないかという思惑が刺激される。
東京学芸大学先端教育人材育成推進機構准教授 日本各地における外国人材の受入れは、人口減少や高齢化の進行を背景に、地域経済を支える重要な人材として、今後益々増加することが予想される。帯同される外国人児童生徒も、未来の日本社会を担う貴重な存在である。国は、日本語教育・指導を中心に施策を進めてきているが、かれらのもつ多様な言語・文化的背景を尊重し、より良い多文化共生社会づくりに積極的に参画する多文化市民の育成を充実させる必要がある。 学校では、コロナ禍を経て、新規に来日する子どもが増えている。同時に、日本生まれ育ちの外国ルーツの児童生徒も増加している。日本生まれ育ちの子どもの多くは、日本語での日常会話には問題ないが、教科書を読んで内容を理解したり、まとまった文章を書いたりすることに課題があり、学習に必要な言葉の力が日本語も母語も年齢相当に十分でない子どもが少なくない。言葉の力は、思考力や人間性の基盤となるものである。就学前段階から、かれらに対する日本語や母語を含む複言語環境を活かした言葉の力を伸ばす教育の充実が求められる。 中学校では、高校進学に向けた教育や支援が必須である。外国籍の生徒にとって、高校進学と卒業は、在留資格との兼ね合いにおいて、日本で安定的な生活基盤を築けるかどうかに大きく関わる。しかし、日本語能力が十分でない生徒に、一般入試のハードルは高く、外国人生徒の特別の定員枠をもつ高校もあるが、対応は自治体間で差がある。また、入学後に日本語や教科学習の適切な支援が受けられず、留年・中退をするケースもある。高校では卒業後の進学・就職等、多様な進路に向けたキャリア支援も必要である。高校での外国人生徒の教育体制の整備は、喫緊の課題である。 外国人生徒も日本の生徒も、多文化共生社会の市民性の育成と、生徒の希望に沿うより良いキャリア形成に向けて、幼保・学校・産官学・地域社会等、日本社会全体で連携し、格差なく取り組むことが求められる。
株式会社マネーフォワード執行役員グループCoPA 2024年に最も注目された政策ワードは「103万円の壁」であった。議論では手取りの増加から男女共同の社会参画、働き方の変革などさまざまな思惑が交差したが、これは政策の広報における1つの敗北事例だったのではないか。 林正義著「税制と経済学」(2024年、中央経済社)に詳しいが、2018年以降、一般的な配偶者の就労抑制が起きそうな制度の壁は、税ではなく社会保険の扶養判定の基準である130万円の水準にある。しかし多くの調査では依然として103万円での壁が観察されており、政策の改善にも関わらず理解がアップデートされずにいる。今後も同じような議論が起こりかねない中、最も貴重なリソースである時間が費消されている。 配偶者に関する控除という、割と初歩的な税制でもこのような状況が起きる。そして、税・社会保障の世界ではそれ以外にも、そろばん時代を彷彿ほうふつとさせる報酬月額の計算、厳密な公平性・中立性を優先するあまり専門家でも覚えきれない規定など、制度の簡素さよりもさまざまな経緯・理屈付けが優先されている。事態をさらに複雑化させるのは政治が持つ誘因であり、その時々の例外追加が、政治的成果としてアピールされていく。 アテンションエコノミーである現在において、制度のおおまかなメカニズムや意義を理解しない人が増えていくことは想像に難くない。それはひいては、自身の負担・便益だけを関心事としていく流れを形成してしまうだろう。一会計ソフト事業者として、できるだけ制度を身近にする努力をしていければと思うが、同時に「簡素」が税の重要原則であり続ける仕組みを統治構造の中で確保しないと、それは犠牲になり続けると思われる。
滋賀県知事 世界で紛争や侵略が深刻化する中、2024年の日本被団協のノーベル平和賞受賞は、私たちの核兵器廃絶と恒久的な平和の実現に向けた思いをより強くする出来事だった。 私自身も昨年は、沖縄の戦没者を祀る「近江の塔」で慰霊し、県内出身の戦死者の遺骨返還式や、アメリカの非営利団体「OBONソサエティ」が県内のご遺族へ遺留品を返還される場へ立ち合い、戦争の悲惨さと平和の尊さを痛感した。 滋賀県には、戦争体験者の証言や遺留品から過去を学ぶ拠点として平和祈念館があり、私はここを発信地に、子どもや若者へ「のこす」、「ひろげる」、「つなげる」輪をひろげ、戦後90年、100年と平和への思いが語り継がれる社会づくりに取り組みたい。 同時に、そうした社会の実現に向けては、「信頼」が不可欠であると考えている。 例えば現在、滋賀県では「誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動できる、持続可能な地域交通」の実現に取り組んでいる。具体の事例として、厳しい経営が続く地方鉄道を、約8年かけて、地域住民や沿線自治体、鉄道事業者と課題を共有し、私自身が参加して対話を重ね、共感を得ることで信頼関係を構築し、公有民営による運行の存続につなげることができた。 今後、県全域において地域ごとに丁寧に対話し、交通税(仮称)など、負担分担の仕組みもつくりながら、持続可能な地域交通の実現に取り組みたい。 平和なくして夢と希望に満ちた未来はない。このことを強く思いながら、対話を尽くし、信頼を大切に、「未来へと幸せが続く滋賀」づくりに力を尽くしたい。
東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻教授 世界的にも、それぞれの国・地域の内部でも「分断」が強く意識される時代になった。それは経済的階層や政治的な立場の分断だけを意味しない。そもそも世界認識、個々の問題を捉える認識が分断してしまっているのだ。そして、それは2つのイデオロギーによる分断ではなく、もはや極めて多様であり、また問題ごとに分断の様相、相貌が異なっている。極めて複雑で多様な分断を伴う、コンセンサスなき時代だということだ。 世界認識1つをとっても、「先進国と中ロ、イラン、北朝鮮」という対立軸とグローバルサウスを想定する三分論が日本や先進国では主流だが、中国ではそうは捉えない。中国では「先進国と非先進国」という対抗軸で世界を捉え、自らを後者の主導者と位置付ける。グローバルサウスの国々、イスラーム諸国では、それぞれの世界観がある。そして、例えばガザ問題ではマレーシアやインドネシアも含めたイスラーム諸国が一致してアメリカを批判するように、案件別に分断の対立軸は変化する。 ウクライナ戦争以降、日本はアメリカや他の同志国に寄り添う姿勢を一層強くした。その可否は別としても、東アジアに位置し、G7の中で唯一の非欧米国である日本の立ち位置については、より戦略的で柔軟な思考の下に判断されるべきだろう。2025年は国際政治の不確実性がさらに増すことが想定される。日本は果たしてコンセンサスなき時代における、さまざまな亀裂を乗り越え、分断面を架橋するような存在になれるだろうか。自らの立場を固定し、二項対立的な思考に陥り、戦略性や柔軟性を喪失することがないように、自己を律することがまずは必要だろう。
京都大学公共政策大学院教授 2024年は日本を含め世界各地で選挙が行われ、おしなべて現職指導者は厳しい審判を受けた。6月のイタリアG7に参加した首脳のうち、日(岸田首相)、英(スナク首相)、米(バイデン大統領)は退陣したかその予定だし、仏(マクロン大統領)、独(ショルツ首相)、加(トルドー首相)も低支持率に喘あえいでいる。この現職批判の流れを決定づけたのが米大統領選挙であり、トランプ氏が132年ぶりに返り咲きを果たす米大統領になった。 この流れはインフレや移民など経済および社会問題、政治腐敗といった国内問題への不満が主たる背景と考えられるが、複数国で共通した現象となっていることは問題の根深さを示している。20世紀中期にアメリカが主導して国際秩序は、大量生産型工業国家としてのアメリカをモデルとした国内政治経済体制とセットになっていた。ウクライナと中東で2つの戦争が進行する中で起きている現職後退の流れは、戦後秩序が内政、外交両面で時代状況とのかい離が拡大していることの証左と考えられる。西側以外の世界の台頭、工業社会から金融情報資本主義社会への変化、人口構造の転換や地球環境問題の深刻化といった諸要因から起きている構造的現象と見るべきなのである。 戦後アメリカのあり方を正面から批判するトランプ政権の復活は戦後秩序の解体を加速するだろう。それは大きなリスクを伴うだろうが、にもかかわらず、旧体制が打破されていく過程では不可避の試練なのかもしれない。しかし大規模な破壊能力をもつようになった人類にとって、2025年は大破局を回避しながら秩序変革を実現するという難問に向き合う年になるだろう。
グロービズ・キャピタル・パートナーズ代表パートナー 日本が再成長し、社会全体として活力を取り戻すためには、スタートアップの育成が喫緊の課題だ。白地で新産業を立ち上げるのはもちろん、製造業など旧来の基幹産業の再成長のためにもスタートアップ発のイノベーションの取り込みが必要だ。 政府も、「骨太の方針」や「スタートアップ育成5カ年計画」で、スタートアップ育成を力強く推進している。2023年にはスタートアップの資金調達額は9,663億円に達し、上場後も含めると時価総額1,000億円に到達したスタートアップは69社に至る。 次なるチャレンジは時価総額1兆円規模で、産業の核となるようなスタートアップの育成だ。そのためには、1,000億円規模に達したスタートアップをさらに飛躍させることへの注力が必要だ。上場後スタートアップの支援政策の拡充、数百億円規模の資金を供給するグロース投資家の育成、人材の有望領域への戦略的シフトを可能とする労働流動性の向上などだ。 マクロ的には、今、日本はここ20年で最も良いポジションにある。地政学的変化は、半導体の日本回帰、米国と連携した次世代エネルギーの開発、相対的な米国市場へのアクセスの良さなど追い風となっている。構造的な人材不足も、逆手に取れば破壊的イノベーションであるAIのいち早い普及を後押しするだろう。製造業で脈々と培われた生産技術もAIと相性が良い。さらには、伝統的文化に加え、マンガ、アニメなどのポップカルチャーも世界で高く評価されている。 ジャパン・アドバンテージを活用しながら、規模化したスタートアップをさらなる成長のために集中的に支援し、それを支えるグロース資金の担い手を育成することで、世界で勝つスタートアップを生み出せるだろう。
日本国際問題研究所客員研究員 「トランプ2.0」の幕開けが迫る傍らで、欧州でも大変なことが起きている。最近お隣の韓国でも異変が起きた。友人知人と話していると、「世界秩序は崩壊に向かっていて、終末の日が来やしないか」という風に感じている人は少なくない。 筆者も「21世紀には大災難がやって来そうだ」と感じる1人だが、その先も考えたい。「現行秩序のグレートリセットは、同時に人類文明のリスタートにもなる」と。 中世の欧州はペストのパンデミックで人口が激減する惨事に見舞われたが、その後はルネサンス文明の花が開いた。20世紀にも2度の大戦のせいで多くの国の経済社会が大損害を受けたが、それは同時に、世紀の前半に拡大していた貧富の格差をリセットする効果も持っていて、世紀後半の経済成長を支えたとか。 そんな大災難が来るとしたら、気になるのはわが日本と同胞の行く末だ。大災難を逃れる術はないだろうが、われわれはそんな中でも相対的に危難を上手に切り抜けられる国と国民ではないか。 楽観的に考える理由を2つ挙げると、1つは日本人が地震や水害など常襲的に起きる自然災害で「鍛えられて」いることだ。同じ目に遭った時、暴動、略奪が起きて秩序が崩壊する国も多い中で、日本人はヘンな言い方だが「諦めて」苦難に堪えることができる。もう1つは日本語が協調性を育むのに長たけた言語だということだ。集団同調にとらわれやすい欠点と隣り合わせだが、物事は良い方に考えよう。 どの国も災難を切り抜けるのに苦労する中で「日本はどうしてうまくやれているのか?」と問われることがあるかもしれない。そんな時には「教祖になる」などと「大それた」考えは持たずに、控えめに経験談を語ろう。
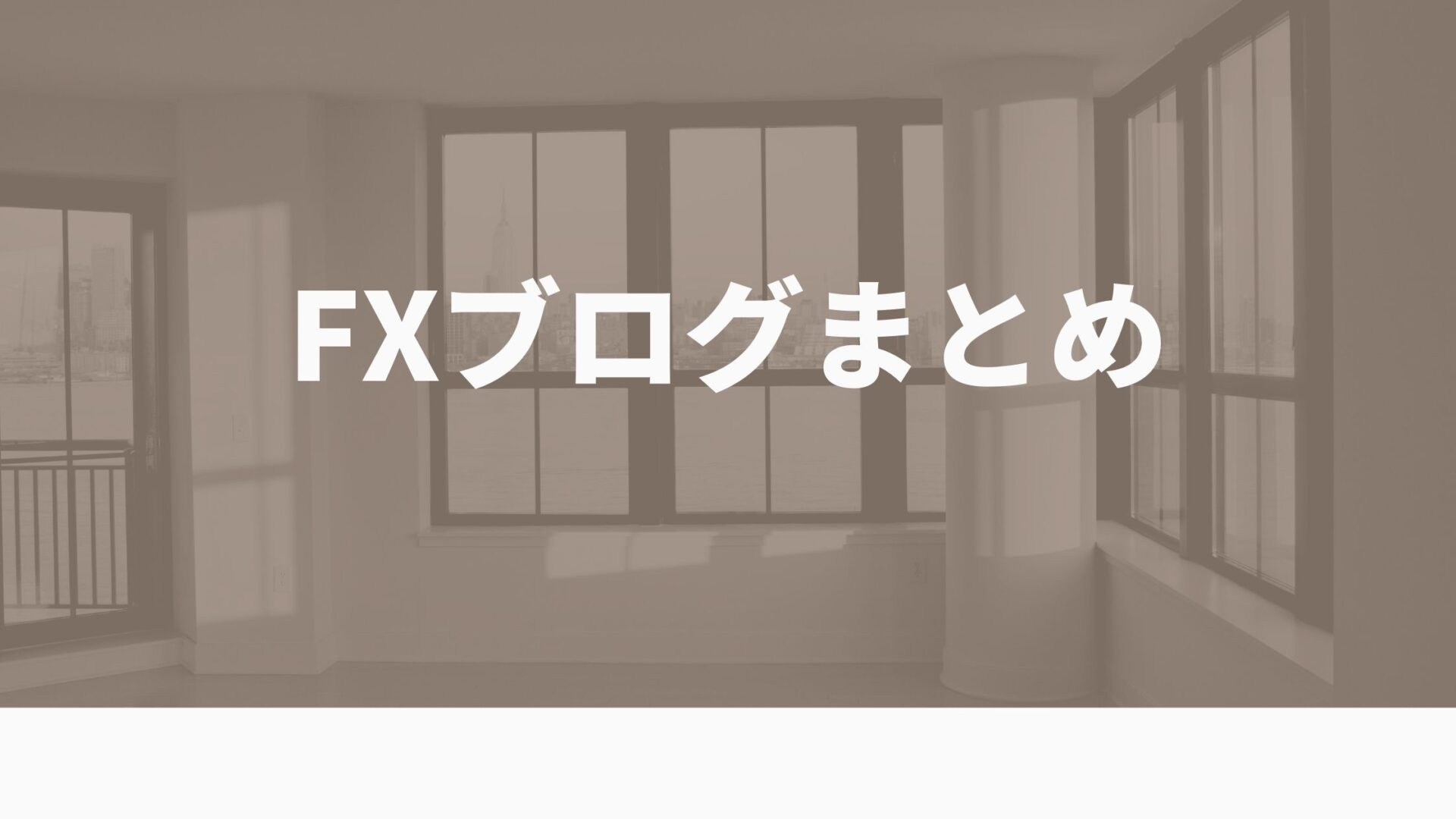




コメント