こうした中 始まった備蓄米の引き渡し
今月10日にはご存じのように政府備蓄米の放出が開始となりますが…。(JAあぐりタウン げんきの郷 浅田貴仁 副店長) 「(米の価格は)落ち着いてこないと思う。まだ、ちょっと高値で続いていく。ことしの米が取れるまでは、まだ(高値が)続いていく気はする」
こうした中、始まった備蓄米の引き渡し。 流通の目詰まりによる政府備蓄米の放出は、今回が初めてとなります。
なぜ備蓄米と表示されないのか、米の価格は下がるのか? 取材しました。
また、全国農業協同組合連合会(JA全農)などによる1月末時点のコメの集荷量が前年同月より23万トン(9%)少ない221万トンだったと発表した。価格高騰で集荷競争が激化しており、減少幅は昨年12月末時点の21万トンから拡大した。 24年産米の収穫量は前年より18万トン多いことから、農水省は「大手集荷業者が競合である中堅・中小事業者との競争で集荷しきれていない」と分析する。また、農家が集荷業者を通さずに知人に配るなどする「縁故米」の在庫を積み増している可能性もあるという。政府は、21万トンの備蓄米を放出する方針だが、集荷量の減少幅の拡大を受けて、対応を迫られる可能性がある。
全国的に米の供給不安や価格高騰が続き、小売りの現場も混乱している。4月に入り、スーパーでは政府が放出した備蓄米がようやく並び始めたものの「売り場に出せば、すぐ品切れになる」といい、「量が少なく、現状では焼け石に水の状態」という。個人店主は「あらゆる米で希望量を仕入れられない」と不安を訴え、「このままでは米が売り場から消えた昨年の『令和の米騒動』の二の舞いになりかねない」と嘆く。 【グラフで見る】コメの小売価格、2年でどのくらい上がった? 政府は既に2回にわたって計21万2000トンの備蓄米を放出。3月下旬からスーパーなどで出回り始めた。4月23日からは3回目の追加放出(10万トン)の入札も始まる。しかし、米5キロの平均価格が14週連続で値上がりするなど市場は不安定で、政府は夏までは毎月、動向をみながら備蓄米を放出する方針を掲げている。 奈良県内を中心にスーパーヤオヒコ14店を展開する八百彦商店(王寺町)は、4月5日に備蓄米5キロ500袋を初入荷。すぐ店頭に並べたが、3日程度で売り切れた。すぐに同数の追加注文を入れたが、次の入荷は早くて5月下旬の見込みという。 備蓄米は複数種類の米が混ざるが、見た目では分かりにくく、同スーパーでは混乱を避けるためにあらかじめ「2023~24年産のブレンド米」と表示。5キロ3180円(税別)で販売していた。安いものでも5キロ3900円(同)以上のその他の商品と比べ、700円以上安いため、物価高に悩む消費者にとって需要が大きく、「1家族1袋」と数量制限しても飛ぶように売れたという。 仕入れ担当者は「備蓄米は家計で苦しむ消費者に対するボランティアのようなもの。通常よりも薄利で販売している」。ただ「多くの客が安い備蓄米を購入することにより、割高な米が売り場に残ってくれるプラスの作用もある」とも話す。店頭在庫を常に確保することにつながり、昨夏のように米自体が売り場からなくなる事態を避けられるためだ。 だが、備蓄米を販売する店舗はまだ十分に広がっていない。 「3月からずっと在庫が少ない。常連客の分を確保するのがやっとだ」。大和郡山市の川西米穀店の店主、正田実さん(57)は諦めた表情で、空きスペースが目立つ在庫置き場を見つめる。 奈良県内の卸業者から奈良、新潟の両県産の4品種を仕入れているが「今は備蓄米に限らず、あらゆる品種で、思うように仕入れができない」と嘆く。1月から入荷数量が前年同期比約6割に落ち込み、3月以降は同約3割にまで減少。仕入れ値が高騰しており、やむなく6日に5キロで500円値上げした。安い米を中心にスーパーでも在庫が足りなくなっていることから、新規の問い合わせは多く舞い込むが、売るものを増やせないでいる。 正田さんは「中小の卸業者は十分に仕入れられず、販売店に届かない。大阪・関西万博を意識して、飲食店や米製品の加工会社などが大口で確保しているのも影響しているのではないか」と指摘。さらに「米を巡る混乱は現時点でも起きているのだから、政府は備蓄米を小出しにせず、まとめた量を放出してほしい」と要望した。【山口起儀】 ◇増田忠義・近畿大准教授(農業資源経済学)の話 米が売り場に行き渡らない事態は、卸売りなど中間業者が今年の収穫期までの需給切迫を見越して在庫をため込んでいるだけでなく、集出荷団体(JAなど)が供給を独占していることも大きく影響している。この状況では取引量が絞り込まれ、取引価格が高く維持されてしまう。そのため、売り場は不足にならない程度の入荷が維持される一方、高値が続く可能性がある。 流通量が絞られているため高値で推移する状況は続きそうだが、2024年産主食用米の収穫量は679万トンで、23年産を18万トン上回っており、24年規模の米不足までにはならないだろう。 備蓄米は複数の収穫年や産地、銘柄を合わせたブレンド米で、食味とともに安全性も気になるところだ。消費者は産地直売所やインターネット通販なども含め、生産者から直接購入先を確保することを検討してもいい。
政府が放出した備蓄米が流通し始めた。大手スーパーの商品棚には既に陳列され、全国で本格的に販売が始まるのは4月以降になる見通しだ。店頭では産地や品種を混ぜた「ブレンド米」の販売が中心となる見込みで、混...
こうした中、始まった備蓄米の引き渡し。 流通の目詰まりでの備蓄米放出は初めてで、備蓄米は今月中にもスーパーなどの店頭に並ぶ見通し。
仙台市太白区にある東北工業大学の八木山キャンパスの学生食堂では、通常は1日でおよそ44キロのコメが消費されるということです。大学によりますと、これまで比較的価格が安い「ひとめぼれ」の古米を使っていましたが、去年の秋から手に入らなくなり、現在は価格が高騰している新米を使用しているということです。大学では、業者に1度に発注するコメの量を増やすなどしてコストを抑えているということですが、これ以上、コメの価格が上昇すれば今のサービスが維持できないとしています。こうした中、市場に安定的に供給するために国が備蓄米の活用を検討していることについて、東北工業大学教務学生課の目黒裕二課長は、「販売価格を上げると学生に影響が出るので、値上げはしていません。いま以上にコメの価格が高騰しなければ、大学としてこれまで同様のサポートができると思うので、今後、議論が進んで、値段がいまより下がることを期待したい」と話していました。

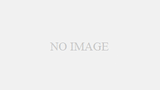
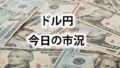
コメント