世界のレアメタル供給 低水準続く
また、世界的には、都市域における水問題も深刻です。水源から供給される水が途中で失われる漏水の問題は、我が国ではほとんど問題とならないものの、世界的には大きな課題となっています(表1-3-1)。例えば、メキシコシティでは35%の水が供給の過程で漏水していることから、仮に我が国と同等の水供給の管理ができるようになったと仮定すると、同じ水源に対して約3割以上もの水資源を節約できることになります。
2023年のニッケルは、インドネシアの増産を背景に世界的な供給過剰となり、価格は軟調に推移した。年初は30,000US$/t台であったが、12月は16,000US$/t台で越年した。2022年3月にLME先物価格が暴騰し、一時的に取引が停止した一件後、LMEでは取引量が減少し、投機筋による一時的な参入で価格が上昇しやすい傾向であったが、2023年は世界的な供給過剰で、基本的に通年下落傾向となった。ニッケルの2023年のトピックとしては、1月に中国青山集団が中国国内の銅製錬所をニッケル製錬所に転換する計画を発表したほか、インドネシアでは6月にPT Halmahera Persada Lygendが国内初の硫酸ニッケル生産を開始した。また、インドネシアは、ニッケル生産国が最適な利益を受けられるよう、具体的な国名は公表していないが、ニッケル版OPEC(石油輸出国機構)の設立を3か国と協議していると公表した。
鉱種別にみると、銅は2019年年初5,839US$で開始し、米中の貿易協議が比較的良好だったことや、インドTuticorin銅製錬所の再開が同国最高裁で認められなかったことに加えて、Freeport Indonesiaがインドネシアで銅精鉱の輸出許可が一時的に認められなかったことを受けて価格が上昇傾向を見せ、3月1日には6,572.0US$/t(2019年最高値)にまで達した。しかし、5月には米中貿易摩擦激化により価格が下落し、7月26日以降は6,000US$/tを下回り、概ね5,600~6,000US$/tにて推移した。亜鉛は、年初2,462US$/tで開始し、中国市場における逼迫感と1990年以来の水準にまでLME在庫が減少したことを背景として上昇傾向となり、4月1日には3,018US$/t(2019年最高値)にまで上昇したが、その後は、LME在庫の増加や米中貿易摩擦の先行き不透明感や、中国亜鉛精錬所が高いTC/RCを背景に増産を進めているとの情報から下落傾向となった。10月には一時上昇傾向に転じたものの、11月~12月にかけては再び下落した。ニッケルは、年初10,440.0US$/tで開始し、Valeのブラジル鉄鉱山ダム決壊事故を受け、世界有数のニッケル生産量を誇る同社のニッケル鉱山操業への影響懸念等を背景に、13,000US$/t台にまで上昇した。その後11,000~13,000US$/tにて推移したが、7月には後述のとおりインドネシアが2022年に未加工鉱石の輸出を再度禁止する方針を示したことや、LME在庫の減少によって急激に上昇し、9月2日には5年ぶりに最高値を更新した。
持続可能な社会の実現のため、環境や経済的な指標だけではなく、人々の暮らしの質を評価する必要性が様々な方面から指摘されています。この生活の質という観点での指標の作成については世界的な試みが進められており、2011年に公表されたOECDによるレポート「暮らしはどうか?(原題"How's Life?")」における生活の質に関する指標群は、2011年に公表された「グリーン成長指標」と並んで、環境・経済・社会の持続可能性の状況を計測するための指標群として重要な位置を占めています。我が国では、新成長戦略(平成22年6月閣議決定)において幸福度指標の検討が盛り込まれ、平成23年12月、幸福度指標の素案が公表されました。同素案では、日本の幸福度について、雇用・所得、教育や住宅などの「経済社会状況」、「心身の健康」、人々のつながりなどの「関係性」という三つの要素からその指標化を検討しています。
森林の用途を見てみると、世界の森林の約3割は生産林として活用され、約2割が土壌・水源・生物多様性等の保護区域として指定されています。この森林の用途を地域的に詳しく見ると、南アメリカやアフリカは、生産林としての利用の割合が低いものの「用途不明もしくはデータがない」とされる森林も多く、これらの国によるガバナンスの確立が重要となります。ヨーロッパやアジア地域では生産林としての森林の利用が中心です。森林の持続的な利用のためには、森林の多面的機能や国や地域ごとの経済状況、気候条件等を踏まえた管理の手法を考える必要があります。
我が国と関係の深い近隣のアジア諸国では、一部を除き、熱帯林を有する多くの国で耕地面積の増加と森林面積の減少がみられます。特にインドネシアやマレーシアでは、近年、世界的なパーム油の生産量の増加とともにパーム油の原料となるヤシの生産面積が増加しており、熱帯林減少の大きな原因となっています。
我が国における絶滅危惧種の減少要因としては、開発、水質汚濁、違法な捕獲、外来種等、人間の社会経済活動が挙げられ、野生生物の種が絶滅への脅威にさらされています(図1-3-9)。また、世界における生物多様性を脅かす要因として、インフラ整備、農地への転換、生息域の分断化、地球温暖化の進行等の脅威が指摘されており、今後もこの傾向は拡大すると考えられています(図1-3-10)。
しかし、単純な技術やシステムの移転だけで、その地域の持続可能な水資源管理ができるとは限りません。身近なものほど大切にする心がけを続けることによって、私たちの日常生活の環境は良好な状態で維持されます。我が国の先進的な技術やシステムに加えて、この心がけを含めて世界へ展開することも、世界の持続可能な社会の実現、ひいては、地球の環境を「べっぴんさん」にする上で大切なのではないでしょうか。
このほかに、ビットコインのマイニング需要によってグラフィックボードの需要が拡大したこと、世界的な規模でのDX(デジタルトランスフォーメーション)あるいはGX(グリーントランスフォーメーション)など中長期的なグローバルトレンドに半導体需要が深く関連していることも、半導体不足に影響していると考えられます。
世界的な精密機械の普及等に伴い、有用性が高い一方で希少性も高いレアメタルに関する注目が高まっています。
亜鉛も、1月に中国需要増加期待により3,500US$/tを突破したが、その後下落に転じ5月の終わりには2,200US$/t付近まで落ち込んだ。しかしこの価格低迷を受けて、収益性が悪化した亜鉛鉱山が次々と操業停止に陥った。最初はスウェーデンBoliden社のアイルランドTara鉱山で、6月にケア&メンテナンスに移行した同鉱山を含め、半年で6つの鉱山の操業が停止された。これらの鉱山操業停止によって世界全体で300千t近い鉱石生産量が失われたとみられており、鉱石市場における供給懸念の高まりが価格の下支えとなって2,600US$/tまで回復した。一方、期を通して実需の低迷継続が強く意識されているほか、中国において需要減退にもかかわらず地金生産が増強された。市場に需給逼迫感は少なく、下半期は2,500US$/t付近を推移した。
EC市場が拡大したことや、世界が「Withコロナ」へと舵を切ったことで、海運の集中による世界的なコンテナ不足も顕在化し。港湾業務に従事する人材が不足するという事態も発生しています。こうした事情から、海上輸送のコストは上昇傾向に陥っているのです。
UNESCOは、普遍的価値を損なうような重大な危機にさらされている世界遺産を「危機にさらされている世界遺産リスト(危機遺産リスト)」として登録しています。現在、危機遺産リストに登録されている15の世界自然遺産のうち、鉱山開発が原因となっているものは、2つあります(ニンバ山厳正自然保護区とオカピ野生動物保護区)。
これらの金属資源は、国内ではほとんど採掘されておらず、海外の鉱山に頼っています。具体的には、我が国は、様々な製品を製造するため、毎年、鉄鉱石約1億3,000万トン、銅鉱石約500万トン、アルミニウム約100万トン、亜鉛鉱約100万トンを輸入しており、世界有数の金属資源輸入国となっています。
2020年の秋以降、世界的な半導体不足が課題として顕在化しましたが、その要因はひとつではありません。また、半導体不足は日本だけに見られる現象ではなく、世界レベルの関心事です。供給のひっ迫と需要の拡大を引き起こす、複数の要因が複雑に絡みあっているのです。

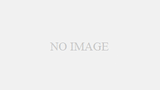
コメント